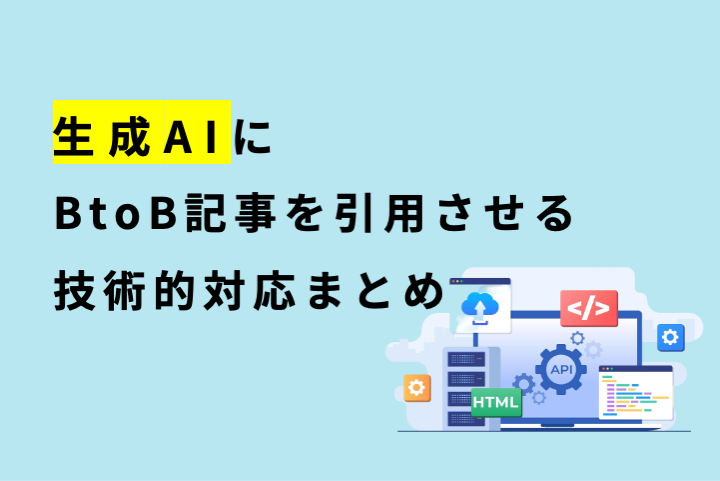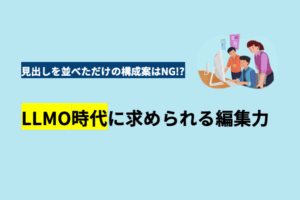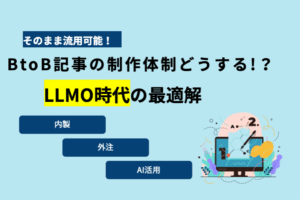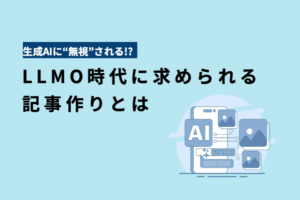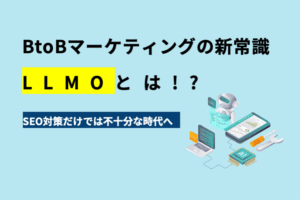ChatGPTに、自社の記事が引用されたことはありますか?
ChatGPTやGoogleのAI Overviewsなど、生成AIがWeb上の情報を引用・要約しながら回答を生成するケースが増えています。
しかし、どれだけ良い記事を書いても、生成AIが参照できる状態になっていなければ、引用されることはありません。
実はその差を生むのが、記事公開後に行うべき「技術的対応」です。
本記事では、自社のBtoB記事がChatGPTなどの生成AIに「拾われる」ために、公開後に必ず押さえておきたい技術対応のポイントを、最新のLLMO(大規模言語モデル最適化)の観点から解説します。
▼ChatGPTに拾われやすい記事制作の基本については、下記をご一読ください。
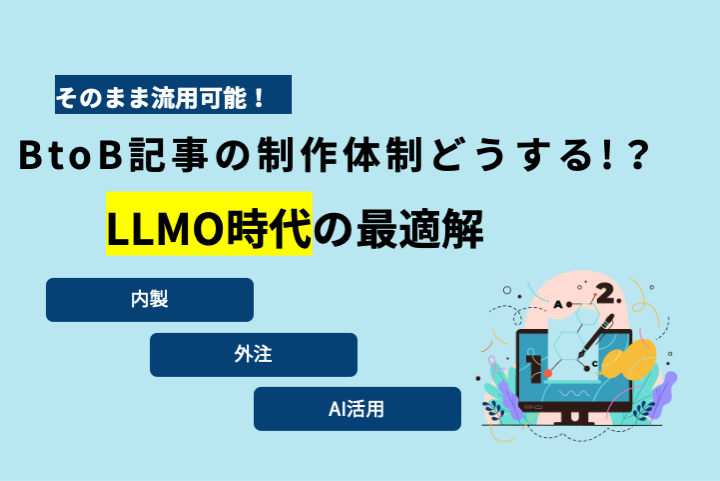
▼LLMOについて基礎から知りたいという方は、下記も参照ください。
ChatGPTをはじめとする生成AIは、どう引用先を決めているのか?
ChatGPTをはじめとする生成AIがWebサイトを引用する仕組みには、大きく2つのパターンがあります。
【パターン①】事前学習 or 埋め込み検索型(RAG)
無料版のChatGPT(GPT-3.5)や、有料版のGPT-4(一部機能制限あり)では、主に事前に学習されたデータセットに基づいて回答が生成されます。
また、RAG(Retrieval Augmented Generation)という仕組みによって、事前に読み込まれた企業独自のナレッジ(例:社内ドキュメントやFAQ)を引用するケースもあります。
これらは、リアルタイムにWebページを検索しているわけではないため、公開後の対策だけでは拾われにくいという前提があります。
【パターン②】Bing連携型(リアルタイム検索による引用)
一方で、Microsoftの「Copilot(旧称:Bing Chat)」や、Perplexityのような生成AIでは、Bingなどの検索エンジンと連携してリアルタイム検索を実行し、その結果をもとに引用や要約を行う仕組みが採用されています。
たとえば、Microsoftは以下のように説明しています。
「Web 検索を有効にすると、ユーザーのプロンプトを Microsoft 365 Copilot が解析し、Web からの情報によって応答の品質が向上する用語を特定します。これらの用語に基づいて、Copilot は、詳細を求める Bing 検索サービスに送信される検索クエリを生成します。」
参考:「Microsoft 365 Copilot および Microsoft 365 Copilot Chat での Web 検索のデータ、プライバシー、セキュリティ」
このように、生成AIのタイプによって「引用のされ方」は異なりますが、共通しているのは以下のポイントです。
・検索エンジンにインデックスされていること
・信頼性の高いドメイン・内容であること
・ページ内の情報が明確かつ、構造化されていること
生成AIに拾われるための技術的対応① 検索エンジンへのインデックス登録
生成AIに引用されるためには、まず記事が検索エンジンに正しくインデックスされていることが大前提です。
特にChatGPTのブラウジング機能やCopilotのようにBing検索と連携するAIに対しては、GoogleだけでなくBing側の対応も欠かせません。ここでは、代表的な2大検索エンジンへのインデックス促進方法を解説します。
Googleサーチコンソールでインデックスリクエストする
記事を公開してすぐに検索結果に反映させたい場合は、サーチコンソールの「URL検査ツール」から手動でインデックス登録をリクエストするのが確実です。
特に、BtoCサイトと比較してページ数や被リンク数が少ないBtoBサイトはクロール頻度が低めになりがちなため、公開直後の手動対応が効果的です。
また、サイトマップ(XML形式)をあらかじめサーチコンソールに登録しておくことで、全体のクロール効率が向上し、記事ごとのインデックス反映も早まります。
Bing Webmaster Toolsを導入する
多くの人が見落としがちなのが、Bing検索エンジンへの対応です。
ChatGPT(Webブラウジング有効時)やMicrosoft Copilotは、Bing検索結果を情報ソースとして活用しています。つまり、Bingで記事がインデックスされていなければ、AIに引用されることはまずありません。
そのため、まずはBing Webmaster Tools にサイトを登録し、サイトマップを送信しておきましょう。
加えて、「URL送信ツール」を使えば、個別ページを即時クロール対象に追加できます。インデックス状況は「インスペクション」機能で確認できます。
Microsoft Clarityを導入してBing親和性を強化する
Microsoft Clarityは、無料で使えるヒートマップ分析ツールですが、Bing検索との連携も持つ点が特徴です。
ページの滞在時間やクリックエリアといったUXデータが蓄積されることで、Bingにおける評価指標にポジティブな影響を与える可能性があります。
また、Clarityで得られるUI改善のヒントは、ユーザー体験の最適化=直帰率や熟読率の改善にもつながり、結果的にAIからの評価にも間接的に貢献します。

生成AIに拾われるための技術的対応② 構造化データとHTML要素の最適化
AIはWebページの表面的な内容だけでなく、HTML構造やメタ情報からも文脈を判断します。
特に構造化された情報(FAQなど)は、LLMが回答を生成する際に非常に引用されやすいため、ここではその具体的な対応策を紹介します。
FAQ構造化データ(schema.org)の活用
生成AI、とくにChatGPT(Webブラウジング有効時)やPerplexityなどは、明確に構造化されたQ&A情報を引用する傾向があります。
このとき効果的なのが、構造化データ(JSON-LD形式)でFAQをマークアップすることです。
具体的には、次のような対応です。

このような構造化データは、記事公開後に追加・修正することができます。
実装後はページに含まれる構造化データで生成されるリッチリザルトを確認できるツール「リッチリザルトテスト」などを活用して、正しく反映されているか確認しましょう。
meta情報やalt属性を最適化する
meta titleやmeta descriptionは、検索エンジンだけでなくLLMによる要約判断にも影響を与える重要な要素です。
特にdescriptionには、記事の要点・構成・対象読者などを端的に記述すると、AIが適切に認識しやすくなります。
同様に、画像に設定するalt属性も、生成AIが「文脈理解」を補完する手がかりになります。
また、意図しないnoindex指定やcanonicalの誤設定があると、検索にもAI引用にもマイナス影響を与えるため、CMSやHTMLを定期的にチェックする体制も重要です。
生成AIに拾われるための技術的対応③ ファイル形式と出力チャネルへの最適化
生成AIの進化により、Webページだけでなく、Office文書やPDFなどのビジネスドキュメントも引用対象として認識されるケースが増えています。BtoBにおけるホワイトペーパーもその対象の1つです。
特にMicrosoft Copilotのように、WordやPowerPointと統合された環境では、ファイル形式の違いがそのまま引用可能性の差につながります。
可能な範囲で、Office形式(Word / PowerPoint)のファイルを用意する
Copilot(Microsoft 365に搭載されたGPT-4ベースのアシスタント)は、WordやPowerPointのファイル内部を直接解析・要約・引用する機能を持ちます。
そのため、ホワイトペーパーや導入事例、営業資料などをWord(.docx)やPowerPoint(.pptx)形式で提供することが、AI引用の入口になる可能性があります。
PDFでのみ提供 → PDFは構造解析がやや難しく、AI側が文脈を正しく把握できず、加工・引用されづらい
pptx形式でも提供 → Copilotがそのまま読み取り、要点抽出・流用がしやすい
ホワイトペーパーの内容もAIフレンドリーにする
生成AIは、「構造的で論理展開が明確な文書」を好みます。つまり、ホワイトペーパーやなどのダウンロード資料は、単に形式を変えるだけでなく、構造そのものの見直しも求められます。
具体的には、
・タイトルの直後に目次を入れ、章立て構成をわかりやすく提示する
・各章の内容が長くなりがちな場合は、最後に要点をまとめたサマリーを設ける
・FAQセクションを追加する(構造化データとしても活用可能)
といった取り組みが推奨されます。すでに配布中の資料をAIフレンドリーな構造に再設計することも十分に価値がある施策です。
生成AIに拾われるための技術的対応④ 信頼性の補強と外部評価の獲得
ChatGPTをはじめとするLLMは、情報の正確性や関連性だけでなく、「その情報源が信頼できるかどうか」を重視しています。これは、Googleで言うEEAT(専門性・権威性・信頼性・経験)に近い評価軸です。
信頼されるサイト構造を整える
生成AIは、信頼性が高いと判断したページを優先的に引用する傾向があります。そのため、サイト全体として「信頼される構造」になっているかを見直すことが重要です。
たとえば、以下のような要素は、AIにとって「信頼の指標」となります。
• サイト全体に企業実体があることを示す要素(所在地・代表者・法人番号など)を記載
• 「会社概要」や「お問い合わせ」ページを明確にナビゲーションに含める
• 必要に応じて特定商取引法に基づく表示ページやプライバシーポリシーを整備
特にBing CopilotやPerplexityでは、引用元のドメイン評価や被リンクの有無といった「信頼性の指標」が可視化される仕組みになっており、こうした要素が実際にAIの引用判断に影響していることがわかります。
そのため、企業情報の明示(会社概要ページの整備やナビゲーションへの設置)、発信実績の蓄積、外部メディアでの紹介などを通じて、サイト全体の信頼構造を強化することが重要です。
まずは、自社サイトが「誰が」「どのような意図で」運営しているかが明確に伝わる状態になっているかを確認し、公開後も継続的に整備・改善を重ねていきましょう。
外部メディアでの掲載実績を獲得する
生成AIは、多くの人やメディアに参照されている情報を「価値のあるコンテンツ」として評価しやすくなっています。
そのため、外部チャネルでの実績掲載は、サイト単体では得にくい信頼性や権威性を補完する手段として非常に有効です。
具体的には、次のような取り組みが有効です。
・PR TIMESやvaluepressでのプレスリリース配信
・業界メディアやBtoBポータルサイトへの寄稿・転載
・自社サイト内に「メディア掲載実績」ページを設置
こうした活動は、SEO効果に加えて、AIが参照するWebデータに対して間接的に“信頼スコア”を渡す役割も果たします。記事公開後は、社外チャネルへの展開も戦略的に行いましょう。
企業・著者情報を明示する
LLMにとって「誰がその情報を発信しているか」は、コンテンツの信頼性を判断するうえで欠かせない情報です。そのため、企業情報や著者情報を公開後に整備しておくことも、重要な技術対応のひとつです。
たとえば、以下のような要素です。
・会社概要ページへのリンク
・著者プロフィール(実名・略歴・顔写真・SNS)
・監修者名や執筆責任者の情報
こうした情報は「ユーザーのため」というだけでなく、生成AIが“この情報は誰から発信されているか”を判断するためのデータとしても活用されます。
技術的なSEO対応だけでなく、信頼の見える化をセットで行うことが、LLMO時代の記事最適化につながります。
生成AIはこう引用する:ChatGPT/Bing Copilot/Perplexityの違い
記事の信頼性や構造を整えても、「実際にどう引用されるのか」が見えないと、その成果を実感しづらいかもしれません。
ここでは、代表的な3つの生成AIツールにおける引用の仕組みと特徴を比較し、どのような記事構成や設定が引用されやすいのかを具体的に見ていきます。
| 生成AIツール名 | 主な引用先 | 表示形式 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT (GPT-4 ブラウジング) | Bing検索 | 回答文中に自然な引用+リンク表示 | FAQ形式・箇条書きを好む |
| Bing Copilot | Bing検索結果 | セクション単位の要約+末尾に出典一覧表示 | メタ情報・見出し構成を重視 |
| Perplexity | Web検索API + リアルタイム検索 | 箇条書き形式で複数の引用元を並列表示 | FAQ構造やJSON-LDなど、構造化データを積極的に参照する傾向あり |
それぞれの生成AIが引用の際に重視する要素には違いがありますが、共通して重要なのは「情報の信頼性」と「構造の明快さ」です。
・ChatGPT(ブラウジング)は、自然な文脈の中でリンクを挿入する形が多く、FAQや明快な段落構成が引用されやすくなります。
・Bing Copilotは、ページ全体を複数セクションに要約し、それぞれに出典を紐づけるため、h2〜h3見出しで整理された情報設計が有利です。
・Perplexityは、引用元の信頼性やデータ構造を重視し、構造化データ(schema.org/FAQなど)を活用している記事を明示的に引用する傾向があります。
技術対応の前に、“土台となる記事”を見直そう
ここまで解説したように、ChatGPTやBing Copilot、Perplexityといった生成AIに引用されるためには、検索エンジンへのインデックス登録や構造化データの活用、Office形式での配信など、公開後の技術対応が重要です。
しかし、それらはあくまで「コンテンツの価値があること」が前提です。
どれだけインデックスを最適化しても、どれだけ構造化データを整えても、記事そのものがAIにも読者にも刺さらなければ、引用されることはありません。
LLMOに強いBtoB記事を“ゼロから作り込む”なら、リードレへ
BtoB企業のマーケティングに特化した支援を行うリードレには、ホワイトペーパーや事例記事、コラムなど豊富なコンテンツ制作実績があります。
検索意図やLLMOの観点を踏まえた構成設計から、専門性と信頼感のある記事づくりまで、ヒアリングを通じて貴社の強みをしっかり言語化し、成果につながるコンテンツをご提案します。
Webマーケティングのコンテンツ作りに課題を感じている方は、ぜひ下記よりお気軽にご相談ください。

自社の既存コラムの内容について、LLMO対応を確認しておきたいという方は、下記の無料チェックリストもご活用ください。