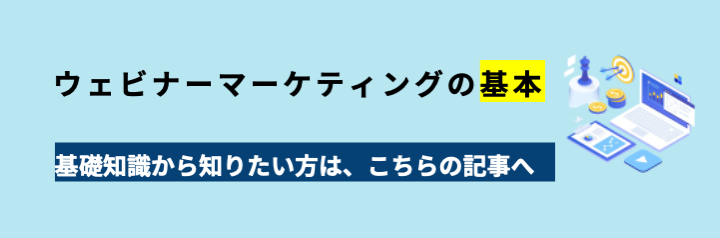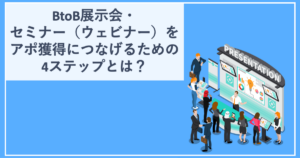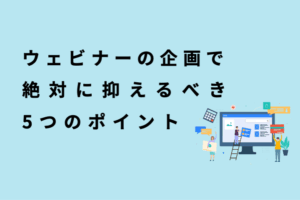ウェビナーを企画する際、「どんな資料を作れば良いか」で悩む方は多いのではないでしょうか。
オフラインのセミナーと違い、ウェビナーでは参加者がパソコンやスマートフォンの画面越しに資料を見るため、
同じ構成・デザインでは伝わりにくくなるケースが少なくありません。
特に、
• 「どのスライドサイズが適切か」
• 「アニメーションはどこまで使ってよいか」
• 「スライド枚数はどのくらいが理想か」
といった基本設計の違いを理解しておくことが重要です。
そこで本記事では、ウェビナーの特性に合わせて資料を設計するための4つの基本ポイントを解説します。
ウェビナー資料は「目的」から設計する
ウェビナー資料は、単なる“説明スライド”ではなく「相手に行動してもらうための設計図」です。スライドを作る前に、「誰に」「何を伝え」「どんな行動を促したいのか」を明確にすることが成果を左右します。
ここでは、オフライン資料との違いと、成果につながる資料設計の考え方を整理します。
オフラインセミナーでしようする資料との違いを理解する
ウェビナー資料を作る際にまず意識すべきなのは、「オフラインセミナーとは視聴環境がまったく異なる」という点です。
| オフラインセミナー | ウェビナー | |
|---|---|---|
| 前提 | 印刷・投影を前提とした構成 | 画面共有を前提とした構成 |
| 情報量 | 詳細な説明文・データを盛り込みやすい | 文字を減らし、図やキーワードで直感的に伝える |
| 目的 | 「読む」資料 | 「見て理解できる」資料 |
| 注意点 | 配布後も読み返して理解できる構成 | 一瞬で内容が伝わる視認性を重視 |
ウェビナーでは、参加者が小さな画面で視聴するケースも多く、スライドに文字や情報を詰め込みすぎると、内容が頭に入ってこないリスクがあります。
そのため、1スライド1メッセージを意識し、「読む資料」ではなく「見て理解できる資料」へと発想を切り替えましょう。
資料作りの出発点は“ゴール設計”
ウェビナー資料を作る際は、スライド構成よりも前に「視聴後の行動」を設計することが重要です。
たとえば、次のようなゴールを明確にすると、構成の軸がブレません。
- 資料ダウンロードや問い合わせにつなげたい
-
導入で課題を提示し、解決策として自社の強みを自然に紹介する
- 別テーマのウェビナー参加を促したい
-
最後に関連テーマを告知して興味を持続する
- 商談化を見据えた関係構築を狙いたい
-
事例紹介や実績データで信頼を醸成する
ゴールを設定したら、「ゴール → メッセージ → 構成 → デザイン」という順番でスライドを設計しましょう。
この流れを意識することで、見た目だけに頼らず“伝わる・行動につながる”資料が作成できるよになります。
ウェビナー資料は“オンライン上の営業トーク”とも言えます。
見やすさだけでなく、「どのスライドで感情を動かすか」を意識することで、商談化率が大きく変わります。
ウェビナーの資料を作る時に必ず押さえるべき4つのポイント
ここからは、実際にウェビナー資料を作るうえで押さえておきたい4つの基本設計ポイントを紹介します。
オフラインのセミナー資料とは異なり、ウェビナーでは「画面越しでどう見えるか」「参加者の集中をどう維持するか」が重要です。
それぞれのポイントを具体的に見ていきましょう。
その1:スライドサイズは16:9に統一
ウェビナー資料の基本は、スライドサイズを16:9(ワイド)に設定することです。
現在ほとんどのパソコンやディスプレイ、ウェビナーツールは16:9に対応しており、画面いっぱいに資料を表示できることで、より見やすい印象になります。
特に、スマートフォンでの視聴者が一定数いる場合は、横長の方がレイアウトが崩れにくく、文字や図も拡大せずに確認できます。
ただし、一部の社内向け配信ツールでは、表示領域が異なるケースもあるため、事前にテスト配信を行い、画面端が切れないか確認しておきましょう。
初期設定のまま「4:3」で作ってしまうと、配信時に上下に余白(黒帯)が出ることがあります。
PowerPointの場合は、必ず「デザイン」>「スライドのサイズ」で16:9を指定してから作成を始めましょう。
その2:アニメーションは「補足」程度に使う
PowerPointやGoogleスライドのアニメーション機能は便利ですが、ウェビナーでは多用しすぎると逆効果になる場合があります。
アニメーションは「段階的に説明を出す」「強調したい部分を一瞬浮かび上がらせる」など、理解を補助するための最小限の演出にとどめるのが理想です。
その3:スライドの枚数はやや多めにする
ウェビナーでは、参加者の多くが“ながら視聴”をしています。そのため、テンポ良く情報が切り替わらないと、集中力が途切れやすくなります。
そこで意識したいのが、スライド枚数をオフラインよりもやや多めにすることです。
ひとつの目安としては、
• 30分のウェビナー → 40枚程度
• 60分のウェビナー → 60〜70枚程度
と考えておくと良いでしょう。
「1スライド1メッセージ」を徹底し、話す内容を細かく区切ることで、アニメーションを多用しなくても自然に“動きのある”構成が作れます。
ただし、高解像度の画像を多用するとデータ容量が重くなり、画面共有がスムーズに進まないリスクがあるため、画像は圧縮やWeb向け軽量化を行っておくと安心です。
その4:用途に応じて3種類の資料を用意する
ウェビナー資料は、「1つ作って終わり」ではなく、目的に合わせて複数のバージョンを用意するのが理想です。
配信中・トラブル時・開催後で求められる役割が異なるため、それぞれの用途に最適化することで、進行の安定性と再利用性が高まります。
| 用途 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 画面共有用 | 当日に登壇者が使用するスライド | 大きめの文字・シンプルなレイアウトで、視認性を最優先。注釈は最小限に。 |
| PDFバックアップ | 不具合時に切り替えて使用 | 画像やフォントを軽量化し、容量を小さくしておく。ツール停止時にも即対応可能。 |
| 配信用 | ウェビナー後に参加者へ共有 | 機密情報・社内向けスライドを削除し、理解補助のコメントやリンクを追加。 |
特に配信用資料は、「当日スライドをそのまま送る」のではなく、“第三者が見ても理解できる形”に再編集することが大切です。
当日聞いていなかった決裁者が後から見ても内容を把握できるようにしておくと、社内共有を通じた商談機会の拡大にもつながります。
3種類の資料を事前に用意しておくと、「当日トラブルへの備え」+「開催後のリード育成」の両面で効率的です。
ウェビナー資料を「ナーチャリング資産」に変える
ウェビナー資料は作って終わりではなく、“営業コンテンツ”として再利用する視点が欠かせません。
せっかく時間をかけて作成したスライドも、開催後に眠らせてしまってはもったいないものです。内容を再編集・再配信することで、見込み顧客との接点を継続的に生み出せます。
資料をホワイトペーパー化してDL誘導に活用
ウェビナー資料の中には、構成やメッセージを整えるだけでホワイトペーパーとして再利用できる要素が多く含まれています。
特に「課題→解決策→成果」の流れを持つスライド構成は、そのままリード獲得用のダウンロード資料に変換しやすい形式です。
- タイトルやリード文を追加して独立した資料に
- グラフや事例スライドを再構成して読み物化
- CTA(問い合わせ・資料請求ボタン)を挿入
こうした加工を行うことで、ウェビナー当日に参加できなかった層にも情報を届けられ、ウェビナーをきっかけとした「リード育成の循環」が作れます。
一部スライドを抜粋してメルマガ・SNS配信
ウェビナー資料の中には、単体で有用なデータ・グラフ・引用なども多く存在します。それらを1スライドずつ切り出してメルマガやSNSに再利用すると、軽い接点づくりに効果的です。
- メルマガでは「ウェビナーで好評だった資料を公開」などの導入で関心喚起
- LinkedInやX(旧Twitter)ではスライド1枚+要約コメントを投稿し、URLへ誘導
- MAシナリオでは既存リードに「ウェビナー抜粋版」として自動配信
ポイントは、“再告知”ではなく“情報提供”として発信することです。営業色が強すぎない情報発信は、既存リードの離脱を防ぎ、信頼関係を維持できます。
ウェビナー資料の作り方でよくある質問
- ウェビナー資料は配布用と当日用で分けたほうが良いですか?
-
はい、目的が異なるため分けて作成するのがおすすめです。
配布用は「説明なしでも理解できる資料」、当日用は「話を聞きながら見る資料」として役割が違います。
当日用は文字を減らし、視覚的にわかりやすく。配布用は注釈や要約を追加し、参加できなかった人でも理解できるよう編集しましょう。
▼下記の記事では、配布・バックアップ・画面共有の3資料の構成を詳しく紹介しています。 - 作成したウェビナー資料は再利用しても問題ありませんか?
-
もちろん可能です。むしろ再利用することでリード獲得効率が高まります。
たとえば、ウェビナー資料を再構成してホワイトペーパー化したり、抜粋スライドをメルマガやSNS投稿に転用することで、ウェビナー参加者以外にも情報を届けられます。
また、録画動画とスライドを組み合わせてアーカイブ公開すれば、継続的にリードを獲得できます。 - ウェビナーの資料はどのくらいのボリュームが理想ですか?
-
30分のウェビナーで40〜50枚前後が目安です。
オフラインのセミナーよりもテンポよく進行する必要があるため、スライド枚数はやや多めが適しています。
1スライド1メッセージを意識し、アニメーションではなく“ページ切り替え”で動きを出すと、通信負荷をかけずに飽きさせない進行ができます。
ウェビナー集客にお困りではありませんか?
ここまで、ウェビナーの資料作りについて解説してきました。
記事内でも触れた通り、ウェビナーは「開催して終わり」ではなく、開催後のアプローチ設計こそが商談獲得、受注につなげる分岐点になります。
多くの企業の中では「当日使用したプレゼン資料」をそのままダウンロード資料として活用していますが、この手法には「ウェビナーに参加していない決裁者への訴求力が弱い」という課題もあります。
こうした課題を解消するためには、ウェビナーの内容をまとめ、説明や補足がなくとも完結するようなホワイトペーパーをダウンロード資料として設置することが有効です。
リードレはBtoB専門のコンテンツマーケティング会社としてこれまでに数多くの企業様のリード・ジェネレーションとリード・ナーチャリングをご支援してきました。
ウェビナーマーケティングの実践をお考えの方は、ぜひリードレまでお問い合わせください。