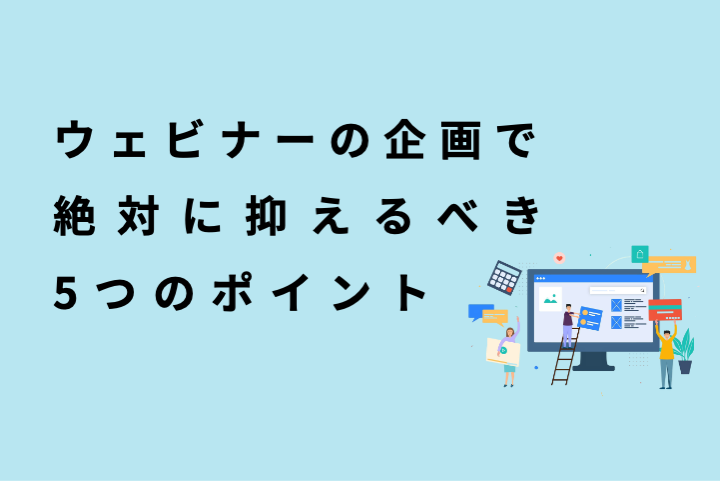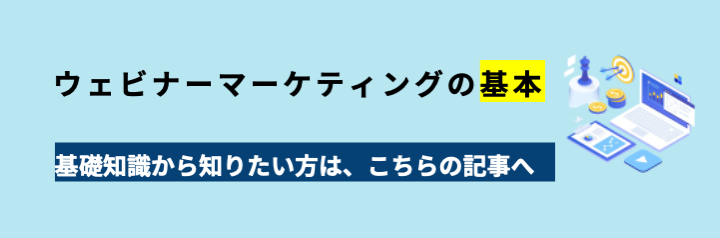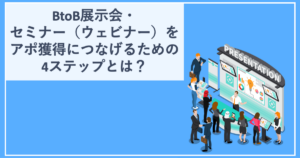「どんなテーマで開催すれば集客できるのか?」
「申し込みは集まるけれど、商談につながらない……」
ウェビナーを企画する際、こうした悩みを抱えるBtoB担当者は少なくありません。
実際に成果を上げている企業の多くは、単に“話題性のあるテーマ”を設定しているわけではなく、企画段階から商談化までを逆算した設計を行っています。
本記事では、他社ウェビナーに埋もれない企画を生み出すために、BtoBマーケティングの実務で押さえておくべき5つの企画ポイントを解説します。
ウェビナー企画とは?成功の鍵は「目的からの逆算」
ウェビナーを成功させる最大のポイントは、“集客ありき”で企画を立てないことです。どれだけ多くの申し込みを集めても、商談や受注に結びつかなければ施策としての成果は出ません。
BtoBマーケティングにおけるウェビナー企画は、最初に「商談化までのストーリー」を描くことから始まります。
目的・ターゲット・テーマを明確にし、営業部門と共通のゴールを設定しておくことで、企画の方向性がぶれにくくなります。
目的を明確にする(認知/育成/商談化)
ウェビナーは“目的によって設計が変わる施策”です。
たとえば、認知拡大を狙う場合と、既存リードの育成を狙う場合とでは、テーマの深さや登壇者の選定も異なります。
| 目的 | ウェビナーの位置付け | 企画の方向性 |
|---|---|---|
| 認知(TOFU) | 新規リード獲得 | 業界トレンド・課題提起型のテーマが有効 |
| 育成(MOFU) | 既存リードの関心維持 | 事例紹介・ノウハウ共有・共催型ウェビナー |
| 商談化(BOFU) | 顕在層へのアプローチ | デモ形式・個別相談型ウェビナー |
このように、「誰に・どんな行動を起こしてもらうか」を明確にすることで、登壇内容やフォロー施策を一貫した流れで設計できます。
ターゲットと課題感を具体化する
ターゲットを「中小企業の経営者」や「マーケティング担当者」といった抽象的なレベルにとどめると、
テーマがぼやけてしまい、他社のウェビナーと差別化できません。
重要なのは、“どんな課題感をもつ人に向けるか”を具体化することです。
- DX推進が進まず、営業活動を属人的に行っている地方企業
- MAツールを導入したが、運用定着に課題を抱えるBtoB企業
- 展示会中心の営業スタイルから脱却できていない製造業企業
このように、課題をベースにターゲットを定義することで、ウェビナーのタイトルや訴求軸がより具体的になり、申込率も高まります。
ウェビナー企画で成果を生む5つのポイント
ウェビナー企画では、テーマ選定や構成を誤ってしまい申し込み数が伸びなかったり、商談化に結びつかなかったりするケースが少なくありません。
ここでは、ウェビナーを成果につなげるために企画段階で押さえておくべき5つのポイントを解説します。
1:テーマは「ワンメッセージ」で統一する
ウェビナー企画で最も重要なのは、「何を伝える回なのか」を一言で言えるテーマ設計です。テーマが広すぎると、内容が散漫になり、結局“誰に響くのか”がわからなくなります。
このように、1回のウェビナーで扱うテーマはできるだけ絞り込み、ワンメッセージ(1テーマ=1ベネフィット)を徹底しましょう。
また、ウェビナーのテーマは 「参加者が検索しそうなキーワード」+「成果に直結する訴求」 の組み合わせが理想です。
複数のテーマを扱いたい場合は、1回に詰め込まず「シリーズ開催」に分けるのがおすすめです。
「全3回で理解できる〇〇講座」など、連続設計にすることでリード育成にもつながります。
2:ワンテーマで実施する
ウェビナーでよくある失敗は、登壇者が一方的に話し続けてしまうことです。
オフラインのように参加者の表情が見えない分、オンラインでは「ながら視聴」が多く、集中力が途切れやすくなります。
そのため、企画段階から「参加者が関われる設計」を組み込むことが欠かせません。
効果的な方法として、以下のような仕掛けが挙げられます。
- 冒頭アンケートの実施
-
テーマに関する質問を投げかけ、結果をリアルタイムで紹介することで、参加者の関心を引き出します。
- チャット質問やリアクション機能の活用
-
「Q&Aタイム」を設けるほか、コメントを拾いながら進行することで、ライブ感と一体感が生まれます。
- 複数登壇者による対談形式
-
講義形式よりもテンポが出て、参加者が感じる疑問を他の登壇者がフォローすることで視聴者が飽きにくくなります。
これらの仕掛けを事前に構成へ組み込むことで、「聞く時間」と「参加する時間」のバランスが取れ、満足度が大きく向上します。
参加設計の目的は“場を盛り上げること”ではなく、“記憶に残すこと”です。
チャット質問や投票の回答をウェビナー後のフォロー(メール・架電)に活用すれば、リードナーチャリングにもつながります。
3:トレンドワードを活用して関心を引く
企画段階で申込率を左右する大きな要素が、タイトルの“引き”です。同じテーマでも、トレンドワードを盛り込むだけで訴求力が大きく変わります。
このように、時流を意識したワードを入れることで、検索やSNS上での露出・クリック率が高まります。
実際にトレンドを探す際は、以下のようなリソースを活用しましょう。
- Googleトレンド:業界に関連するキーワードの検索動向を可視化
- X(旧Twitter)・LinkedIn:ターゲット層が関心を持つ話題をモニタリング
- 展示会・業界メディア:今後伸びるテーマを早期にキャッチ
ただし、トレンドを“話題性だけ”で取り入れてしまうと、自社の強みと結びつかない内容になってしまうリスクがあります。
そのため、必ず「自社の商材・提供価値とどう関連づけるか」を軸に検討しましょう。
トレンドワードは“集客のフック”として有効ですが、コアメッセージの一貫性が最優先です。
一時的な関心ではなく、自社の専門性や信頼を高めるテーマ設計を心がけましょう。
4:開催後のフォローを前提に企画する
ウェビナーの目的は「開催して終わり」ではなく、参加者を次のアクションへ導くことです。そのため、企画段階から「視聴後にどんな行動を取ってもらいたいか」を設計することが重要です。
たとえば、以下のようなフォロー導線を事前に想定しておきましょう。
- 視聴直後: サンクスメール+当日資料ダウンロード案内
- 数日後: 関連ホワイトペーパー・事例資料の紹介
- 1週間以内: アンケート回答者への個別フォロー(メール・架電)
このようにフォローのシナリオを先に描くことで、ウェビナー内容と連動したメッセージ設計が可能になります。結果として、開催後のナーチャリングがスムーズに進み、商談化率も向上します。
また、営業との連携を意識した企画にすることで、フォロー施策の精度も上がります。
「どの情報を共有すれば商談につながるか」を営業とすり合わせておくと、MA(マーケティングオートメーション)によるスコアリングやリード分類にも活かせます。
フォローを前提にした企画では、“誰に・どんな資料を送るか”を明確に決めておくことが鍵です。
企画とフォローの一貫性が、ウェビナーのROIを大きく左右します。
5:企画段階で“共催・登壇者選定”を戦略的に行う
ウェビナーの集客・信頼性を大きく左右するのが、誰と共に開催するか・誰が登壇するかです。共催や登壇者選定は「当日の盛り上がり」だけでなく、集客効果とブランド強化の両立を狙える重要な戦略要素と言えます。
共催のメリット
- 集客チャネルの拡大:自社・共催社それぞれのリストやSNSで相互告知できる
- 信頼性の向上:業界内で実績のある企業や専門家との共催で、参加意欲が高まる
- リードの質向上:同一テーマに関心を持つ層に対して、より深い接点を築ける
登壇者選定のポイント
登壇者を選ぶ際は、専門性 × 親しみやすさのバランスを意識しましょう。専門知識に加え、具体事例や失敗談を交えて話せるスピーカーほど、参加者の共感を得やすくなります。
また、形式を変えることで聞き手の集中を維持しやすくなります。
- 対談形式:異なる立場からの意見交換で内容に深みを出す
- パネルディスカッション形式:複数人での掛け合いによりテンポが生まれる
こうした構成を事前に設計しておくことで、「飽きないウェビナー」かつ「記憶に残るウェビナー」を実現できます。
共催ウェビナーは「テーマ・リード属性・目的の一致」が成功のカギ。
単なるコラボではなく、双方のリード戦略をすり合わせた上で実施することが重要です。
ウェビナー企画でよくある質問
- ウェビナーのテーマはどのくらい具体的に絞り込むべきですか?
-
テーマは「誰の」「どんな課題を解決するか」が明確になるレベルまで絞り込みましょう。
たとえば「製造業のDX推進」では広すぎますが、「中小製造業がDXを進めるうえでつまずきやすい3つの課題」とすれば、ターゲットが即座に“自分ごと化”できます。
テーマを狭めるほど参加率・満足度ともに上がる傾向にあります。 - ウェビナーの理想的な開催時間はどのくらいですか?
-
BtoBウェビナーの場合、20〜30分程度が最も集中力を維持しやすいとされています。60分以上になると途中離脱が増える傾向があります。
内容が多い場合は、「前編・後編」などシリーズ化することで、リード接点を増やす設計が有効です。 - 共催ウェビナーを成功させるコツはありますか?
-
成功の鍵は「目的とリード属性の一致」です。
単に登壇者を増やすのではなく、同じ業界課題を異なる立場から語れるパートナーを選定しましょう。
また、集客時点で“どちらのリストから申込が来たか”を識別できるようにしておくと、フォロー時のアプローチ精度が高まります。
ウェビナー開催後のナーチャリングをご支援!
ここまで、ウェビナー企画について詳しく解説してきました。
記事内でも触れた通り、ウェビナーは「開催して終わり」ではなく、開催後のアプローチ設計こそが商談獲得、受注につなげる分岐点になります。
多くの企業の中では「当日使用したプレゼン資料」をそのままダウンロード資料として活用していますが、この手法には「ウェビナーに参加していない決裁者への訴求力が弱い」という課題もあります。
こうした課題を解消するためには、ウェビナーの内容をまとめ、説明や補足がなくとも完結するようなホワイトペーパーをダウンロード資料として設置することが有効です。
リードレはBtoB専門のコンテンツマーケティング会社としてこれまでに数多くの企業様のリード・ジェネレーションとリード・ナーチャリングをご支援してきました。
ウェビナーマーケティングの実践をお考えの方は、ぜひリードレまでお問い合わせください。