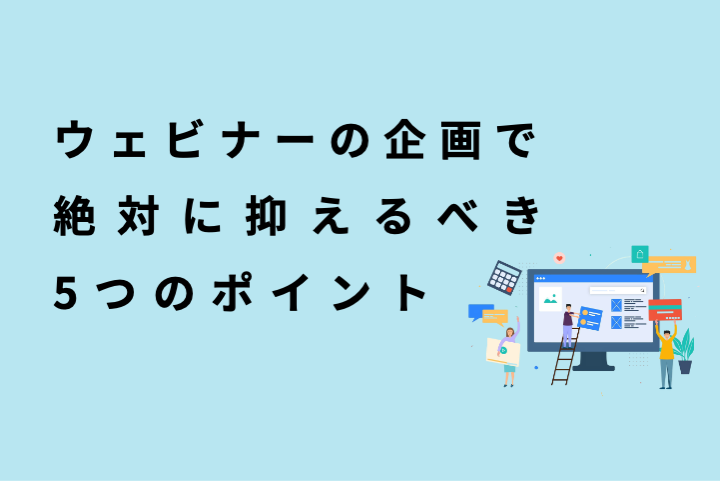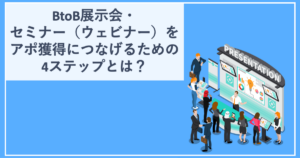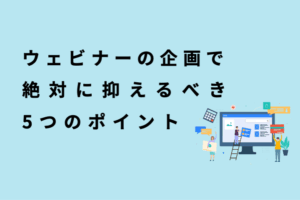BtoBマーケティングにおいて「ウェビナーマーケティング」は、リード獲得から商談化までを効率化できる有力な手法として定着しました。
オンライン上でセミナーを開催することで、従来のオフライン施策に比べてコストを抑えながら、より多くの見込み客と接点を持てるのが特徴です。
一方で、「企画の立て方がわからない」「集客が思うようにいかない」「開催後のフォローが続かない」といった課題を抱える企業も少なくありません。単にウェビナーを実施するだけでは成果につながらず、戦略的なマーケティング設計が欠かせません。
そこで本記事では、ウェビナーマーケティングの定義・目的・効果を整理しながら、成果を上げるための実践ステップや成功事例を紹介します。
ウェビナーマーケティングとは?
まずは、「ウェビナーマーケティング」という言葉の意味と、BtoBにおける位置づけを整理します。
ウェビナーマーケティングの定義
「ウェビナーマーケティング」とは、オンライン上で行うセミナー(ウェビナー)を活用して、リードを獲得・育成し、商談・受注につなげるマーケティング手法を指します。
ウェビナーは、リード獲得を目的としたTOFU(認知・興味喚起)フェーズから、既存リードの関係を深めるMOFU(ナーチャリング)フェーズまで幅広く活用できます。
低コストかつ高効率で実施できる上、参加者データやアンケート結果などを通じてリード情報を蓄積・分析しやすい点も大きな特長です。
BtoBにおけるウェビナーマーケティングの一般的な活用フロー
BtoBマーケティングでは、ウェビナーを単発イベントではなく「リード育成の起点」として位置づけるのが基本です。
多くの企業では、次のような流れでウェビナーを活用しています。
業界課題や最新トレンドをテーマにしたウェビナーを開催し、申込フォーム経由で新規リードを獲得します。興味関心に応じたテーマ設計が、後続の成果を左右します。
加者に対してウェビナー後のフォローメールで関連資料を案内し、理解を深めてもらいます。特にホワイトペーパーのようなダウンロード資料は、リードの温度感を把握する手段にもなります。
アンケートで得た回答データをもとに、ニーズの高い層へインサイドセールスがアプローチ。ウェビナーの満足度や課題感を把握することで、次回企画や営業戦略にも活用できます。
このように、ウェビナーは単なる“オンライン講演”ではなく、見込み客の関心を育てるための導線設計が重要な施策です。
また、録画アーカイブ配信やメールナーチャリングを組み合わせることで、長期的なリード育成にも展開できます。
ウェビナーを成功させるための設計ポイント
ウェビナーを単発イベントとして開催しても、成果につながらなければ継続は難しくなります。重要なのは、マーケティング全体の設計にウェビナーを組み込むことです。
企画段階から「誰に」「どんな価値を届けるのか」を明確にしておくことで、集客・配信・フォローのすべてを一貫した流れで設計できます。特に、下記のような観点で事前に整理しておくと効果的です。
- ターゲット:どの業種・職種を想定するか
- テーマ設定:ターゲットの課題をどの切り口で扱うか
- ゴール設計:ウェビナー後に何を行動してもらいたいか
これらを事前に定義することで、ウェビナーをリード獲得だけでなく、育成や商談化の起点として活用できます。
ウェビナーマーケティングの目的と効果
BtoBにおいて、ウェビナーは単なる情報発信の場ではありません。リード獲得から商談化まで、マーケティング全体の中で明確な目的を持たせることで、成果を最大化できます。
ウェビナーマーケティングの主な目的
ウェビナーを実施する目的は、自社のマーケティング課題や顧客フェーズによって異なります。
代表的な4つの目的を整理しておきましょう。
- 1.リード獲得(新規顧客へのアプローチ)
-
ウェビナーは、広告や展示会よりも低コストで新規リードを獲得できる手法です。特に、検索流入やSNSからの自然流入を組み合わせることで、興味度の高い見込み客を効率的に集められます。
- 2.ナーチャリング(既存リードの育成)
-
既存リードに対して定期的にウェビナーを案内することで、自社への関心を維持できます。MA(マーケティングオートメーション)ツールと連携すれば、参加データを基にスコアリング・再アプローチも可能です。
- 3.ブランド認知・信頼構築
-
専門家登壇や他社共催を通じて、企業の知見や業界内での立ち位置を強化できます。「情報を提供する立場」であることが、信頼醸成に直結します。
- 4.営業連携による商談化
-
ウェビナー後のアンケート結果や質疑応答内容を営業部門と共有し、ホットリードへのアプローチにつなげます。インサイドセールスとの連携により、“商談化率の高いリード”を効率的に抽出できます。
▼アポ獲得までの流れについては、こちらの記事もご一読ください。

ウェビナーがもたらす主な効果
ウェビナーの効果は、単なる参加数だけで測れるものではありません。定量・定性の両面で次のような成果が期待できます。
定量効果
- 新規リード数の増加(広告・展示会に比べコスト効率が高い)
- メール開封率・クリック率の改善(ウェビナー参加後のフォローで反応率が上昇)
- 商談化率・受注率の向上(ニーズ顕在化層を特定しやすい)
定性効果
- 自社の専門性・ブランド力の向上
- 顧客理解の深化(アンケート・質問内容から課題把握が可能)
- 部門との連携強化(営業・マーケティングのデータ共有が容易)
このように、ウェビナーマーケティングは単発の施策ではなく、リード獲得から商談化までを一貫して支える「BtoBマーケティングの中核施策」として機能します。
ウェビナーマーケティングの実践ステップ
ウェビナーの効果を最大化するには、「企画→集客→開催→フォロー」の全体設計を一貫して行うことが重要です。
以下の4ステップで、実践の流れを整理していきましょう。
STEP1 企画・テーマ設定
ウェビナーの成否を分けるのは、テーマ選定の精度です。自社が伝えたい内容ではなく、「顧客の課題」から逆算して企画することで、参加率と満足度が大きく変わります。
たとえば、単に「製品紹介」ではなく、「製品を使うことで解決できる課題」を軸にしたテーマ設定が効果的です。
(例:「現場DXを成功させる3つの視点」「成果が出るリードナーチャリング設計とは」)
▼ウェビナーのテーマ設計の考え方は、下記の記事で詳しく解説しています。
STEP2 集客・告知
どれだけ良い企画を立案したとしても、集客ができなければ成果にはつながりません。効果的な集客では、複数チャネルの組み合わせがカギとなります。
主な集客手法
- SNS広告(LinkedIn、Xなど)によるターゲティング配信
- メールマガジン・プレスリリースによる既存リードへの周知
- SEOコラムや自社ブログを通じた自然流入
特に、メルマガやSEO経由での申込は“情報収集段階の見込み客”を獲得できるため、ナーチャリングの起点になります。
▼実際のチャネル設計は、下記の記事で解説しています。
STEP3 開催・配信準備
開催当日にトラブルが起きると、印象が大きく損なわれてしまいます。機材・ツールの確認はもちろん、進行台本や登壇者の役割分担まで整理しておくことが欠かせません。
準備のポイントは次のとおりです。
- 配信環境(ネット速度・照明・音声)のチェック
- スライド・台本・リマインドメールの整備
- 司会・登壇者・サポートの役割分担
- チャット質問やアンケート投票など双方向性の設計
▼こうした事前準備の詳細や注意点は、以下の記事で実例を交えて紹介しています。


STEP4 開催後のフォロー
ウェビナーの成果は、「開催後のアクション」で決まります。資料ダウンロードやアンケート回答を起点に、参加者の関心度を測りながら次の接点を設計しましょう。
代表的なフォローフローは以下の通りです。
- 開催翌日に御礼メール+資料ダウンロード案内
- 数日後、アンケート回答者に個別フォロー(架電・メール)
- 興味度の高い層にホワイトペーパー・事例資料を配信
- 商談化につながったデータをMAで蓄積・分析
特に、ウェビナー内容と連動したホワイトペーパーの活用は、リード育成の要です。
ウェビナーとオフラインセミナーの違い
ここまでウェビナーについて解説してきましたが、時にはオフラインセミナーが有利な場面もあります。
そのため、目的やターゲットに応じて「どちらを選ぶか」または「どう組み合わせるか」を設計することが重要です。
ここでは、両者の特徴を比較しながら、それぞれの強みを整理します。
| 比較項目 | ウェビナー | オフラインセミナー |
|---|---|---|
| コスト | 会場や移動費が不要で、少人数でも気軽に開催できる。 | 会場費や交通費はかかるが、直接会える分、関係構築の効果が高い。 |
| リーチ | 全国・海外など、場所を問わず広く参加を募れる。 | 地域や業界を絞って、見込み度の高い層と深く接点を作れる。 |
| コミュニケーション | チャットやアンケートなど、ツールを使った交流が可能。 | 目の前で反応を見ながら会話でき、信頼関係を築きやすい。 |
| データ活用 | 申込・視聴データを自動取得し、後続施策に活かしやすい。 | 名刺交換や紙アンケート中心。データ化には手間がかかるが、直接的な関係を築ける。 |
| 継続・再利用のしやすさ | 録画アーカイブを再配信し、長期的なリード育成に活用可能。 | 当日の熱量を活かして商談化・提案につなげやすい。 |
目的に応じた使い分け方
ウェビナーは、情報発信やリード獲得を効率よく行いたい場合に最適です。
一方、オフラインセミナーは、信頼関係を深めたい、決裁者層と対話したいときに有効です。
BtoBマーケティングでは、両者を組み合わせた次のような使い分けが主流になっています。
- リード獲得フェーズ(TOFU):ウェビナーで多くの層へ認知拡大
- 商談・受注フェーズ(BOFU):オフラインセミナーで信頼構築と深掘りヒアリング
近年では、「ウェビナー × 展示会」や「オンライン説明会 × 対面商談会」など、オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド施策が成果を上げています。
デジタルの拡散力とリアルの信頼感をうまく組み合わせることで、リード獲得から商談化までの流れがスムーズになります
ウェビナーマーケティングでよくある質問
- ウェビナーの平均参加率はどれくらいですか?
-
BtoB向けウェビナーの平均参加率は、申込者の 30〜40%前後 が目安です。ただし、ターゲットとの親和性が高いテーマ(例:「最新トレンド」「失敗事例」「他社事例」など)では 50%以上 に達するケースもあります。
リマインドメールを複数回送る、開催前日に再通知を行うなど、参加を促す工夫も重要です。 - ウェビナーの最適な開催時間は?
-
BtoBでは、 30〜45分程度 が最も集中しやすい時間帯です。1時間を超えると離脱率が上がる傾向があるため、
・30分:テーマ特化型の知識提供
・45分:事例紹介+Q&Aを含む構成
といった形で内容を設計するのが効果的です。 - 平日と週末、どちらが効果的ですか?
-
BtoBでは、平日(火〜木)の午前10時〜午後4時が最も参加率が高い傾向にあります。特に昼休み時間帯(12時〜13時)を活用した「ランチタイムウェビナー」も人気が高く、営業・マーケティング職や決裁者層にリーチしやすい時間帯です。
週末開催はBtoC向け以外ではほとんど効果が見込めません。 - どんなテーマが参加率を高めますか?
-
「課題解決型」または「他社事例型」 のテーマが最も効果的です。
自社商材の直接的な宣伝ではなく、業界共通の悩みや成功事例に焦点を当てた内容にすることで、集客効率とエンゲージメントの両方を高められます。
(例:「営業DXを成功させる3つのポイント」「導入企業の事例から見るマーケ支援の成果」など) - ウェビナー後のフォローはどのくらい重要ですか?
-
ウェビナーの真価は開催後のフォローにあります。アンケートやダウンロード資料の行動データを基に、興味度の高いリードに対して1週間以内に架電またはメールフォローを行うことで、商談化率が大幅に向上します。
MAツールを使ってスコアリングを行い、関心度別にナーチャリングを設計するのが理想です。
ウェビナーマーケティングの企画立案・制作はリードレにお任せ!
本記事では、ウェビナーマーケティングの基本について詳しく解説してきました。文中で解説した通り、実際にウェビナー配信が無事完了したからと一息つくのはNGです。開催後のアプローチ設計こそが商談獲得、受注につなげる分岐点になるためです。
多くの企業の中では「当日使用したプレゼン資料」をそのままダウンロード資料として活用していますが、この手法には「ウェビナーに参加していない決裁者への訴求力が弱い」という課題もあります。
こうした課題を解消するためには、ウェビナーの内容をまとめ、説明や補足がなくとも完結するようなホワイトペーパーをダウンロード資料として設置することが有効です。
リードレはBtoB専門のコンテンツマーケティング会社としてこれまでに数多くの企業様のリード・ジェネレーションとリード・ナーチャリングをご支援してきました。
ウェビナーマーケティングの実践をお考えの方は、ぜひリードレまでお問い合わせください。