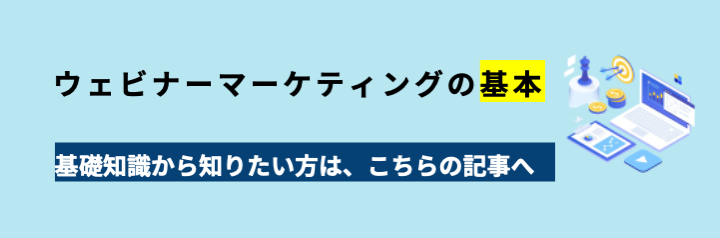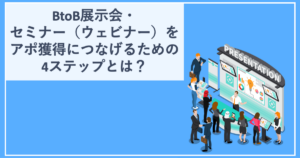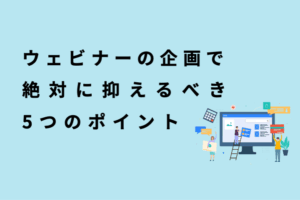ウェビナーは、今やBtoBマーケティングに欠かせない集客・リード獲得の手段です。
とはいえ、「何から準備すればいい?」「当日はどんな流れで進める?」といった疑問を持つ担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、初めての方でもスムーズに進められるよう、ウェビナー開催までの流れを8つのステップで解説します。
ウェビナーの開催方法を8ステップで解説
ウェビナーを初めて開催する方は、「どんな準備が必要?」「どの順番で進める?」と悩む方も多いでしょう。
本章では、企画から配信、フォローまでを8つのステップに分けてわかりやすく紹介します。
ステップ1:ツール(アプリ)を選ぶ
ウェビナーを開催する際は、Zoom・Google Meet・Microsoft Teamsなど、オンライン会議ツールを利用するのが一般的です。
近年では、これらのツールにも「ウェビナー専用モード」や「視聴者管理機能」が実装され、以前よりも簡単に本格的な配信を行えるようになりました。
ただし、目的によって最適なツールは異なります。集客規模や配信形式(ライブ/録画配信)、参加者の操作性を踏まえて選定することが重要です。
特に以下の機能をチェックしておくと、安定した運営につながります。
- 主催者以外の自動音声OFF・カメラOFF機能(ハウリングや雑音が防止されているか)
- 画面共有機能・動画再生機能(プレゼンやデモがスムーズに実施できるか)
- 録画・録音・文字起こし機能(アーカイブ配信や社内共有に活用できるか)
- チャット・QA機能(リアルタイムに質疑応答ができるか)
- 参加者の出欠・滞在時間レポート機能(マーケティングデータとして活用できるか)
ステップ2:機材を準備する
ウェビナー開催にあたっては、ツール(アプリ)だけではなく配信に必要な機材をそろえておくことが大切です。
現在は多くのパソコンにマイクやカメラが内蔵されていますが、安定した音質・映像品質を保つためには外付け機材の準備が推奨されます。
パソコン
ウェビナー当日に複数のアプリ(ウェビナーツール・スライド資料・メモなど)を同時に立ち上げても、動作が遅くならない程度のパソコンを用意しましょう。
特に映像の共有や録画を行う場合は、処理性能に余裕がある端末が安心です。社内で使用しているパソコンの動作が重い場合は、予備機や貸出用PCを利用するのも一案です。
ヘッドセット(または外付けマイク)
パソコンの内蔵マイクでも音声は拾えますが、距離や周囲の環境によって聞き取りにくくなることがあります。
そのため、ノイズキャンセリング機能付きのマイクや、マイク一体型のイヤホン・ヘッドセットを使用すると安心です。
最近では、AirPodsなどのBluetoothイヤホンも音質面で十分実用的です。
ウェブカメラ
パソコン内蔵カメラの画質が上がっているものの、角度調整や照明の影響を受けやすい点には注意が必要です。
特に、顔映りを明るく保ちたい場合は、外付けのウェブカメラ+リングライトを併用するのがおすすめです。配信環境を整えることで、オンライン上でも信頼感のある印象を与えられます。
ステップ3:ウェビナー配信に適した場所を確保する
ウェビナーの配信では、音声のクリアさと映像の安定性が参加者の印象を大きく左右します。
どれだけ内容が充実していても、雑音や途切れがあるだけで集中を妨げてしまうため、静かで通信環境の安定した場所を確保することが重要です。
オフィスから配信する場合は、会議室などの密閉された空間が適しています。空調やドアの開閉音なども意外と響くため、不要な機器の電源を切る・「配信中」サインを掲示するなど、周囲への配慮を行いましょう。
自宅から配信する場合は、生活音や通知音が入らないように事前に環境を整えます。呼び出し音やスマートフォンの通知をオフにするほか、外光の影響を避けるためにカーテンを閉め、照明で明るさを調整すると画面映えが良くなります。
さらに、最近では企業向けのウェビナースタジオや貸会議室の配信ブースを活用する企業も増えています。専用の照明・マイク・防音設備が整っており、初めてのウェビナーでも安心して運営できます。
重要な発表や多人数での登壇がある場合は、こうしたスタジオ利用も検討すると良いでしょう。
ステップ4:集客を行う
冒頭で述べたように、すでに多くの企業が積極的にウェビナーを開催しています。皆さんも、日々各社からウェビナー開催を告知するメルマガを受け取っているのではないでしょうか?
このような状況で自社のウェビナーに目標とする数の参加者を集めるには、十分な集客施策を実行することが重要です。
具体的には、下記のような施策です。
新規リード獲得を目的とする場合
新しい見込み客を獲得したい場合は、自社外からの流入チャネルを広げることが重要です。
- ウェブ広告を出稿する:Google広告やLinkedIn広告など、BtoB層にリーチできる媒体を選びます。
- プレスリリースを配信する:業界メディアやニュースポータルに配信し、企業・担当者の認知を広げます。
- ウェビナーポータルサイトで告知する:イベント情報サイトに登録して、関心層の自然流入を獲得します。
- SNSで告知する:X(旧Twitter)やLinkedInなど、業界担当者が情報収集に使うSNSで定期的に発信します。
既存リードの育成を目的とする場合
すでに接点のあるリードを商談化につなげたい場合は、関係性を深める発信が効果的です。
- メルマガを配信する:過去のダウンロード・イベント参加者に対してウェビナー案内を配信します。
- MAツールの活用:属性や行動データをもとに配信内容を最適化します。
- インサイドセールスを行う:既存顧客やリードへ個別に連絡し、参加を促します。
また、これらの集客施策を行ううえでは、下記のポイントを押さえておく必要があります。
- ポイント1:PDCAを回して最適な集客施策を見極める
-
配信媒体ごとに申込率・参加率を比較し、費用対効果の高い施策へ集中します。
- ポイント2:共催ウェビナーで新しい層にリーチする
-
業界が近い企業と共催することで、相互にリードを拡大できます
- ポイント3:申込を後押しする仕掛けをつくる
-
「参加特典」や「参加者限定資料」などを設け、申込ハードルを下げましょう。
- ポイント4:アーカイブ配信を活用する
-
ライブ配信だけでなく、録画データを後日配信することで、予定が合わなかった層にもリーチできます。
ステップ5:申込者に案内メールを送る
ウェビナー申込者には、開催情報を正確かつタイムリーに伝えることが欠かせません。
特にビジネスシーンでは、予定のダブルブッキングやリマインド漏れが参加率低下の原因になるため、案内メールの設計は集客の延長線上にある重要なプロセスです。
案内メールには、下記のような情報を欠かさず入れましょう。
- ウェビナーのテーマ・開催日時
- 開催URL(Zoom、Meet、Teamsなど)
- 当日の参加方法や推奨環境
- 質問投稿・チャット利用のルール
- 緊急連絡先(技術トラブルなどへの対応)
その上で、申込から開催当日まで、以下のように3段階リマインドを設定しておくのが効果的です。
- 申込直後:申込完了メール(自動返信)→参加URL・日時を明記し、カレンダー登録リンクを添付。
- 前日リマインド:開催前日の午前中→見出し例:「明日の〇〇ウェビナーのご案内」
- 当日リマインド:開始2〜3時間前→「まもなく開始します」として再通知。
MAツール(SATORI、HubSpot、b→dashなど)を使えば、これらを自動化することも可能です。
ステップ6:資料を作成する
ウェビナーでは、参加者がスライドを見ながら理解を深める構成が基本です。
ただし、オフラインのセミナー資料をそのまま使うと、オンラインでは「文字が小さく読みにくい」「テンポが遅く感じる」などの問題が発生します。
ここでは、ウェビナー用資料を作成する際のポイントを整理します。
ポイント1:画面サイズと文字設計
横長(16:9)のスライド比率に統一し、1枚あたりの文字量は100〜120文字以内を目安としましょう。
その上で、 図表やキーワードを多用して、視覚的に理解できる構成にすると参加者が理解しやすいです。
ポイント2:アニメーションは最小限に
複雑な動きは通信環境によって遅延・乱れの原因になります。必要な強調部分のみ「フェード」など軽い動きにとどめましょう。
ポイント3:スライド枚数は多めに
オンラインでは視聴者の集中が途切れやすいため、テンポよく進む構成が理想です。1枚を長く見せるよりも、1テーマ=1スライドで区切ると理解度が上がります。
ポイント4:3種類の資料を用意する
目的ごとに資料を分けることで、再利用性が高まります。
| 登壇者用スライド | 登壇者の説明用 | 図やキーワード中心、文字少なめ |
| 配布用スライド | 参加者の振り返り用 | 注釈・補足を追記 |
| DL資料(ホワイトペーパー化) | 不参加者・意思決定者への共有用 | 完結した文章+CTA |
ステップ7:当日もしくは前日にテストを行う
ウェビナーでは、ウェビナーツールはもちろん、パソコン、ネットワーク回線、ヘッドセットなど様々な機器を使用して開催します。そのため、これらの機器に不具合がなく、かつ設定・操作をスムーズに行えるようにしっかりと準備しておくことが重要です。
当日もしくは前日に、本番と同じ環境でテストを行いましょう。その際にチェックすべき項目は、下記の通りです。
技術面チェック
- 主催者・登壇者・参加者それぞれのアカウントで入室できること
- マイク・スピーカー・カメラが動作すること(雑音・ハウリングがないか)
- 資料共有(PowerPoint・PDFなど)が正しく表示されること
- 録画・チャット・Q&Aなどの機能が正常に動くこと
- 通信が不安定な場合の代替策(スマホテザリングや予備Wi-Fiなど)を準備すること
② 体験面チェック
- 画面共有時に文字が小さすぎないか
- スピーカーの声がこもっていないか
- 開始・終了時の案内スライドが自然に切り替わるか
- 「入室から開始までの静寂時間」が発生しないようBGMまたはオープニング画面を設定
ZoomやMeetなどの主要ツールには「リハーサル機能」や「待機室機能」が実装されています。これらを活用すれば、参加者に見せずに事前調整が可能です。
ステップ8:参加者にメールで資料を配信する
ウェビナー開催の目的は、単に申込者を集めることではありません。
ウェビナーを通じて獲得したリードを継続的にナーチャリング(育成)していくことで、アポ獲得や受注につなげることが目的です。
そのため、ウェビナー開催後のフォローを徹底しましょう。
具体的には、ウェビナー参加への御礼の言葉を添えてウェビナーで使用した資料をメールで配信します。
それに合わせて架電をすることで、ウェビナーの感想をヒアリングしつつアポ獲得を狙うのが効果的です。
ウェビナーの開催方法でよくある質問
- ウェビナー開催までにどのくらいの準備期間が必要ですか?
-
1カ月前を目安に計画しましょう。ツール選定や資料作成、告知期間を含めると、最低3〜4週間前の準備が理想です。
- 少人数のウェビナーでも効果はありますか?
-
あります。特にBtoBでは「質の高いリード」を獲得できるケースが多く、10〜20名規模でも商談につながることがあります。
- ウェビナー後のフォローは何をすればいいですか?
-
参加者に資料送付とヒアリングを行いましょう。メール配信+架電の組み合わせで、アポ率を高めることができます。
ウェビナー開催後のリード獲得はリードレにお任せください!
今回は、ウェビナーの開催方法を8つのステップにわけて解説してきました。
前述の通りウェビナー実施後は参加者へのアプローチを継続してアポ獲得、受注につなげていく必要があります。その際、特に重要なコンテンツがホワイトペーパーです。
例えば、ウェビナー開催後のアポ獲得の取り組みのひとつとして、メールで資料ダウンロードを促す方法があります。一方で、セミナー(ウェビナー)を開催している企業の中には「当日使用したプレゼン資料」をそのままダウンロード資料として活用しているケースが少なくありません。
プレゼン資料は、説明する内容を視覚的に補足するために作られていることがほとんどです。そのため、参加した担当者が後から内容を振り返ることはできても、参加していなかった方がプレゼン資料から当日の内容を十分に理解することは難しいでしょう。
このことから、決裁者がセミナー(ウェビナー)に不参加の場合、プレゼン資料によって自社の特長やメリットをアピールする機会を失っている可能性があります。こうした課題を解消するためには、ウェビナーの内容をまとめ、説明や補足がなくとも完結するようなホワイトペーパーをダウンロード資料として設置することが有効です。
リードレは、BtoB専門のコンテンツマーケティング会社として、このようなホワイトペーパーの制作をはじめ、これまでに数多くの企業様のリードジェネレーションとリードナーチャリングをご支援してきました。
リードジェネレーション・リードナーチャリングの取り組みを検討している方は、ぜひリードレまでお問い合わせください。