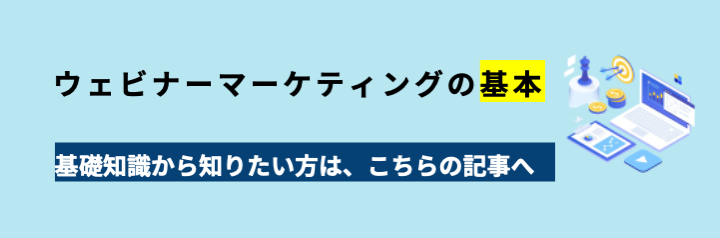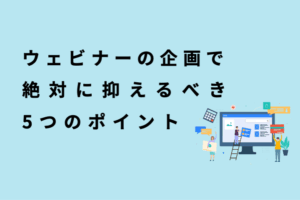展示会・セミナー・ウェビナーを開催しても、「名刺交換や参加者リストの整理で終わってしまう」という声は少なくありません。
しかし、イベントはリード獲得の“起点”ではなく、“商談化の入り口”として設計することで、成果は大きく変わります。
本記事では、BtoB企業が展示会やウェビナーをアポ獲得につなげるための4ステップを、MA活用・ナーチャリング戦略とあわせて解説します。
STEP1:イベントの目的を「商談化」から逆算して設計する
展示会やウェビナーの開催は、単なる「集客イベント」ではなく、商談獲得につなげるための重要なマーケティング施策です。
最初に決めるべきは、集客数ではなく「誰に」「どんな行動を取ってほしいのか」です。この目的設計を誤ると、どれだけ多くの参加者を集めても成果には結びつきません。
商談化からを起点にKPIを逆算して設計する
イベントを成果につなげるためには、まず商談化率や受注金額などのKGI(最終指標)を設定し、そこから申込数・来場率・アポ率といったKPIを逆算して設計します。
多くの企業では「展示会で名刺を集める」「ウェビナーで申込者を増やす」といった表面的なKPIだけで判断しがちです。しかし、イベントの真の目的はリードを商談化・受注へつなげることです。
「どんな顧客層から何件の商談を創出するか」を基準に設計することで、初めてマーケティング全体と連動した成果が見えてきます。
目的に応じて最適なイベント形式を選ぶ
次に、設計したKPIをもとに目的別の形式選定を行いましょう。
たとえば、
• 認知拡大が目的なら「ウェビナー」で広くリーチ
• 深耕・商談化が目的なら「展示会」や「個別相談会」で密度の高い接点を設計
といったように、目的と形式をセットで考えることが重要です。
この段階で営業チームと連携して、“どのリードをどの段階で営業に渡すか”の条件をすり合わせておくと、後のフォローがスムーズになります。
STEP2:来場・参加データを活用して“温度感”を可視化する
イベント後に「名刺をリスト化して営業に渡すだけ」では、商談化の精度は上がりません。
ウェビナーや展示会の参加データを分析し、リードの関心度=“温度感”をスコアリングすることで、営業が本当に優先すべき相手を見極められるようになります。
たとえば次のようなデータを取得・分類しておくと、営業判断の精度が上がります。
- 来場・視聴回数(繰り返し参加しているか)
- 滞在時間・動画視聴率(どこまで見たか)
- 資料ダウンロード履歴
- アンケート回答内容(課題・検討時期など)
これらの情報を統合的に見ることで、「ただの参加者」から「今すぐ検討層」までを明確に分けられます。
MAツールで行動ログをスコアリングする
MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用すると、参加・閲覧・クリックといった行動ログを自動で数値化(スコアリング)できます。
たとえば、
• ウェビナー視聴完了 → +30pt
• 資料DL → +20pt
• アンケートで「導入を検討している」と回答 → +40pt
といった形でスコアを設定し、リードを「A:即アプローチ」「B:ナーチャリング」「C:情報提供のみ」に分類します。
このような仕組みを整えておくと、営業は温度の高いリードから優先的にフォローできるようになります。
オンラインとオフラインのデータを統合する
展示会とウェビナーを並行して運営する企業も増えていますが、両方のデータが分断されたままだと、見込み度の高いリードを取りこぼす恐れがあります。
そこで有効なのが、オンラインとオフラインの統合管理です。ウェビナー視聴データと展示会の名刺情報を紐づけることで、
「どのセミナーに参加した人が、どの展示ブースを訪れたか」を可視化できます。
データを統合すると、次のような“自動連携シナリオ”を設計できます。
• メール開封・動画視聴・資料DLをトリガーに、自動で営業通知を送信
• 展示会来場者のうち、ウェビナー視聴済みの層に個別フォローを自動配信
このようにアナログ管理から脱却することで、マーケティングと営業の連携がデータドリブンに進化します。
STEP3:ナーチャリング設計で「次の行動」を促す
BtoBマーケティングでは、展示会やウェビナー直後に“即商談化”するケースは多くありません。
重要なのは、参加直後の関心が高いタイミングで適切なフォローを行い、段階的に関係を深める仕組み(ナーチャリング)を整えることです。
ここでは、成果を上げるためのナーチャリングシナリオの設計ポイントを紹介します。
参加直後は最も関心が高まっているタイミングです。
まずは翌日中に御礼メールを送信し、当日の資料ダウンロードリンクを添付します。
本文のポイント:
• 件名は「ご参加ありがとうございました」で簡潔に
• 本文では「復習用」として資料を提供(営業色を抑える)
• メール開封率を高めるため、件名・送信時間をテスト運用
この段階では“販売”ではなく、“信頼関係の維持”を目的に据えることが重要です。
初回の御礼メールで反応があったリードには、3日以内に関連資料を案内します。
当日のテーマをより深く掘り下げたホワイトペーパーを紹介することで、参加者の関心を「理解・共感」フェーズに進められます。
たとえば、「ウェビナーの成果を上げる方法」というテーマなら、「ウェビナー後の商談化設計」や「効果測定チェックリスト」など、次の行動を促す内容が効果的です。
アンケートに「導入検討中」「課題を感じている」と回答した層には、1週間以内に個別フォローを行います。この層は“ホットリード”に近いため、メールまたは架電で具体的な課題ヒアリングを実施しましょう。
ポイント:
• 営業が対応する前にMA上でステータスを「A:商談候補」とタグ付け
• 回答内容を踏まえたパーソナライズ対応(例:「DXに課題を感じている」と回答した層には導入事例を送付)
一定期間が経過しても商談化していないリードには、定期的なナーチャリング配信を行います。
成功事例・ノウハウ・業界トレンドなど、“学び”を重視したコンテンツで、長期的な接点を維持しましょう。
MAシナリオ例:
• 「課題別ホワイトペーパー3連配信」
• 「セミナー動画アーカイブシリーズ」
• 「導入事例+無料相談案内」
定期的に「資料DL」「動画視聴」「クリック」などの反応を確認し、温度感の変化を再スコアリングします。
ウェビナーで使用したスライドや動画を再編集してホワイトペーパー化すれば、ナーチャリング用コンテンツとして再利用できます。一度の開催で複数のチャネルに活用できるよう設計することで、コンテンツ制作コストを抑えつつ成果を最大化できます。
SETP4:商談獲得につなげる営業連携・フィードバック
展示会やウェビナー開催の最終ステップを担うのが、営業部門との連携設計です。
マーケティングが生成したリード情報を、定量データと定性情報の両面から営業に共有することで、商談化率を大きく高めることができます。
MAスコアを基に「優先度別リード引き渡し」を行う
マーケティングオートメーション(MA)ツールのスコアリング結果を活用し、リードを「A:即時アプローチ」「B:フォロー対象」「C:長期育成」といった優先度で分類します。
これにより、営業は“温度の高いリード”に集中でき、リソースの無駄を防げます。
また、リードの行動履歴(視聴時間・資料DL・アンケート回答など)を併せて共有しておくと、初回接触時のトーク内容もより具体的になります。
インサイドセールスが初回接点を担当する
営業へのパスを効率化するには、インサイドセールス(内勤営業)の存在が重要です。MAスコア上位のリードに対して、インサイドセールスが架電・メールで初回接点を取得し、興味度合いや課題感をヒアリングします。
特にBtoBでは、営業がすべてのリードにアプローチするのは非効率です。
初期接点の段階で、見込み度を分類しておくことで、フィールドセールス(外勤営業)は“商談化可能性の高いリード”だけに集中できます。
フィードバックループで「マーケ施策」を改善する
商談が成立したかどうかだけでなく、失注理由や商談時の反応もマーケ側にフィードバックする仕組みが必要です。
「どのテーマのウェビナー参加者が商談につながりやすかったか」
「アンケートのどんな回答内容が受注率に影響しているか」
こうした情報を定期的に共有することで、次回の企画テーマやフォロー施策を改善できます。
営業が「資料DL者に全件架電する」状態では、成果は頭打ちになります。MAスコアや行動履歴をもとに、“温度感ベース”の優先アプローチへ移行することが、展示会・ウェビナーのROIを最大化するカギです。
BtoB展示会・セミナー(ウェビナー)のアポ獲得でよくある質問
- 展示会やウェビナーからの商談化率はどのくらいですか?
-
BtoBの場合、一般的な商談化率は5〜10%前後が目安です。ただし、業種・テーマ・リードの成熟度によって大きく変動します。
たとえば、既存リード向けウェビナーや小規模展示会では15〜20%に達するケースもあります。重要なのは、「名刺や申込数」ではなく、どれだけのリードが次の接点(資料DL・相談)に進んだかをKPIとして設計することです。
- MAツールを導入していない場合でも、リード管理は可能ですか?
-
はい、可能です。MAツールがない場合でも、Excelやスプレッドシートで最低限の行動データを管理できます。
たとえば次のような指標を記録しておくと効果的です。
• イベント種別(展示会/ウェビナー)
• 参加日・テーマ
• 資料ダウンロード有無
• アンケート回答内容
• フォロー状況(未架電/架電済み/商談中)将来的にMAを導入する際も、このデータ構造を整えておくことでスムーズに連携できます。
- ナーチャリングと営業フォローの違いは何ですか?
-
ナーチャリングは「リードを温める段階」、営業フォローは「商談へ動かす段階」を指します。
具体的には次のように役割が異なります。ナーチャリング 営業フォロー 目的 関心・理解を深める 商談・受注に繋げる 手段 メルマガ、ホワイトペーパーなど 架電、個別メール、商材設定 担当 マーケティング部門 営業・インサイドセールス この2つを連携させることで、リードの温度感に応じた最適な接点設計ができます。
- 小規模なウェビナーでも商談化は見込めますか?
-
十分に見込めます。むしろ「少人数×高関心層」に絞ることで、1件あたりの商談率が高まるケースもあります。
たとえば、月1回30分のテーマ特化型ウェビナーを開催し、参加者に限定ホワイトペーパーを案内するだけでも、継続的なリード育成施策になります。
重要なのは規模ではなく、“ターゲットの課題に即した内容設計”です。内容とフォローの一貫性があれば、小規模でも確実に成果を積み上げられます。
BtoBの展示会・セミナー(ウェビナー)後のアプローチにはホワイトペーパーが必須!
ここまで、BtoB企業が展示会やセミナー(ウェビナー)を通じて獲得したリードをアポ獲得につなげるために取り組むべきことについて解説してきました。
記事内でも触れた通り、ウェビナーは「開催して終わり」ではなく、開催後のアプローチ設計こそが商談獲得、受注につなげる分岐点になります。
多くの企業の中では「当日使用したプレゼン資料」をそのままダウンロード資料として活用していますが、この手法には「ウェビナーに参加していない決裁者への訴求力が弱い」という課題もあります。
こうした課題を解消するためには、ウェビナーの内容をまとめ、説明や補足がなくとも完結するようなホワイトペーパーをダウンロード資料として設置することが有効です。
リードレはBtoB専門のコンテンツマーケティング会社としてこれまでに数多くの企業様のリード・ジェネレーションとリード・ナーチャリングをご支援してきました。
ウェビナーマーケティングの実践をお考えの方は、ぜひリードレまでお問い合わせください。