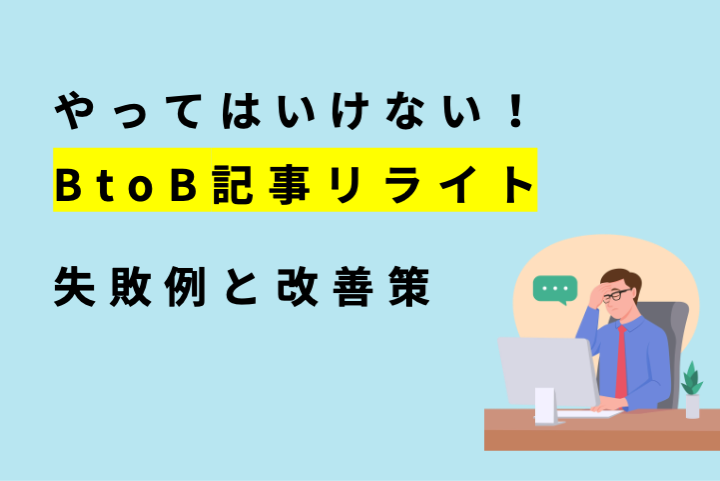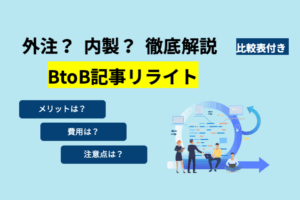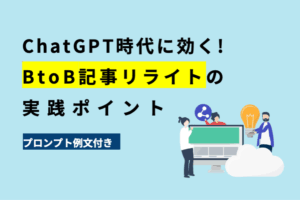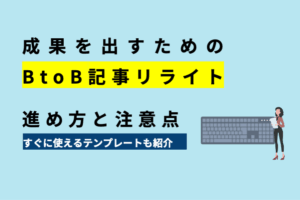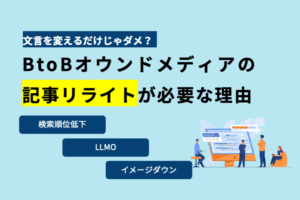「せっかく記事をリライトしたのに、検索順位もCVも改善しない」
このような課題をお持ちではありませんか?
BtoBオウンドメディアにおけるリライトは、単なる「文章の書き換え」ではなく、構成や意図の“再設計”が求められる高度な編集作業です。にもかかわらず、見出しだけ変えたり、文字数を増やしただけの表面的な対応で済ませてしまうケースが後を絶ちません。
本記事では、よくある失敗例(NGリライト)を実例つきで紹介しながら、なぜ成果につながらないのか/どうすれば防げるのかをFAQ形式でわかりやすく解説します。
▼記事リライトの基本的な考え方を知りたい方は、下記の記事をまずお読みください。
BtoB記事のリライト、なぜ「失敗する」ことがあるのか?
「とりあえず加筆して文字数を増やした」「文体を整えて読みやすくした」
それだけでリライトが完了したと考えていませんか?
そもそもリライトとは、ただの“書き換え”ではなく、コンテンツ全体の再設計に近い作業です。表面的な表現変更だけでは、検索順位もコンバージョンも改善されにくいのが実情です。
特にBtoBの記事は、読み手の課題や検討ステージに沿った構成と情報設計が求められます。既存の記事の構成を踏襲したままの修正では、読者の興味を引けず、SEOの効果も期待できません。
さらに現在のSEOやLLMO(AI検索)では、情報の網羅性・論理の明快さ・見出し構造などが評価対象となります。こうした観点が欠けていると、検索順位が下がるだけでなく、AIにも拾われづらくなってしまいます。
“なぜリライトするのか”“誰に読んでもらいたいのか”といった本質的な問いに立ち返り、構造・意図・文脈を再設計することが重要です。
BtoB記事のリライト、失敗を防ぐためのQ&A集
コンテンツ制作の現場では、「リライトしたのに順位が落ちた」「どこまで直せばいいのか分からない」といった悩みも少なくありません。
そこでこのセクションでは、リライト時によくある疑問とその対処法をFAQ形式で解説します。失敗を避けるための実践的なヒントとして、ぜひお役立てください。
- とりあえず文字数を増やすのはNG?
-
不要な水増しは逆効果です。
「文字数を増やせばSEOに強くなる」といった認識は過去のものです。むしろ、本質的でない加筆は読者の理解を妨げ、AI検索(LLMO)からも評価されづらくなります。
Googleの「Helpful Content Update(有益なコンテンツに関するアップデート)」では、「ユーザーのニーズを満たしていない、単に検索順位を意識したコンテンツ」はランキングを下げる可能性があると明言されています。
参考:Google検索セントラル「2022 年 8 月の Google の有用なコンテンツの更新についてクリエイターが知っておくべきこと」
つまり、本質的でない“水増し”はコンテンツ全体の品質スコアを下げる要因となり得ます。<改善策>
1つの見出しにつき、読者の具体的な疑問を想定し、それに対して明確に答える構成に見直しましょう。「Q→A→根拠→具体例」の順で情報を整理すると、検索エンジンにもAIにも理解されやすくなります。
無理にボリュームを増やすのではなく、「要点を明確にする」方向でリライトするのが効果的です。 - 古い表現を“書き換えるだけ”では不十分?
-
表面だけの修正では検索順位もCVも改善しにくい
言い回しを少し変えただけでは、検索エンジンにも読者にも「新しい情報」とは認識されません。リライトの目的は、単なる文体変更ではなく、検索意図に対する適切な回答と導線設計を整えることです。
<改善策>
リライトでは、構成の再設計、ターゲットペルソナの再設定、そしてCV導線の見直しまで一貫して行うことが重要です。
・「誰に・何を・どう伝えるか」をゼロベースで見直す意識が、成果につながるリライトの第一歩となります。 - 外注ライターに丸投げするとどうなる?
-
読者や自社ビジネスの文脈を伝えられない場合、自社の強みが薄れるおそれがある
BtoB領域では、業界特有の課題や専門用語、顧客の意思決定プロセスへの理解が不可欠です。こうした背景を共有しないままライターに丸投げすると、検索意図からズレた記事や、信頼感に欠ける文章が仕上がることも少なくありません。
<改善策>
まずは「誰に」「何を伝えるのか」を明確にした要件定義が重要です。
そのうえで、編集者がライターとの橋渡しとなり、構成チェック・文脈補強・一次情報の挿入などを行うことで、BtoB記事としての精度と成果が大きく変わります。 - 旧記事の内容を活かしてリライトすべき?
-
古い内容を無理に活かすと、構成が破綻する
リライト時に「せっかく書いたから」と過去の内容を無理に残そうとすると、現在の検索意図や読者ニーズに沿わない情報が混在し、文脈が崩れるリスクがあります。
特に、時代背景が変わったテーマや制度改定が絡む内容では注意が必要です。
読者にとって価値のある情報かどうかを軸に判断し、思い切った差し替えや他記事との統合も視野に入れましょう。
過去の内容を活かすにしても、現在の検索意図に整合する形で再構成することが前提です。 - LLMO文脈での“やりがちNG”とは?
-
「答えがどこにあるか分からない記事」は拾われにくい
ChatGPTやAI OverviewsなどのLLMO(大規模言語モデル最適化)では、構造と文脈の明確さが重視されます。
人間が「なんとなく理解できる」文章でも、AIには「要点が曖昧」「回答が不明瞭」と判断され、検索結果やAI回答で参照されにくくなるケースがあります。読者の疑問を明確にQとして提示し、それに対してAで回答し、根拠を添えるという「Q→A→根拠」の構成を意識しましょう。
特にAIが要点を拾いやすい文章構造にすることが、今後のSEO・LLMOにおいて鍵となります。
【リードレ支援事例】適切な記事リライトで検索順位・CV率が改善
BtoB記事のリライトは、適切な手順と構成を踏めば、コンバージョン(CV)や検索評価を大きく改善できます。
以下は、実際にリードレが支援したリライト事例です。
- Before:構成が煩雑で読みづらく、成果につながらない状態
- 施策
- After:構成・文脈の再設計によりCV率1.5倍に
この事例からも明らかなように、記事リライトでは、単なる加筆修正ではなく、構成や導線を含めた“再設計”が重要です。
特にBtoB領域では、「誰に・何を・どう伝えるか」がより明確に伝わる構造でなければ、読者もAIも正しく評価してくれません。
記事リライトの失敗を避け、成果につなげるためには?
BtoB記事のリライトで成果を出すには、単なる加筆や言い換えではなく、記事全体の意図と構成を再設計する視点が欠かせません。
とくに専門性の高い領域では、表現力だけでなく「誰に・何を・どう伝えるか」を編集的な視点で整理し直す必要があります。
リライトは、構成力と編集力がもっとも活きる作業です。
「とりあえず修正」ではなく、「なぜ今この内容を、誰に届けるのか」を明確に設計することで、CVや検索評価に直結する記事へと生まれ変わります。
このような構成設計・一次情報のヒアリング・導線最適化までを一貫して支援するのが、リードレの強みです。リライトを通じてBtoB記事の価値を高めたいとお考えであれば、ぜひご相談ください。

まずは自分で既存の記事をチェックしてみたいという方は、下記より無料の「LLMOチェックリスト」をダウンロードいただき、ご活用ください。