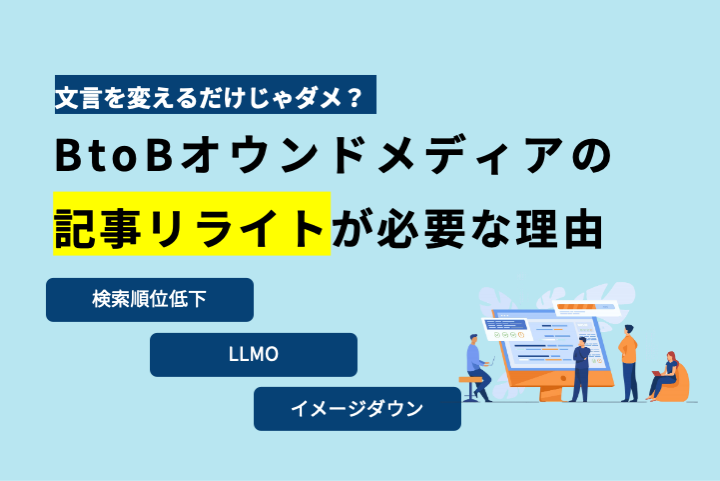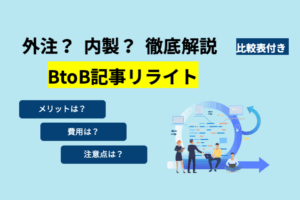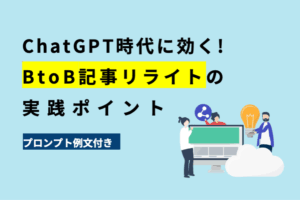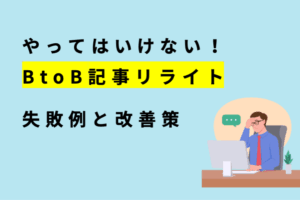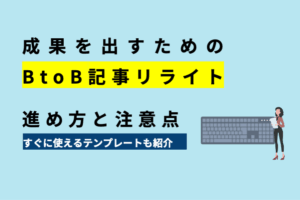BtoB企業におけるオウンドメディア運用では、過去に公開した記事をそのまま放置していませんか?
かつては検索上位にあった記事でも、情報の陳腐化や検索アルゴリズムの進化により、順位が大きく下落しているケースが少なくありません。
特に、ChatGPTなどの生成AIが普及するいま、単なる加筆・修正では成果につながらない「リライトの限界」が顕在化しています。
本記事では、BtoB記事のリライトが求められる背景や、LLMO(Large Language Model Optimization)時代に有効なリライトの視点・手順をわかりやすく解説。SEO対策だけでなく、AIにも“拾われる”構成・編集の実践ポイントまで網羅的に紹介します。
BtoB記事における「リライト」とは?
BtoB領域における「記事のリライト」とは、単なる文章の書き換えや表現の修正を意味するものではありません。読者の検索意図や市場の変化、そして技術の進化をふまえた“再設計”に近い作業です。
従来の記事リライトでは、事実や用語、更新日のアップデートのみが行われるケースが多く見受けられました。実際に、それだけでも検索順位を維持・向上できた時期もありました。
しかし、SEOだけでなく、LLMO(大規模言語モデル最適化)が台頭した今日では、AIに伝わる明確な構造設計が不可欠で、記事によっては構成・文脈はもちろん、訴求軸そのものを見直す必要が生じています。
LLMOについて、基本を押さえたい方は、下記の記事もご一読ください。
今、BtoB記事のリライトが求められている3つの理由
「かつて検索上位を獲得していたBtoB記事が、近年は目に見えて成果を出しにくくなっている」
「用語などをアップデートしても、検索順位が戻ってこない」
このような課題を持つWeb担当者は多いのではないでしょうか。実際に今、記事のリライトが重要視されている背景には、次の3つの理由があります。
① 検索順位の低下(SEOアルゴリズムの変化)
Googleをはじめとする検索エンジンのアルゴリズムは、年々進化しています。かつて評価されていた構成やキーワードの詰め込みは、今では逆効果になることも少なくありません。
とくに、更新が途絶えた記事は「陳腐化」や「放置されたコンテンツ」とみなされやすく、検索順位が大きく下落する原因となります。
②LLMO(AI検索)への最適化が必要に
AI Overviews(Google検索における生成AI機能)やChatGPTなど、生成AIによる検索体験の広がりにより、AIが理解・引用しやすい構造や文脈が求められるようになりました。
従来のSEOでは通用していた記事も、「質問→回答→根拠」のような明快な構成がないと、AI検索に“無視”される可能性があります。
③古い記事がサイト全体の品質スコアを下げる
検索エンジンは個別記事の評価だけでなく、サイト全体の品質スコア(E-E-A-Tなど)を重視しています。内容の古い記事、読者ニーズから乖離した記事を放置しておくと、ドメイン全体の評価が下がり、他の記事の順位にも悪影響を及ぼすことがあります。
オウンドメディアの放置がもたらす3つのリスク
BtoBオウンドメディアの記事を放置していると、表面上は「悪くない状態」に見えても、裏側では大きなリスクが進行していることがあります。特に以下の3点は、成果を大きく損なう原因となりやすいため注意が必要です。
①検索順位が下がる=流入が減る
GoogleのアルゴリズムやAI Overviewsの進化により、情報の鮮度や構造の明快さが重視されるようになっています。
更新のない記事は「古い情報」と見なされやすく、以前は上位にあった記事が圏外に落ちているケースも珍しくありません。結果として、自然検索からの流入が激減し、記事の存在意義が失われていきます。
②問い合わせやCVのチャンスを逃す
流入が減るということは、見込み顧客との接点が減ってしまうこととイコールです。また、せっかく時間やコストをかけて制作した記事だったとしても、現状と合わない情報や古いCTAのままでは、コンバージョンにはつながりません。
③古い内容がブランド毀損につながる
特にBtoB領域では、専門性・信頼性が重視されます。
にもかかわらず、記事内に古いサービス情報や誤解を招く表現が残っていた場合、読者に「この会社は最新の業界事情に明るくないのではないか?」という印象を与えかねません。
そうしたイメージはオウンドメディア全体の信頼性にも影響し、ブランド毀損リスクにつながります。
成果につながる記事リライトのポイントとは?
BtoB記事のリライトは、単なる加筆・修正では成果につながりません。検索エンジンとAIが進化した今、以下の4つの観点から“構造そのもの”を見直すことが重要です。
ポイント1 構成の見直し
今日では、Web記事の読者は、検索やAIアシスタントを通じて「疑問→回答」を高速に解決したいと考えています。そのため、記事構成は「Q(読者の疑問)→A(結論)→根拠(理由・事例)」の順に整理するのが効果的です。
たとえば、「〇〇ツールの選び方で迷っていませんか?」という問いから始め、最適な選び方を示し、その理由や実例を続けて示すことで、読者にもAIにも伝わりやすい構成になります。
ポイント2 一次情報(事例・開発背景など)の追加
AIによる要約コンテンツが溢れる中で、一次情報の価値は急上昇しています。
自社の成功事例、現場の声、開発背景、インタビューといった独自の視点は、コンテンツの信頼性と差別化を高めるだけでなく、検索エンジンからの評価にも貢献します。
ポイント3 CTAの強化
リライトの目的が“検索順位回復”だけになってしまうと、本来のゴールである「問い合わせ」や「資料ダウンロード」につながりません。
読了後に読者が自然とアクションを起こせるように、CTA(行動喚起)も見直すことが重要です。単なるボタン設置ではなく、読者の心理に沿ったタイミングと訴求が鍵を握ります。
ポイント4 LLMO最適化
ChatGPTやGoogleのAI Overviewsなど、生成AIによる情報提供が一般化するなか、AIが正しく文脈を理解できる構成が求められます。
具体的には、セクションごとに主張→根拠→まとめを明確にし、質問形式の見出しやFAQ的な文章構造を意識することで、AIに“拾われる”可能性が高まります。
LLMO時代の記事制作のポイントについては、下記の記事で詳しく解説しています。
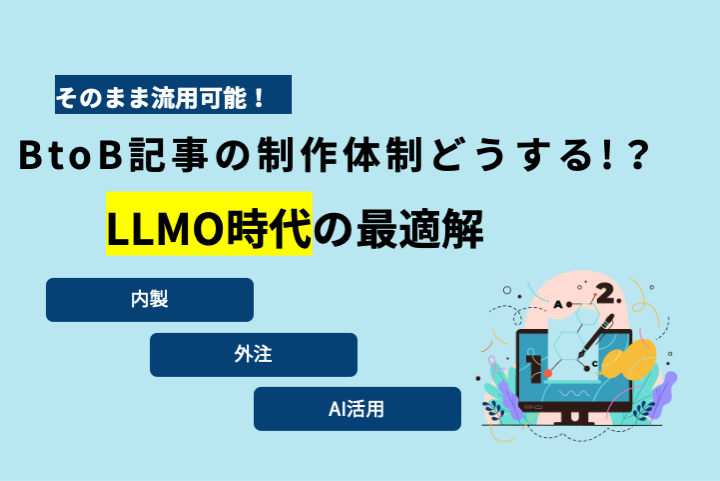
リードレの記事リライト支援事例
BtoBオウンドメディアにおける記事リライトの成果を示す事例として、リードレが支援したSaaS企業のケースをご紹介します。
- Before:ライター外注記事が検索圏外に
-
対象となった記事は、かつて専門ライターに完全外注して制作されたもので、一時は「○○+課題」などの検索ワードで上位表示を獲得していました。
- 施策
- After:構成・文脈の再設計によりCV率が2.5倍に
この事例は、単なる文章表現の修正ではなく、記事の再構成と情報設計がいかに成果に直結するかを示す好例です。
BtoB商材の場合、専門性が高く、伝えるべき一次情報が社内に眠っているケースが多くあります。ライター任せではなく、編集側が意図を持って情報を引き出し、構成に落とし込むプロセスこそが、LLMO時代に求められるリライトの本質といえるでしょう。
▼記事リライトの外注について不安を抱えている方は、下記の記事も参照ください。
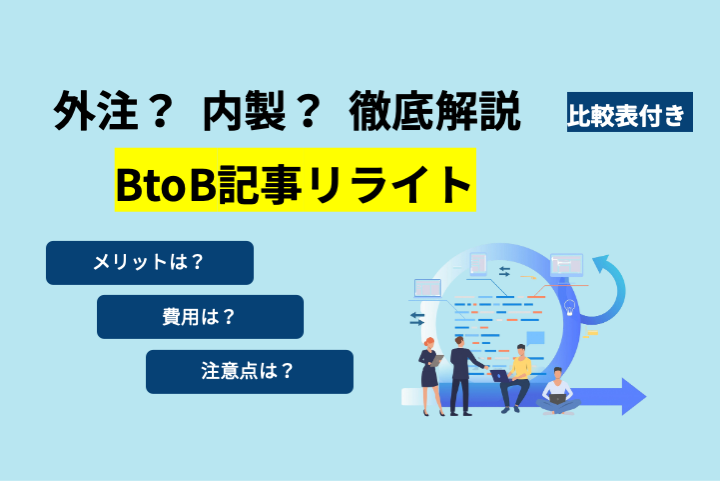
どの記事のリライトから手をつけるべきか?
BtoBオウンドメディアにおいて、すべての記事を一度にリライトすることは現実的ではありません。限られたリソースで最大の効果を得るには、優先順位の見極めが欠かせません。
以下のいずれかに該当する記事は、リライト対象として早急に見直すことをおすすめします。
更新が1年以上されていない記事
検索アルゴリズムやユーザーの検索意図は日々変化しています。とくにテクノロジー系や業界トレンドを扱う記事は、「古い」だけで評価を下げられるリスクがあるため、定期的な更新が不可欠です。
流入が減っている or CVが発生していない記事
GoogleアナリティクスやSearch Consoleを活用して確認した結果、直近6〜12か月で流入が減少している記事や、CVに結びついていない記事は改善余地のある「眠れる資産」といえます。タイトルや構成、CTAなどの見直しで成果が変わる可能性があります。
古い情報・導線の不備がある記事
リンク切れや廃止されたサービスの情報など、読者の信頼を損ねかねない要素を含んだ記事は、早急に対処が必要です。また、CTAがない、リンク先が不適切など、導線に問題がある記事もコンバージョン機会を逃しています。
これらを踏まえると、特に、検索順位が中位〜下位(11〜30位)に沈んでいる記事は、改善効果が出やすいため、優先して手を加えるべき対象と言えるでしょう。
また、内容が自社の現状と乖離していたり、信頼性に欠ける情報が含まれている場合は、あえて「非公開」にする判断も有効です。無理に残しておくよりも、サイト全体の品質スコアを下げるリスクを避けたほうが長期的にプラスになります。
放置せず、「改善すべきか/非公開にすべきか」も含めて計画的にメンテナンスを行うことが、BtoBコンテンツの成果を底上げする第一歩になります。
よくある記事リライトの”失敗”パターン
BtoB記事のリライトは、適切に行えば成果を大きく伸ばす可能性を秘めています。しかし、やり方を誤ると、時間やコストをかけても効果が出ないどころか、かえってパフォーマンスを落とすリスクもあります。以下に、よくある失敗パターンを挙げます。
- 失敗パターン1:とりあえず文字数を増やす
- 失敗パターン2:表現だけの変更
- 失敗パターン3:外注に丸投げしてしまう
(※)Google検索セントラル「2022 年 8 月の Google の有用なコンテンツの更新についてクリエイターが知っておくべきこと」においても、「Google が優先する文字数があるとどこかで聞いたか読んだかしたために、特定の文字数になるように記事を書いていますか(そのような設定は存在しません)。」と明確に記載されています。
これらの失敗を避けるためには、「何を伝えるべきか」「誰に届けるべきか」「どう構成すべきか」といった戦略的な編集・設計プロセスが欠かせません。単なる修正作業ではなく、“再設計”としてリライトをとらえることが、成功への第一歩です。
▼リライトの失敗と改善策について、より詳しく知りたい方は、下記の記事もご一読ください。
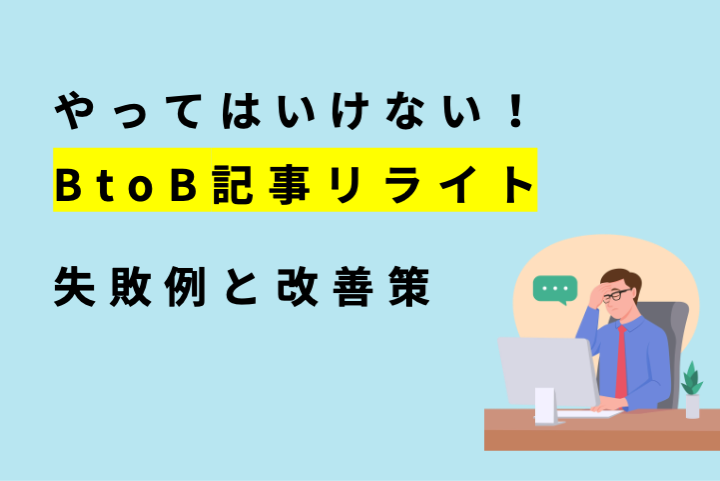
記事リライトを成功させるための3ステップ
BtoB記事のリライトは、単なる加筆修正ではなく「再設計」に近い作業です。成果につなげるためには、構成や情報の取捨選択だけでなく、読者視点での再編集が欠かせません。
以下の3ステップで進めることで、リライトの成功確度が大きく高まります。
まず取り組むべきは、想定読者(ペルソナ)が「いま何に困っているのか」を再確認することです。検索意図が変化していたり、業界のトレンドが変わっている可能性もあります。アクセス解析ツールや検索クエリの変化をもとに、記事が“現在の問いに答えているか”を見直しましょう。
読者の疑問に答えるには、信頼性の高い一次情報が不可欠です。自社の事例、開発経緯、社内の専門家の声などをヒアリングし、構成を「Q(疑問)→A(結論)→Reason(根拠)→CTA(行動喚起)」の順に再構築することで、AIにも読者にも伝わる記事になります。
構成だけでなく、文中の語句や見出しもAIに伝わりやすい形に調整します。抽象的な表現は避け、具体的なキーワードや因果関係を明示することが重要です。また、読者に次の行動を促す明確なCTAも忘れずに設置しましょう。
▼より詳しいステップを知りたい方は、下記の記事もご一読ください。
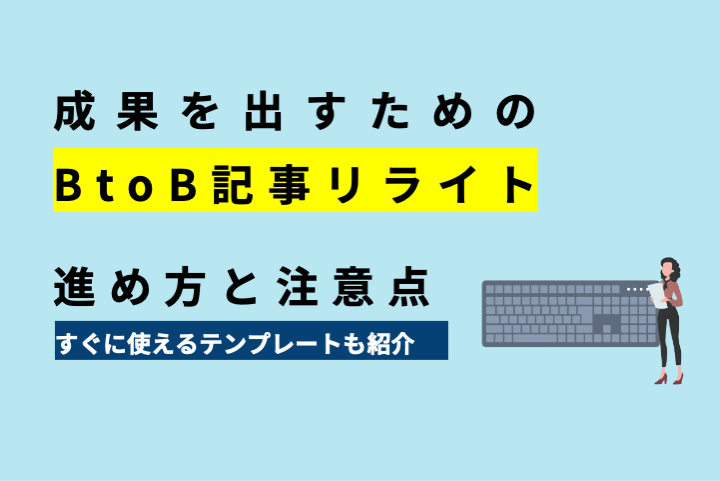
まとめ|BtoB記事のリライトは「編集力×構成力」がカギ
ここまで解説してきたように、BtoBオウンドメディアにおけるリライトは、単なる加筆修正ではなく「編集し直す」ことに近い作業です。特に現在は、検索エンジンだけでなく、AIに伝わる構成と一次情報の質が成果を左右する時代となりました。
• リライト=記事の“再構成”であり、再出発
• 構成・一次情報・AI最適化の三位一体で成果につながる
• 放置せず、計画的にメンテナンスすることが重要
リライトを通じて、検索順位やCV率を回復・向上させることは十分可能です。とはいえ、闇雲に手を加えるだけでは逆効果になるケースもあります。
だからこそ、ターゲットに合わせた編集設計と、構成・一次情報の見直しが不可欠と言えるでしょう。
▼具体的なリライトの進め方は、下記の記事に詳しく記載しています。
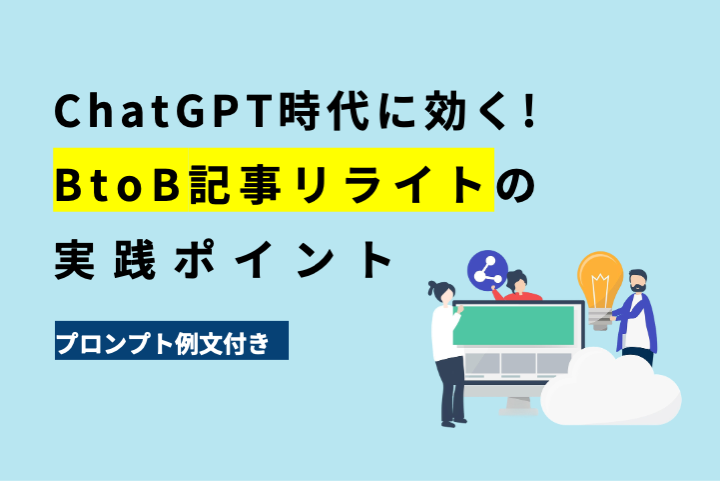
外注に”お任せ”した記事のリライトを検討している方へ
「どの記事から手を付けるべきかわからない」「そもそも構成の見直し方が分からない」という場合は、ぜひリードレまでご相談ください。
現状の課題を可視化し、改善に向けた編集方針をご提案させていただきます。

まずは自分で既存の記事をチェックしてみたいという方は、下記より無料の「LLMOチェックリスト」をダウンロードいただき、ご活用ください。