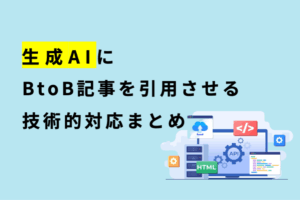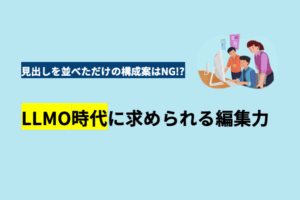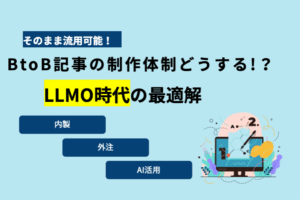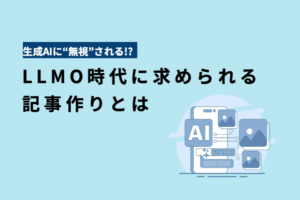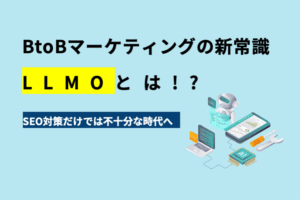「コンテンツを出しても、検索順位が伸びない」
「生成AIに拾われていない気がする」
BtoB企業における中長期的なコンテンツマーケティングは、これまでSEOを軸に成果を狙う手法が主流でしたが、いまその前提が大きく揺らぎ始めています。
GoogleのAI Overviews(生成AIによる検索要約)やChatGPTをはじめとした生成AIの普及により、LLMO(大規模言語モデル最適化)という新たな視点が注目されています。
本記事では、実際にLLMO対策に取り組み、問い合わせ数やCVR向上といった成果を上げたBtoB企業の3事例を紹介。
国内のSaaS企業から、海外の製造業・保険業界まで、業種やアプローチの異なる成功例を比較しながら、「LLMO時代に成果を出すには何が必要か」を紐解きます。
「自社のコンテンツはAI時代に適応できているのか?」と不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
▼LLMOについて、基礎から知りたいという方は、こちらの記事をまずご一読ください。
事例1 【リードレ支援】CVに直結した「ヒアリングベース」の記事最適化
リードレが支援したBtoB向けSaaS企業では、以前、専門ライターに完全外注した記事が検索上位を維持しており、そこからのコンバージョンを商談に繋げていました。
しかし、Googleのアルゴリズム更新やAI Overviews(生成AIによる検索要約)の登場を機に、検索順位が急落。20位以下に沈み、アクセス・CV(問い合わせ)ともに激減していました。
この状況を受け、リライトの依頼を受けたリードレでは、次のような改善アプローチを実施しました。
- 取り組んだ施策の内容
- 成果
この事例から見えるのは、「誰が書いたか」以上に、「どう聞き出し、どう設計し、どう届けるか」という編集設計・構成力の重要性です。とくにLLMO時代においては、
• 表面的なキーワード対策ではなく、検索意図との接続精度
• コンテンツ内での因果関係の明示
• 一次情報を“意味のある位置”に配置する文脈設計
が成果に直結します。
また、生成AIが記事の文脈を評価する今の検索環境では、「実際に何が起きていたのか」を、読者とAIの両方に“伝わる形”で再現できる編集力が問われているといえるでしょう。
▼LLMO時代に求められる編集力については下記の記事もご一読ください。
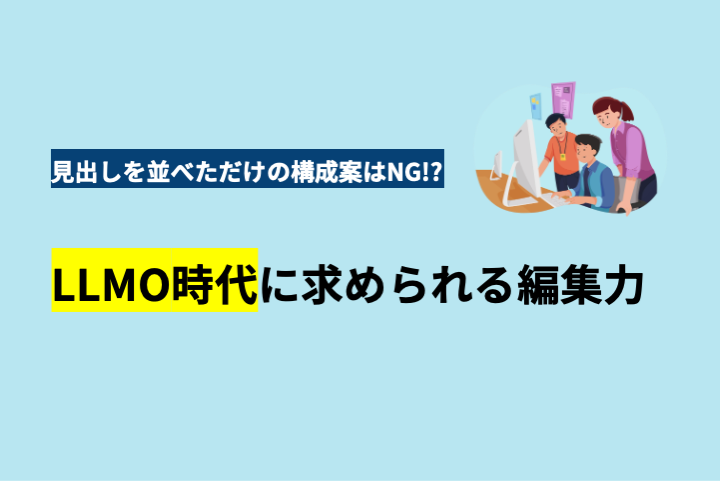
事例2 【海外】ChatGPTに“拾われる”構造を設計
米国のある生命保険会社では、企業ブログでコンテンツ発信を継続していたものの、検索流入が低迷していました。
特にChatGPTをはじめとする生成AIを活用した検索(AEO=Answer Engine Optimization)において、記事が“拾われない”状況が課題でした。
そこでマーケティング支援会社「Growth.pro」の支援により、次のようなAI検索最適化の施策に取り組みました。
- 取り組んだ施策の内容
- 成果
この取り組みは、アメリカで先行するLLMO対策の具体事例として非常に参考になります。
特に、以下のようなポイントはBtoB領域にも転用可能です。
• 質問に答える形での構成
• 一次情報の配置場所の工夫
• 文脈に沿った構造設計によるAI理解の促進
アメリカは日本よりもAEO(Answer Engine Optimization)やLLMOへの対応が進んでおり、このような先行事例をチェックすることで、成功のポイントを押さえることができます。次も同様に、アメリカの企業の事例を紹介します。
事例3 【海外】AI Overviews最適化で流入2300%アップ
米国のある中堅製造業者は、従来のSEO施策を継続していたものの、GoogleのAI Overviews(旧SGE)にはまったく表示されず、検索流入の伸び悩みが課題となり、AI検索時代への対応が急務となっていました。
そこで同社が取り組んだのは、次のような内容です。
- 取り組んだ施策の内容
- 成果
参考:https://diggitymarketing.com/ai-overviews-seo-case-study/
この事例は、従来型SEOでは評価されにくくなったコンテンツが、「質問に対する精度の高い回答」と「独自の一次情報」を意識した構成へ再設計することで、AIにもユーザーにも“伝わる”ページに生まれ変わったという好例です。
特にBtoB製造業のように、製品知識や技術解説が重要な業種では、こうした情報設計の工夫が、生成AIに”拾われるかどうか”を左右します。
事例の共通点と成功のポイント【なぜ成果が出たのか?】
ここまで紹介してきた3つの事例は、業種や企業規模、国は異なれど、共通して“ある変化”を実践したことで成果につながっています。それは、「検索に評価される構造」と「一次情報を活かした文脈設計」を意識した編集プロセスです。
| 企業 | 課題 | 主な施策 | 成果 |
|---|---|---|---|
| 1 リードレ支援先 | CV発生せず | ヒアリング+リライト | CV率2.5倍 |
| 2 生命保険会社(米国) | アクセス低迷 | AEO対応+一次情報挿入 | 問い合わせ270%増 |
| 3 中堅製造業者(米国) | AIに拾われない | AI Overviews構造最適化 | トラフィック2300%増 |
具体的には、次のような共通点が見られます。
- ヒアリングや統計データを通じた一次情報の活用
-
すべての事例において、Web上に既出の情報だけではなく、自社独自の経験・データ・知見を盛り込むことで、AIからも読者からも「有用な情報源」として認識されやすくなっています。
- Q&Aや因果構造を意識した“構造的な設計”
-
見出し・段落・文章のつながりを、「誰のどんな問いに答えているのか」という観点で構築。これが、AIにとって理解しやすい文脈を生み、AI OverviewsやChatGPTによる引用にもつながりました。
- 小手先のテクニックのみでなく、コンテンツの”質”に力を入れていたこと
-
どの事例も、CMSのテーマ変更や被リンク数の増加といった小手先のテクニックのみに頼るのではなく、「どう伝えるか」という編集面に注力した結果、成果が現れています。つまり、成果を左右したのは“記事の中身”でした。
成果を生むのは「誰が書くか」ではなく「どう設計するか」
LLMO時代のBtoBコンテンツでは、もはや「キーワードを埋めた記事を量産する」だけでは成果は望めません。今回紹介した3つの事例からも明らかなように、
• どのような構造で問いに答えるか
• 一次情報をどのように配置するか
• AIにも読者にも文脈が伝わる設計になっているか
といった「編集設計の巧拙」が、検索流入やCV数に直結する時代が到来しています。
もちろん、専門性を持ったライターや、ツールの選定も重要な要素です。しかし、それ以上に問われるのは、現場情報を引き出し、構造化し、編集・執筆を最適化する力です。
ChatGPT時代のコンテンツ制作、「設計」からご相談いただけます
「自社でもLLMO対策を始めたいが、何から着手すべきかわからない」
「記事は出しているが、AI検索に拾われていない気がする」
「構成や一次情報の整理を含めた、編集体制を見直したい」
このようなお悩みがありましたら、BtoBマーケティングでコンテンツの設計〜制作〜運用まで一貫支援するリードレにお気軽にご相談ください。貴社の目的や体制に合わせた、最適なコンテンツ戦略をご提案いたします。

▼自社の既存コラムの状況が気になる…という方は、無料のチェックリストをご活用ください。