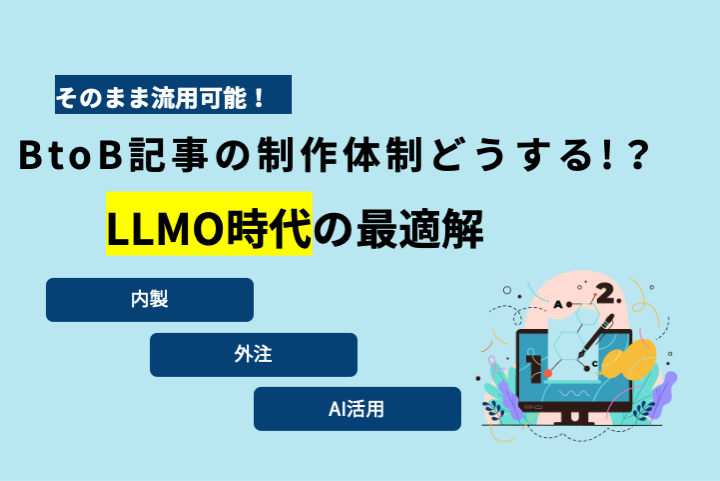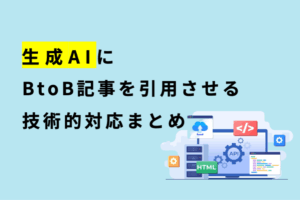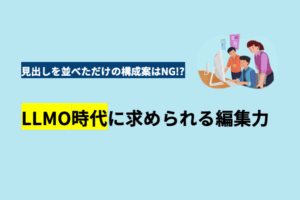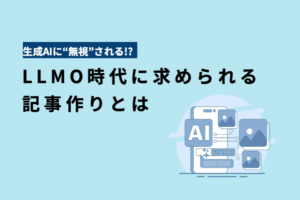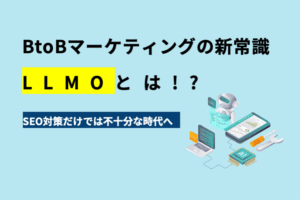「AIで記事を作ってみたけど、全然読まれない…」
「外注しているのに、成果につながっている気がしない」
BtoB企業のWeb担当者から、こんな悩みを聞く機会が増えています。生成AIの普及により、記事制作の手段が多様化する一方で、「誰が・どうやって書くか」が成果を左右する時代になりつつあります。
本記事では、ChatGPTに代表されるAIに“引用されやすい”記事=LLMO対策を前提とした制作体制について、「内製・外注・AI活用」それぞれのメリット・デメリットを徹底比較。制作を依頼する側・する側、どちらにとっても役立つ判断材料を提供します。
▼LLMOについて、基礎から知りたいという方は、こちらの記事をまずご一読ください。
LLMO時代の「記事制作」に求められるものとは
ChatGPTなどの生成AIが情報収集の手段として一般化する中で、記事に求められる役割は大きく変わってきています。従来のSEO対策では、構造やキーワード配置などが重視されていましたが、LLMO(ローカル・ランゲージ・モデル最適化)においては、それだけでは不十分です。
では、AIにも読者にも伝わる「拾われる記事」を作るには、何が必要なのでしょうか。
単なる文章作成ではなく「一次情報の言語化」が鍵
今後のSEOおよびLLMO対策で最も重要視されるのは、「一次情報」の有無です。実体験や業務で得た知見、自社独自の調査データなどは、他にはないオリジナリティとしてAIにも評価されやすくなります。
Googleも、実際の体験に基づいた専門知識や深い理解を示すコンテンツ(例:製品やサービスの使用経験など)を重視しています。
参考:Google検索セントラル「2022 年 8 月の Google の有用なコンテンツの更新についてクリエイターが知っておくべきこと」
E-E-A-Tを高める「実体験」「専門性」の明示
Googleは、コンテンツの評価基準としてE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視しています。なかでも「経験(Experience)」の評価が近年追加され、実際に体験したこと・現場での知見に基づいた記事であることが、ますます重要になっています。
参考:Google検索セントラル「品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加」
読者とAIの両方に伝わる「文脈性」と「構成力」
LLM(大規模言語モデル)は、文脈を重視して情報を理解・出力します。そのため、意味の通った構成や因果関係の明示が欠かせません。読者にとって読みやすい構成=AIにとっても“引用しやすい”構造です。
FAQ形式やQ&Aスタイルで情報を整理することで、LLMO的にも好まれるコンテンツになります。
ここで解説しているE-E-A-Tや一次情報の重視といった要素は、本来はGoogle検索におけるSEO指針として定められたものですが、近年ではChatGPTなどの生成AIも同様の基準で“信頼に足るコンテンツ”を見極めようとしています。つまり、SEOとLLMOは評価軸の多くを共有しており、両者の対策が連動しているのが現実です。
制作体制をどう整える? 3つの選択肢と向き合い方
LLMO時代のコンテンツ制作では、「誰が」「どうやって」記事を作るかが、従来以上に成果を左右します。
とくに、SEOとLLMOを両立させるには、専門性・一次情報・構成力が欠かせません。
では、内製・AI・外注といった手段のなかで、自社にとって最適なスタイルとはどれなのでしょうか? 以下に、それぞれの特徴と活かすための条件をまとめました。
選択肢① 内製(→自社のノウハウを余さず反映可能)
社内リソースを活用して記事を内製するスタイルは、コストや柔軟性の面で魅力があります。一方で、コンテンツの質や継続性には課題も伴います。
- メリット
- デメリット
- スムーズにPDCAが回る条件
選択肢② AI活用(→スピードと効率性が強み、ただし限界も)
近年は、ChatGPTなどの生成AIを活用して記事制作を効率化する動きも広がっています。アイデア出しや文章生成がスムーズに進む一方で、一次情報の欠如や構成の粗さといった課題も顕在化しています。
- メリット
- デメリット
- スムーズにPDCAが回る条件
選択肢③ ライター・制作会社への外注(→専門性をどう引き出すかがカギ)
リソース不足やスキル面の課題から、外部ライターや制作会社に記事制作を依頼するケースは多くあります。とくに構成力や文章力の点で安定した品質が期待できますが、一次情報に乏しくなりがちなのが弱点です。
- メリット
- デメリット
- スムーズにPDCAが回る条件
最適解は「ハイブリッド型」の制作体制
LLMO時代のコンテンツ制作においては、「内製か外注か」「AIを使うべきか」など、単一の手法にこだわるのではなく、それぞれの手段の“いいとこ取り”をする ハイブリッド型の体制が効果的です。
たとえば次のようなフローが代表的です。
- AIで構成案や見出しのたたき台を生成
→効率よく全体像を把握し、時間短縮に - 社内の開発・営業部門などから一次情報をヒアリング
→専門性・独自性の高いコンテンツの素材を確保 - 構成・執筆・編集はプロに外注
→論理性・読みやすさ・AIへの文脈伝達力を担保
このようなハイブリッド体制では、AIのスピード感・社内の専門知・外注の構成力をすべて活かすことができ、読者とAI双方に刺さるコンテンツを安定的に生み出すことが可能になります。
実際に、私たちリードレでもこの体制を採用しています。たとえば、ある製造業のクライアントでは、以下のような形でコンテンツ制作を行いました。
リードレが開発部門・営業部門にヒアリングを行い、既存顧客の課題感や開発の経緯を把握した上で、構成・ライティングを実施しました。結果的に”一般論”に留まらない、オリジナルのホワイトペーパーを仕上げることができました。
リードレでは、長年、このような制作フローを続けてきましたが、LLMOの文脈を踏まえると、このような「ハイブリッド型」の制作こそが、時代に求められる“勝てる制作体制” といえるでしょう。
誰が書くかではなく、“どう書くか”の時代へ
生成AIやAI Overviewsの普及により、従来の「誰が記事を書くか」だけでは語れない時代が到来しています。
特にBtoB領域では、「どんな経歴のライターが書くのか」というご相談をいただくことも少なくありません。もちろん、業界知識や経験も大切な要素です。
しかし現実には、いかに業界歴が長いライターであっても、その業界の最新情報や現場感覚を継続的にアップデートしている人材は限られます。加えて、そうしたライターであっても、自社特有の商材や開発経緯、顧客課題の詳細までは把握できていないのが一般的です。
リードレでも、専門性を持った編集チームが記事設計・執筆を担っていますが、それでもなお、現場部門からのヒアリングを通じて一次情報を引き出すプロセスは欠かせません。
いま、求められているのは、誰が書くかではなく、
・現場から何を引き出すか
・それをどう整理し、構成するか
・そしてAIにも読者にも伝わる形にできるか
といった「どう書くか」の部分です。
SEOやLLMOに対応したコンテンツ制作は、こうした総合的な設計力と現場理解が問われるフェーズに入っています。
ChatGPT時代の”伝わる=拾われるコンテンツ”作りを支援します
「AIにも拾われる記事を作りたい」
「SEOもLLMOも対策したい」
このような課題感をお持ちでしたら、ハイブリッドな制作体制で、設計から制作まで一貫した支援が可能なリードレまで、お気軽にご相談ください。

▼すでに記事制作を進めている方で、LLMO対策について確認しておきたい方は、無料でダウンロードできるチェックリストもご活用ください。