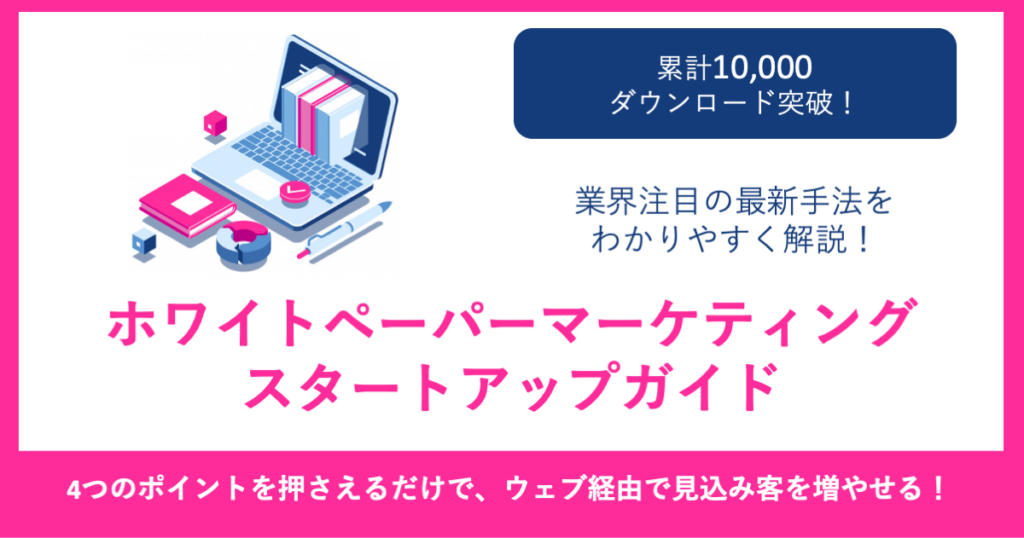「営業活動を強化したいけれど、広告だけでは成果が出にくい」
「Webからの問い合わせを増やしたいが、何から始めればいいかわからない」
こうした悩みを抱えるBtoB企業に注目されているのが、コンテンツマーケティングです。検索やSNSを通じて潜在顧客と出会い、資料や記事で信頼を獲得して商談へとつなげる手法で、広告に頼らず中長期で成果を積み上げられる点が最大の魅力です。
本記事では、コンテンツマーケティングの基本から導入メリット、具体的な施策の種類や進め方、よくある失敗と成功のポイント、さらに外注を検討する際の注意点までを網羅的に解説します。
初めて取り組む方でも「全体像」がわかり、次の一歩が見える内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
コンテンツマーケティングとは?
まずは基本的な定義を押さえ、BtoB企業が取り組む意義を整理しましょう。コンテンツマーケティングの本質を理解しておくことで、施策の選び方や投資の優先順位が明確になります。
コンテンツマーケティングの定義
コンテンツマーケティングとは、見込み顧客にとって価値のある情報を継続的に発信し、信頼関係を築きながら購買行動へと導くマーケティング手法です。
BtoBの営業活動は顧客の導入検討期間(=リードタイム)が長く、導入担当者の情報収集も入念に行われるのが特徴です。そこで、企業ブログ、ホワイトペーパー、事例記事、動画などのコンテンツが導入担当者の「情報源」として機能し、購買の判断材料として活用されます。
ここで「情報の押し付け」ではなく、「相手が知りたい内容」を的確に届けることで、自然に自社の商品・サービスへの関心を高めてもらうことを狙います。
SEOや広告との違い、BtoBでの位置づけ
コンテンツマーケティングはSEOや広告といった用語と混同されがちですが、その役割や性質には違いがあります。
- SEOとの関係
-
SEOは「検索で上位表示されること」を目的とします。一方でコンテンツマーケティングは「顧客に役立つ情報を届けること」を中心に置き、その結果としてSEO評価が高まるという関係性にあります。つまり、SEOは手段の一つであり、コンテンツマーケティングの中に含まれる位置づけです。
- 広告との違い
-
広告を活用することで短期的に認知や流入を増やせますが、出稿を止めればその効果はすぐに消えます。
それに対し、コンテンツマーケティングは資産型の施策であり、過去に作成した記事やホワイトペーパーが中長期的にリード獲得を支え続けます。
BtoB領域では、購買決定に至るまでの情報収集がほぼオンラインで完結する時代になっています。そのため、自社の知見を「顧客に届く形」にして蓄積していくことこそが、営業活動の基盤を強化する最も効果的な方法といえます。
BtoBにおけるコンテンツマーケティングの導入メリット
コンテンツマーケティングの導入によってどのような効果が得られるのかを理解すると、自社にとっての必要性が明確になります。
ここでは、BtoB企業にとって代表的な4つのメリットをわかりやすく整理します。
1:中長期的にマーケティングコストを低減できる
「広告は掛け捨て、コンテンツは資産になる」
このような話を耳にして、コンテンツマーケティングに関心を持ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
これは、特にウェブサイトへの集客施策としてのコンテンツ(主にSEOコラム)の価値を端的に示した言葉です。
ウェブサイトへの集客施策としては、ウェブ広告(リスティング広告やSNS広告など)やプレスリリースを出稿することも選択肢の1つです。もちろん、これらの施策も運用しだいで大きな集客効果を期待できます。
しかし、このような広告系の施策で集客をするためには、予算を投下しつづけるしかありません。広告出稿費の支払いをストップした瞬間に、当然ながら集客効果はゼロになります
一方で、SEOコラムをはじめとするコンテンツは、制作費こそ発生するものの、その後は基本的には費用が発生しません。そして、検索上位に表示され続けている間は、一定の流入が発生し続けます。
そのようなコンテンツを増やしていくことができれば、”掛け捨て”である広告出稿の費用を減らしても、必要な数の流入を獲得していくことが可能です。
そのため、コンテンツマーケティングは中長期的な視点で見るとマーケティングコストの低減につながるのです。
2:スモールスタートしやすい
コンテンツマーケティングは、自社のコーポレートサイトやサービスサイト、ブログサイトといったオウンドメディアでSEOコラムをはじめとするコンテンツを公開する形で実践します。
最近では、Wordpressをはじめとする無料で利用可能な様々なCMS(Contents Management System)が提供されています。
このようなCMSを活用すれば、オウンドメディアを簡単に立ち上げて、コンテンツマーケティングをスタートすることが可能です。
さらにコンテンツ制作は、必ずしも外部の制作会社に依頼する必要はありません。
SEOやウェブマーケティングに関して一定程度の知識を持った人が、SEMRushのようなアナリティクスツールなどを活用しつつターゲットとするSEOキーワードを選定し、それにもとづいて社内メンバーがコンテンツを制作するといった方法も可能です。
このように、コンテンツマーケティングは現状の予算にあわせてスモールスタートをすることが可能なマーケティング施策です。
3:具体的な数値にもとづくPDCAを回しやすい
Googleアナリティクス、Googleサーチコンソール、SEOツール、ヒートマップツール、マーケティングオートメーションなど、今日では特にウェブマーケティングの分析・改善に役立つ様々なITツールを活用できます。
そして、これらのツールを駆使することで、次のような数値を可視化することが可能です。
- 流入数が多い検索キーワード/ページ
- 閲覧数が多いページ
- 離脱率が高いページ
- コンバージョン(問い合わせ、資料ダウンロードなど)への貢献度が高い流入元ページ
- 自然検索経由でのコンバージョン数(リード獲得件数)
など
このように、コンテンツマーケティングは実行した施策の効果を具体的な数値で評価しやすいので、PDCAサイクルを回して継続的な改善活動を続けられることも大きなメリットです。
4:ブランディング効果を期待できる
コンテンツマーケティングでは、SEOコラムやホワイトペーパーなどのコンテンツを通じて自社が蓄積している知識やノウハウを発信します。
蓄積された知識やノウハウは、自社にとっては当たり前のものであっても、他社にとっては非常に有益な情報であるということがよくあります。
裏を返すとそのような情報を発信しなければ、どれほどコンテンツを制作・公開してもありきたりな情報ばかりを発信することになってしまい、成果にはつながりづらいです。
そのため、コンテンツマーケティングを進めるあたっては自社が保有している知識やスキルを棚卸したうえで、SEOキーワードやターゲットとするリード(見込み客)の情報ニーズを踏まえつつコンテンツを制作・公開していくことが重要です。
ここで他社にとって有益な情報を数多く発信できれば、大きなブランディング効果が期待できます。
BtoBにおけるコンテンツマーケティングの主な施策と種類
一口にコンテンツマーケティングといっても、さまざまな施策があります。ここでは、BtoB企業でよく活用される代表的な種類と特徴を整理します。
オウンドメディア記事(コラム、事例記事など)
自社が運営するWebサイト(オウンドメディア)に記事コンテンツを公開する方法で、業界トレンドの解説コラムや、自社サービスの導入事例記事などが代表的な形です。
こうした記事は、検索を通じて新規の見込み顧客に自社を見つけてもらえるだけでなく、「実績やノウハウを公開している信頼できる会社」という印象を与えます。
さらに、記事を継続的に増やしていくことで長期的なアクセスを集められるため、コンテンツマーケティングの基盤となる施策といえます。
ホワイトペーパー
ホワイトペーパーは、特定の課題やテーマを深掘りした資料をPDFなどで提供する施策です。
記事よりも詳しい情報を求める見込み顧客に向けて「ダウンロード」の行動を促せるため、氏名やメールアドレスといったリード情報を獲得できるのが大きな特徴です。
さらに、資料として社内共有されるケースも多く、営業活動の支援や商談化の確度を高める効果も期待できます。
メールマーケティング
メールマーケティングは、獲得したリードに対して定期的に情報を届ける方法です。メールマガジンやセミナー案内を活用することで、検討中の見込み顧客に自社を思い出してもらう機会をつくれます。
特にBtoBの商談は導入までの検討期間が長いため、記事やホワイトペーパーで得た関心を維持し、最終的な「相談・問い合わせ」につなげるために、メールは重要なフォロー手段といえます。
SNS・動画活用
X(旧Twitter)やYouTube、TikTokなどのSNSや動画配信を活用して情報を広げる方法です。
SNSは記事やホワイトペーパーの告知に使えるほか、動画は「サービスの使い方」や「顧客インタビュー」を直感的に伝えられるのが強みです。さらに、拡散力が高いため短期間での認知拡大に向いており、検索エンジン以外の新しい流入経路を作る手段として効果的です。
SNS活用はBtoCのイメージが強いと考えている方も多いかもしれませんが、最近ではBtoBで活用される機会も増えつつあります。
コンテンツマーケティングの導入ステップ
次に、BtoB企業が実際に導入する際の流れをステップごとに解説します。全体の手順を把握しておくことで、どこから着手すべきか、また外部に委託する場合に何を依頼すべきか判断しやすくなります。
STEP1 目的・KPIの設定
最初のステップは「何のために取り組むのか」をはっきりさせることです。
「問い合わせ数を増やす」「商談化率を高める」といったゴールを明確にしたうえで、KPI(成果を測る指標)を設定します。たとえば「記事からの資料ダウンロード数」や「問い合わせ件数」など、数字で進捗を確認できるようにしておくと、後の改善がしやすくなります。
STEP2 ペルソナ設計とカスタマージャーニー整理
次に、自社の見込み顧客像を具体的に描きます。
自社のターゲットとなる企業を意識した上で「どんな役職の人が、どんな課題を抱えて、どんな情報を探しているのか」を整理し、その人が契約に至るまでの情報収集プロセス(カスタマージャーニー)を書き出します。これにより、どの段階でどんなコンテンツを用意すればよいかが見えてきます。
STEP3 コンテンツ企画と制作体制の構築
ペルソナやカスタマージャーニーが整理できたら、次は「どんな記事や資料を作るか」を計画します。
たとえば初期段階の見込み顧客向けには「業界の基礎解説コラム」、検討が進んでいる層には「導入事例記事」や「比較表」を用意する、といった具合に段階ごとにテーマを割り振ります。
また、制作体制も事前に決めておくことが重要です。社内にライティングが得意なメンバーがいれば自社で記事を作成し、専門性の高いテーマや分量が多い場合は外部の制作会社に依頼すると効率的です。
さらに、公開までの流れを「企画 → 原稿作成 → 校正 → 公開 → 拡散」といったフローに整理しておけば、担当者が変わっても安定してコンテンツを発信できます。
STEP4 運用・効果測定・改善
コンテンツは公開して終わりではなく、実際の成果を確認しながら改善を繰り返すことが欠かせません。
Googleアナリティクスやサーチコンソールを使えば、どの記事から多くの問い合わせが生まれているのか、どのページで離脱が多いのかといった情報を把握できます。
定期的に効果をチェックし、テーマの見直しや導線改善を行うことで、成果は徐々に積み上がっていきます。
BtoBのコンテンツマーケティングでよくある失敗と注意点
成功事例に学ぶだけでなく、失敗を防ぐ視点も欠かせません。ここでは、BtoB企業がコンテンツマーケティングに取り組む際に陥りやすい3つの落とし穴を整理します。
失敗例1 短期成果を求めすぎる
「記事を5本公開したのに問い合わせが来ない」「半年やっても成果が見えない」
取り組みの初期には、担当者からこのような声が上がってくるケースは少なくありません。
コンテンツマーケティングは広告のようにすぐに反応が返ってくる施策ではなく、資産を積み上げていく中長期の取り組みです。
短期で成果を期待しすぎると「やっぱり効果がない」と判断して施策をやめてしまい、せっかくの投資が無駄になります。始める前に「半年〜1年は育成期間」と理解して取り組むことが大切です。
失敗例2 評価指標(KPI)が曖昧
「記事を何本作ったか」「アクセス数が増えたか」だけを見ても、売上やリード獲得との関係は分かりません。評価指標(KPI)が明確でないと、成果を判断できずに社内での理解も得にくくなります。
たとえば、「月間○件の資料ダウンロード」「記事経由の問い合わせ○件」など、営業に近い数値を設定すれば、経営層にも成果を示しやすくなります。
失敗例3 社内リソース不足への対応
「記事を更新する時間がない」「専門知識を持つ人が執筆できない」という課題もよく見られます。
特にコンテンツ制作を社内だけで無理に回そうとすると、更新が止まり、結果的にマーケティング全体の効果が落ちてしまいます。
社内リソースが足りない場合は、外部の制作会社に依頼するのも一つの方法です。その際には、単なるライティング代行ではなく、自社の強みや専門性を引き出してくれるパートナーを選ぶことが重要です。
コンテンツマーケティング導入のポイント
取り組み開始後に成果を安定的に出すためには、いくつかの重要な視点があります。ここでは、BtoB企業が取り組む際に押さえておきたい3つのポイントを整理します
ポイント1 営業計画と直結させる
コンテンツマーケティングでは「記事を増やすこと」や「アクセス数を伸ばすこと」自体を目的にしてしまうと、成果につながりません。
大切なのは、自社の営業計画と結びつけることです。たとえば「新規顧客開拓に課題がある」ならリード獲得をKPIに設定する、「既存顧客のアップセルを狙いたい」なら事例記事や導入ノウハウ記事を増やす、といった形です。
コンテンツを営業計画に直結させることで、社内の合意も得やすくなり、マーケティング活動が「単なる広報」ではなく「売上に貢献する施策」として認識されます。
ポイント2 外注と内製の適切な組み合わせ
コンテンツマーケティングでは、すべてを社内で完結しようとするとリソース不足に陥り、逆にすべてを外注するとコストが膨らみ、自社の強みが反映されにくくなります。そこで重要なのが「役割分担」です。
たとえば、専門知識が必要なテーマ解説やホワイトペーパー制作は外注し、社内の空気感や現場感を伝える記事は内製する、といった組み合わせが効果的です。
また、外注先を「単なるライター」ではなく「パートナー」と位置づけ、企画段階から関わってもらうことで、自社ならではの強みを引き出すことができます。
ポイント3 継続性を担保する仕組みづくり
コンテンツマーケティングは1回や数か月の取り組みでは成果が見えにくく、継続が何より重要です。そのためには「仕組みづくり」が欠かせません。
具体的には、年間のコンテンツ計画を立てて公開スケジュールを明確にする、毎月の効果測定会議を設けて改善点を共有する、といったルールを決めると継続しやすくなります。
一度止まってしまうと再開に大きな労力がかかるため、「少しずつでも止めない」ことが成功企業に共通する特徴です。
コンテンツマーケティングの取り組みを外部に委託する場合
社内だけではリソースが不足する場合、外注や代行を活用するのも有効です。ただし、どの会社に任せるかによって成果は大きく変わります。ここでは、委託する会社選びのポイントを整理します。
制作会社を選ぶ際のチェックポイント
制作会社を選ぶ際は「見栄えの良い記事を作れるか」だけではなく、成果につながる視点を持っているかが重要です。
具体的には以下の点を確認すると安心です。
- BtoB分野での実績が豊富か
- ライティングだけでなく、マーケティング戦略全体を踏まえたコンテンツ制作が可能か
- 専門的なテーマに対応できる編集体制があるか
単なるライティング代行ではなく、戦略面まで伴走できる会社を選ぶことで、継続的な成果につながりやすくなります。
代行会社の比較・検討方法
外注コストは少ないに越したことはありませんが、記事の本数あたり・ホワイトペーパーの本数あたりの価格だけで判断するのは危険です。
費用に差があったとしても、調査やヒアリングを丁寧に行い質の高い記事を出す会社と、表面的な記事を大量生産する会社では、最終的な成果に大きな差が出ます。
比較する際には、サンプル記事やこれまでの事例を確認し、実際に「問い合わせや商談につながったコンテンツを作れているか」を見極めることが大切です。
外注と内製の使い分け
前述した通り、すべてを外注に頼るとコストが高くなり、自社の独自性が出にくくなります。逆に、すべてを内製でまかなうと更新が止まるリスクがあります。
おすすめは「戦略や難易度の高いコンテンツは外注」「現場の空気感を伝える記事や最新情報の更新は内製」といった組み合わせです。
また、外注先をパートナーとして長期的に関わってもらえば、自社の理解も深まり、内製と同じ目線で質の高いコンテンツを継続できます。
最近では、生成AIを活用してコンテンツの内製化を進める企業も増えています。リードレでも、豊富な制作実績を活かした”生成AI活用・コンテンツ制作支援プログラム”をご用意しています。
▼外注先の選び方については、下記の記事に詳しく記載されています。

BtoB企業がコンテンツマーケティングに取り組むならリードレにお任せ!
ここまで解説してきた通り、コンテンツマーケティングは単なる記事制作ではなく、BtoB営業を加速させる戦略的施策です。
とはいえ、成果の出るコンテンツはターゲット・ペルソナや自社商材の強みによっても異なるため、「他社の成功コンテンツをそのまま流用すればOK」というわけにはいかないのが難しいところです。
特に、経験のあるマーケターが在籍していない会社の場合、自社に合わせた最適な方法を検討する際には、マーケティング支援会社への相談が有効です。
リードレは、ホワイトペーパー制作500本以上・記事制作1,000本以上の実績をもとに、BtoB企業の課題をヒアリングし、戦略立案から制作・運用まで一貫してご支援しています。
「何から始めればよいかわからない」「外注と内製のバランスに悩んでいる」といった段階でも問題ありません。まずは情報整理からご一緒し、自社に合った進め方をご提案します。
ぜひ、下記のサービスガイドをご一読ください。
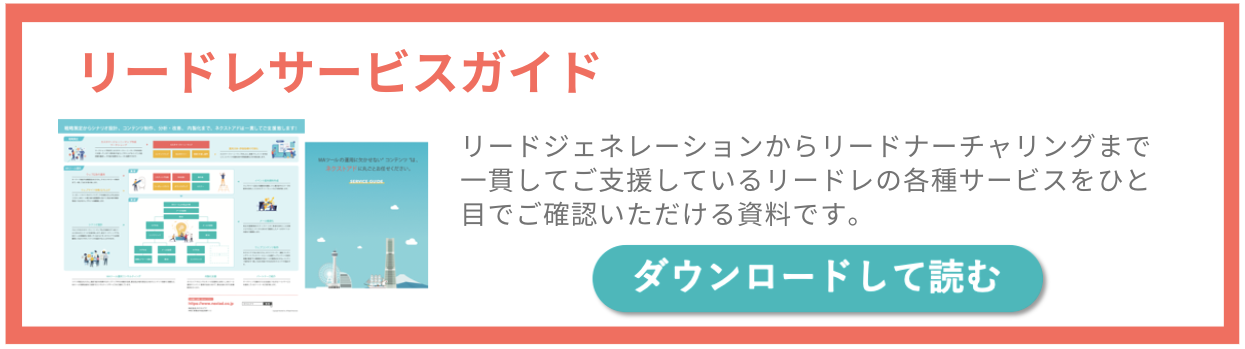
また、ホワイトペーパーを活用したマーケティングに役立つ無料の資料もご用意しておりますので、こちらもぜひダウンロードください。