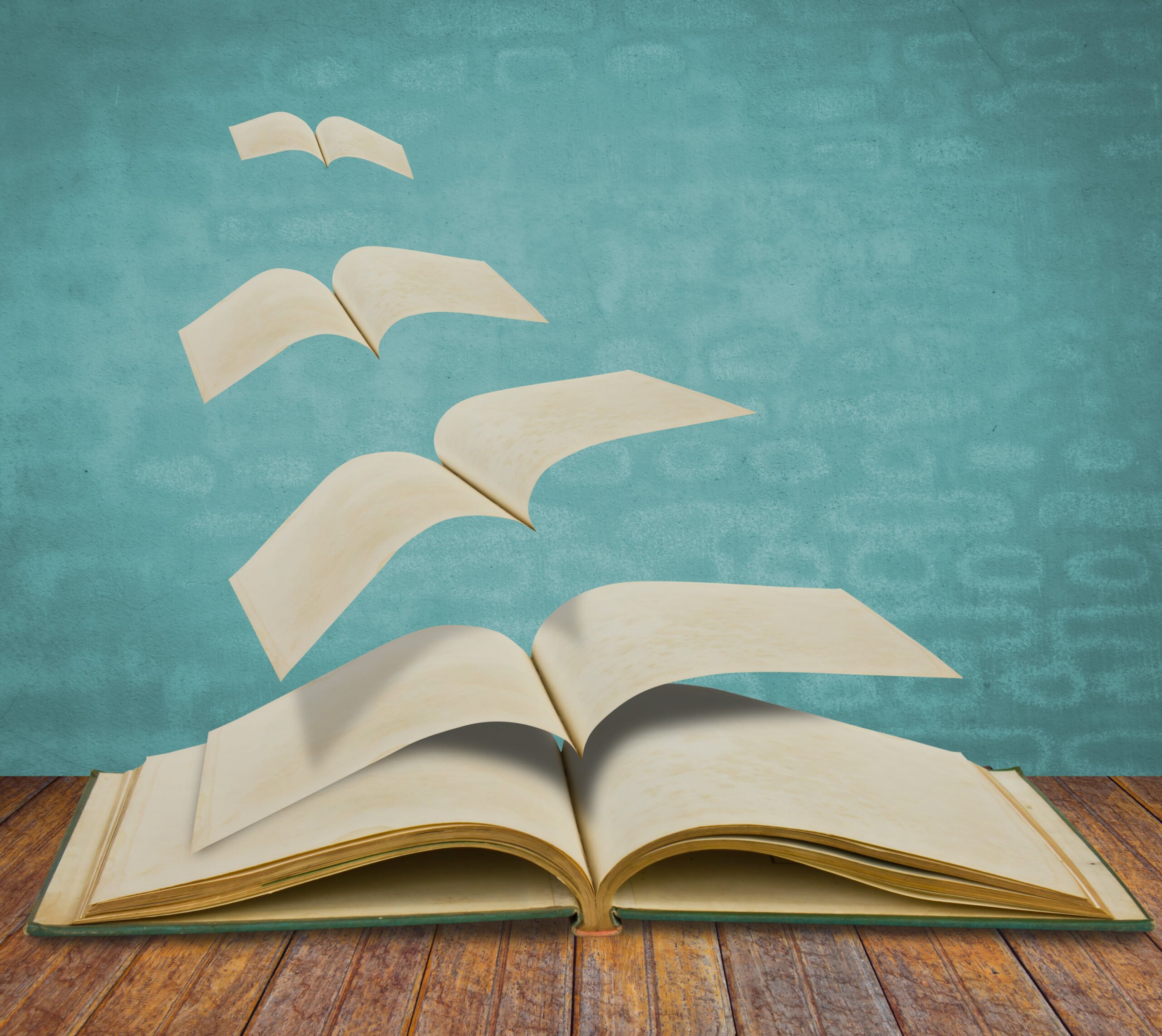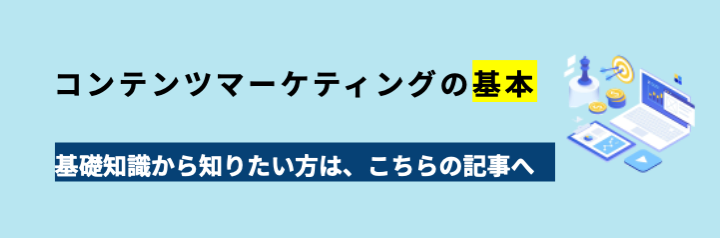コンテンツマーケティングで成果を出すためには、ホワイトペーパーやコラムといったコンテンツの冒頭に「リード文」を書くことが欠かせません。リード文は読者が最初に目にする部分であり、ここで心を掴めるかどうかが、その後の読了率やCVR(コンバージョン率)にも直結します。
一方で、コンテンツ制作担当者の中には「なかなかリード文を書き進められない」「パターンが思いつかず毎回悩んでしまう」といった課題を抱える方も少なくありません。
そこで本記事では、リード文をスムーズに書けるようになるために役立つ3つのパターンを、具体的な文例とともに解説します。
リード文とは? その役割をわかりやすく解説
リード文とは、ホワイトペーパーやコラムの冒頭に配置される短い導入文のことです。読者が記事を読み進めるかどうかを判断する最初の分岐点であり、コンテンツ全体の成果を左右する重要なパートといえます。
リード文には大きく2つの役割があります。ひとつは、読者が抱えている課題や不安を提示して「この先に答えがありそうだ」と感じてもらうこと。もうひとつは、本文で解説する要点をかいつまんで伝え、「読むことで得られる価値」を先に示すことです。
この2つを押さえることで、冒頭での離脱を防ぎ、最後まで読んでもらえる可能性が高まります。結果として、読了率の向上やコンバージョン率(CVR)の改善にもつながるのです。
一方で、毎回まっさらな状態からリード文を考えようとすると、冒頭で述べた通り「なかなか書き進められない」という状況に陥ってしまいます。特に、これからWebマーケティングを本格化しようとする企業の場合、コンテンツの量産が必要なケースも多いでしょう。
そんななか、1つのコンテンツ作るたびにリード文で頭を悩ませていると、なかなか制作を進めることができず、スケジュール全体の遅れにもつながりかねません。
こうした課題を解消するためには、あらかじめリード文のパターンを頭に入れ、それを押さえた上でリード文を書き始めることが重要です。
リード文の構成要素と基本フォーマット
リード文は大きく「導入」と「本編への誘導」の2つの要素で構成されます。この2つを意識するだけで、誰でもスムーズにリード文を書けるようになります。
その1:「導入」
最初の数行は、読者の状況や悩みを示して「これは自分に関係のある内容だ」と共感してもらうことが大切です。
たとえば、BtoBマーケティングに関する記事なら、次のように始めると自然です。
【導入部の例】
「記事は増えてきたのに、問い合わせにつながらない」
「何を書けばいいのか、毎回悩んでしまう」
その2:「本編への誘導」
導入で課題を示したら、次に「この記事(または資料)を読むと何がわかるのか」を簡潔に示します。
「本コラムでは、」「本資料では」につづける形で、タイトルで使用しているキーワードと連動させる形で作成するのが一般的です。
【例1】
タイトル:導入事例制作を外注する場合に押さえるべきポイント
「本編への誘導」:そこで、本コラムでは導入事例の制作を外注する場合に押さえるべきポイントを紹介します。
【例2】
タイトル:CVRを改善するために見るべき5つのポイント【BtoB企業向け】
「本編への誘導」:そこで、本コラムではCVRを改善するためにBtoB企業が見るべき5つのポイントを解説していきます。
ここでは、記事タイトルに含めたキーワードを再度入れることがポイントです。検索エンジンに「本文のテーマと一致している」と認識されやすくなり、SEOの観点でも有効です。
このように、リード文は「導入」と「本編への誘導」という2つの構成要素で成り立っています。
このうち、「本編への誘導」については、タイトルと連動させる形でキーワードだけを入れ替えれば良いので簡単に書き進めることができます。
一方で、「導入」については、コンテンツの内容に応じて大きくテキストを変化させる必要があります。「リード文をなかなか書き進められない」という方の多くも、この導入部分につまづいているのではないでしょうか?
裏を返せば、「導入」さえ乗り越えることができれば、リード文をスラスラと書き進められるはずです。そこで次項では、特に「導入」部分にフォーカスしてリード文でよくある3つのパターンをご紹介します。
リード文をスラスラ書くために覚えるべき3つのパターン
パターン1.業界事情と課題の紹介 〜最近、注目の対策はコレ!〜
【パターン1の文例】
近年、情報通信デバイスが多様化し、ユーザーの購買プロセスも複雑になっています。こうした状況のなか、一人ひとりのニーズに合わせることで顧客を獲得するため、Webマーケティングに取り組む企業が増加しており、注目を集めています。
そこで、本資料ではWebマーケティングに取り組む場合に押さえるべき3つのポイントを紹介していきます。
「導入」で、業界事情や課題に触れたうえで、注目されている対策を紹介するパターンです。
特に、BtoB領域でのコンテンツで使用するリード文としては、王道と言えるでしょう。使い回しやすいパターンですが、「注目の対策」が一般化している場合、「それなら知っている」と読者が離脱してしまう可能性もあるため、注意が必要です。
一方で、他社にはない先鋭的な製品やサービスを紹介する場合には適したパターンです。
パターン2.読者の課題をセリフで示す 〜その悩み、解消できます!〜
【パターン2の文例】
「コンテンツを量産しろと言われたけれど、リード文がなかなか書けない…」
「上司にコンテンツをチェックしてもらったら、リード文がイマイチだと言われた」
こうした悩みは「リード文のパターン化」によって解消できる可能性があります。
そこで、本コラムでは代表的なリード文のパターンを3つ紹介します。
読者が感じているであろう課題を書いたうえで、対策を伝えるパターンです。
読者の考えとコンテンツを直接リンクさせることができ、「具体的にどのような対策なのか?」と感じさせるため、本文への強い推進力を生みます。
ただし、課題感がマッチしていないと、リード文の時点で「私には関係がないコンテンツだ」と離脱されてしまう可能性があります。
そのため、このパターンを使う際には、あらかじめペルソナを設定した上で、その課題感を明確にしておくことが不可欠です。
また、セリフは多すぎると冗長になってしまうので、記載するのは2個、多くても3個までにしましょう。
パターン3.課題に気づかせる 〜その対策だけでは不十分!〜
【パターン3の文例】
これからWebマーケティングに取り組もうとする企業のなかには、ホワイトペーパーの制作・公開を検討している方も多いのではないでしょうか?
しかし、見込み客の数を増やすための施策としては、ホワイトペーパーを公開するだけでは不十分です。ホワイトペーパーでリードを獲得するには、その前提として、ホワイトペーパーを公開するサイトが相応の流入を獲得していることが不可欠だからです。
そこで、本ホワイトペーパーでは、ホワイトペーパーを有効に活用するためのSEO対策についてご紹介します。
ありがちな勘違い」を示し、それを否定することで新たな課題に気づかせるパターンです。
製品やサービスに関して精通している読者にとっては常識的な内容でも、認知・理解が浅い読者には「なぜ?」と本文を読んでもらえる可能性が大きく上がります。
そのため、製品やサービスの購買を意識し始めた、情報収集段階の読者をターゲットにしたコンテンツのリード文として有効です。
このパターンを使用する際には、勘違い→理由→解決策という順序を崩さないように注意しましょう。
リード文作成でよくある質問
- リード文は何文字くらいが理想?
-
どのコンテンツを作るかにもよりますが、SEOコラムなら250〜400字、ホワイトペーパーやレポートなら400〜500字が妥当でしょう。
もし情報量が多い場合は「導入」と「本編への誘導」の2段に分けて、読みやすさを意識すると効果的です。 - ホワイトペーパーとコラムで書き分けは必要?
-
はい、目的に応じてトーンを変えることが重要です。ホワイトペーパーは信頼性や根拠を重視するため、やや硬めの導入が向いています。一方でコラムは共感や軽快さを大切にし、読者が「自分ごと」として読み進めやすいトーンにすると効果的です。
- ライティングは外注しても品質は担保できる?
-
BtoB領域では、専門性とヒアリング力が品質を大きく左右します。制作会社や専門ライターに依頼する場合は、過去の実績や制作プロセスを確認し、特に「構成案の精度」が高いかどうかを判断基準にすると安心です。
BtoBのコンテンツマーケティングはリードレにお任せ!
今回は、リード文をスラスラ書き進めるために覚えておいていただきたい3つのパターンを紹介しました。
▼タイトルの付け方については、下記の記事もぜひご一読ください。
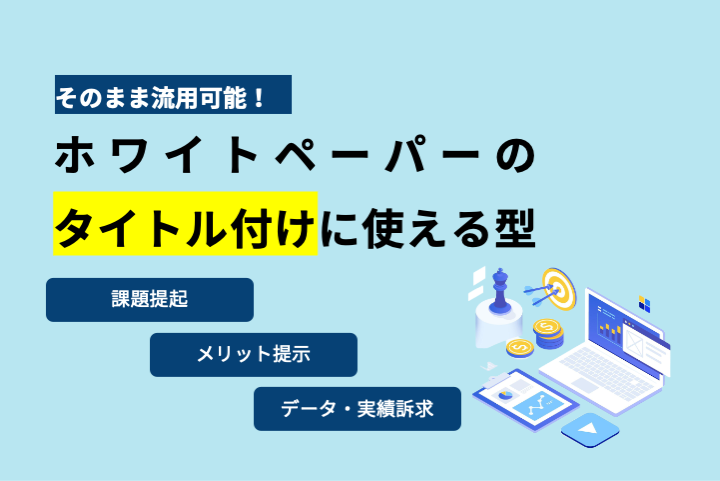
本記事を作成した株式会社リードレでは、これまで数多くのBtoB企業様のコンテンツマーケティングをご支援してきました。
その知見をもとに、最上流のマーケティング戦略策定から、コンテンツ制作の伴走支援まで、ワンストップでご依頼いただけます。
コンテンツ制作も含めて、「マーケティングを全て丸投げしたい!」というBtoB企業の方は、ぜひ下記のサービスガイドをご一読ください。