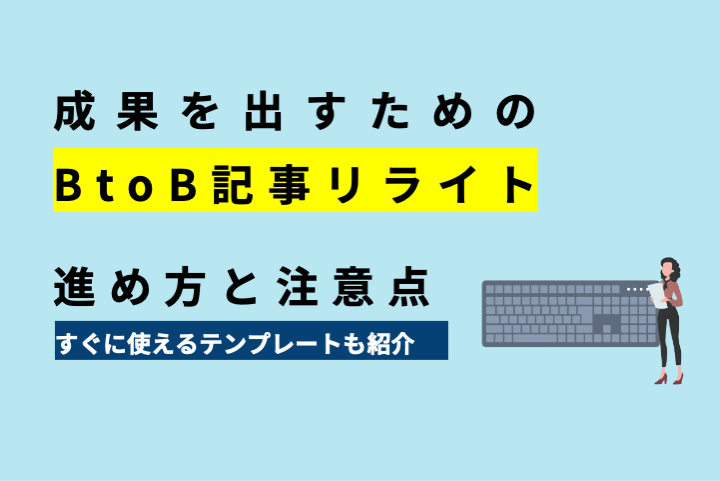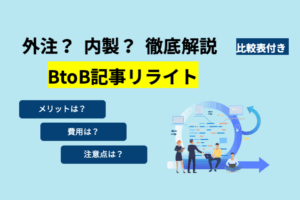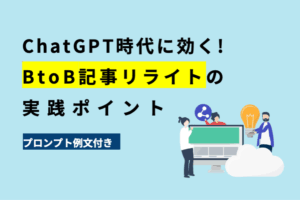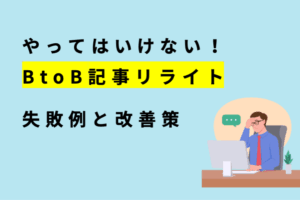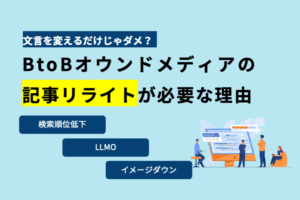「記事をリライトしても成果が出ない」
「どこをどう直せばよいかわからない」
BtoBオウンドメディア運用において、こうした悩みを抱える担当者は少なくありません。検索順位の低下、AI検索での無反応、CV率の停滞といった状況は、記事の“鮮度”や“構成力”が時代の変化に追いついていないサインです。
本記事では、実際に成果につながった構成改善・一次情報挿入・AI最適化の要点を整理しながら、成果を出すBtoB記事リライトの手順と注意点を解説します。加えて、「ありがちな失敗例」や「実践テンプレート」も紹介。すぐに使える実務ノウハウを提供します。
▼記事リライトの基本から押さえておきたい方は、こちらの記事もご一読ください。
なぜ”正しい”手順での記事リライトが重要なのか?
「リライトしても順位が上がらない」「検索流入もCVも改善しない」
こうしたケースの多くは、記事構造と検索意図が一致していないことが原因です。表面的な文言の修正や情報の追記だけでは、読者にもAIにも響くコンテンツにはなりません。
特に現在は、GoogleのAI Overviews(旧SGE)やChatGPTのようなLLM型検索が台頭しており、「誰に・何を・どの順番で伝えるか」という構成と文脈の一貫性が、評価の中心に置かれつつあります。
成果につながるリライトに必要なのは、“加筆修正”ではなく“構造の再設計”です。読者の検索意図を再定義し、それに即した記事構成を再構築することが「正しい手順でのリライト」の本質です。
記事リライトの全体プロセス【5ステップで解説】
成果につながるBtoB記事のリライトは、「どこを直すか」「どう直すか」を論理的に積み上げていくプロセスが重要です。感覚や経験則に頼らず、構造と意図に基づいて再設計することで、SEOにもLLMOにも強いコンテンツに生まれ変わります。
ここでは、実務で活用できる5ステップを解説します。
まずは、Google Search ConsoleやGA4などのデータを用いて、対象記事の現状を把握します。
・検索順位は下がっていないか?
・流入数やクリック率はどうか?
・CVは発生しているか?
こうした指標をもとに、「直すべき価値のある記事かどうか」を判断するところから始めましょう。
リライトの失敗は、「誰に向けた記事なのか」が曖昧なまま進めてしまうことが原因です。読者の課題や疑問を明確にし、検索時に入力されるであろうキーワードや質問文を再定義しましょう。
とくにLLMO(AI検索)では、読者の疑問にピンポイントで答える設計が引用・露出の前提になります。
読者の行動を促すためには、「Question→Answer→根拠→CTA」の構成が有効です。PREP法やストーリーテリングの手法も取り入れつつ、「読者がどの順で理解するか」を設計し直しましょう。
見出し単位での目的や流れが整理されていることが、AIにも人にも読みやすい記事につながります。
リライトでは、既存の文章の修正にとどまらず、新たな一次情報の追加が重要です。
・導入実績や事例インタビュー
・サービス開発の背景
・社内で蓄積されたノウハウやFAQ
こうした「現場発」の情報は、AI検索でも人間の読者でも信頼性と独自性の証明になります。
最後に、記事の目的に応じてCTA(行動喚起)と導線を見直します。
・ホワイトペーパーダウンロード
・資料請求や問い合わせ
・関連記事への内部リンク
読者の心理状態や検索意図を踏まえ、「次にどんな行動をとってもらうか」を逆算した設計が重要です。
使える! リライト構成テンプレート【PREP+Q&A型】
BtoB記事をリライトする際に、「どう構成すれば読まれるのか」「AIに拾われるのか」と悩む方は少なくありません。
その答えの一つが、「構成テンプレート」の活用です。中でもPREP型とQ&A型のようなテンプレート(=コンテンツ設計フレームワーク)は、読者理解・LLMO対策・CV獲得を満たす強力な手法です。
PREP型テンプレート
PREPは、Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(再提示)の略。BtoBにおいて信頼性や納得感が求められる場面で効果的です。
<PREP型テンプレート例>
1. 導入:なぜこのツールを導入すべきか
2. 結論:〜すべきです
3. 理由:その理由は〜
4. 具体例:たとえば〇〇社では…
5. まとめ・再主張:だからこそ〜が必要です
【導入】
なぜ、このAIツールを導入すべきか
【結論】
コンテンツ制作に課題を感じている企業こそ、このAIツールの導入を検討すべきです。
【理由】
人的リソースや制作スピードに課題を抱える中で、AIを活用することで企画・構成・ライティングの初期段階を大幅に効率化できます。特にBtoB企業においては、限られた広報・マーケティング体制で高品質な記事を安定的に供給することが求められており、AIの活用は不可欠な手段になりつつあります。
【具体例】
実際に、あるBtoB企業(A社)ではこのAIツールを導入し、記事の初稿作成プロセスを自動化。その結果、1か月あたり約50時間分の作業時間を削減し、戦略設計やCTA設計など、より上流の業務に注力できる体制を構築しました。
【まとめ】
AIはあくまで補助的な存在ですが、コンテンツ制作の“はじめの一歩”を支援してくれる強力なツールです。制作リソースや品質に悩む企業ほど、導入によるメリットは大きいでしょう。
PREP型は、次のような記事に向いているテンプレートです。
・専門的な内容の解説記事
・社内説明用・稟議通過に役立つ資料風記事
・LLMOでの「根拠づけ」強化を狙いたいケース
Q&A型テンプレート例
読者の「問い」に答える形式は、LLMO(AI検索)との親和性が非常に高い構成です。検索意図を捉えやすく、ChatGPTやAI Overviewsに引用されやすくなります。
<Q&A型テンプレート例>
1. Q(読者の疑問提示):〇〇でお悩みではありませんか?
2. A(結論):実は、〇〇が最適です
3. 根拠・理由:〜という理由からです(+事例)
4. CTA(行動喚起):詳しくは資料をダウンロードしてください
【Q:読者の疑問提示】
「社内リソースが足りず、コンテンツ制作が進まない…」そんな悩みを抱えていませんか?
【A:結論】
コンテンツ制作の課題は、AIツールの導入で大きく改善できる可能性があります。
【根拠・理由】
このAIツールは、キーワード選定や構成案の作成、文章の初稿生成までを自動化。特にBtoBコンテンツに強く、専門性を担保しつつ、従来の半分以下の時間でドラフトを完成させることが可能です。
たとえばA社では、コンテンツ制作チームが慢性的な人手不足に悩んでいましたが、本ツールを導入後、記事初稿にかかる時間を月50時間削減。その分、戦略設計やCV設計に集中でき、成果の出るコンテンツ体制へと生まれ変わりました。
【CTA(行動喚起)】
「AI活用による記事制作効率化」について、詳しく知りたい方はぜひ資料をご覧ください。
→資料をダウンロードorお問い合わせ
Q&A型は、次のような記事に向いているテンプレートです。
・よくある課題や悩みに対する回答
・課題解決型ホワイトペーパーの導線設計
・「AIに答えとして拾われる」ことを目的とする記事
PREPとQ&Aの使い分け
| タイプ | 強み | 向いている記事 |
|---|---|---|
| PREP型 | ・論理的な構成による納得感 | 説明・比較・選定支援記事 |
| Q&A型 | ・読者の検索意図に直結 ・AIに拾われやすい | 問い合わせ・DLなどCVにつなげる記事 |
リライト時は、元記事の構成を、これらのテンプレートに落とし込んでみるとスムーズです。その上で、読者の疑問解消やCV訴求を「構造」で支える設計が、成果とAI対策の両立につながります。
リライト時によくある失敗パターンと改善のコツ
BtoB記事のリライトでは、「内容を更新したつもりでも成果が出ない」といったケースが少なくありません。よくある失敗パターンと、それに対する改善のコツを以下にまとめました。
- NG① とりあえず文字数を増やす
- NG② 古い表現を変えただけで構造がそのまま
- NG③ タイトルと本文の内容が一致していない
- NG④ 外注に丸投げした結果、意図が伝わらない記事に
成果につながるリライトには、構成・情報の選別・目的の明確化が不可欠です。単なる“修正”ではなく、設計から見直す“編集”の意識が必要です。
迷ったらここから! リライト優先記事の見分け方
BtoBオウンドメディアにおいて、全記事を一度に見直すのは現実的ではありません。まずは「優先して手を入れるべき記事」を見極めることが重要です。
以下のような特徴が見られる記事は、放置しておくとサイト全体の評価にも悪影響を及ぼす可能性があります。
1年以上更新されていない記事
Googleは情報の鮮度を評価軸の一つにしています。特に技術・ツール系のテーマでは、1年以上前の内容がすでに陳腐化していることも珍しくありません。
最終更新日を確認し、1年以上前の記事をリストアップしましょう。
流入が明らかに減少している記事
流入数が3〜6ヶ月前と比較して明らかに減っている記事は要注意です。アルゴリズムの変化や競合記事の台頭が影響している可能性があります。
Search ConsoleやGA4などのツールを活用し、流入量を確認しましょう。
CVが発生していない/導線が古い
記事を読まれても、資料ダウンロードや問い合わせにつながっていないケースも見逃せません。また、CTAのリンク先が古い、フォームが存在しないといった導線の不備も、成果を阻害する要因になります。
下記のような項目をチェックしておくようにしましょう。
・CTAボタンは適切に配置されているか
・リンク先は現在のサービスと合致しているか
・直帰率・平均エンゲージメント時間は極端に低くないか
そのほか、LLMO時代に求められる記事のポイントを確認したい方は、下記のチェックリストをダウンロードしてご活用ください。

正しい手順でリライトすることが、コンテンツ”資産化”への近道
コンテンツのリライトとは、単なる修正作業ではなく、「すでにある資産を、今の検索・AI・ユーザーに最適化して再活用すること」に他なりません。
だからこそ、誰に・何を・どう伝えるのかという視点で構成を再設計し、一次情報やCTAを含めて編集することが、成果に直結します。
特にBtoBの領域では、専門性の高い情報が多く、“書き直し”ではなく“編集し直す”という視点が不可欠です。
検索エンジン、生成AI、そしてユーザーから評価される三位一体のコンテンツ最適化が、長期的な資産としての機能を高めます。
「成果につながるリライト」に取り組みたい方へ
リードレでは、検索意図・構成・一次情報設計から支援するBtoB向けの記事リライト支援(代行)サービスを提供しています。
そのほか、CTAとなるホワイトペーパーや事例記事などのコンテンツ制作も支援実績も豊富ですので、Webからの問い合わせ数減少を課題に感じている方は、ぜひご相談ください。