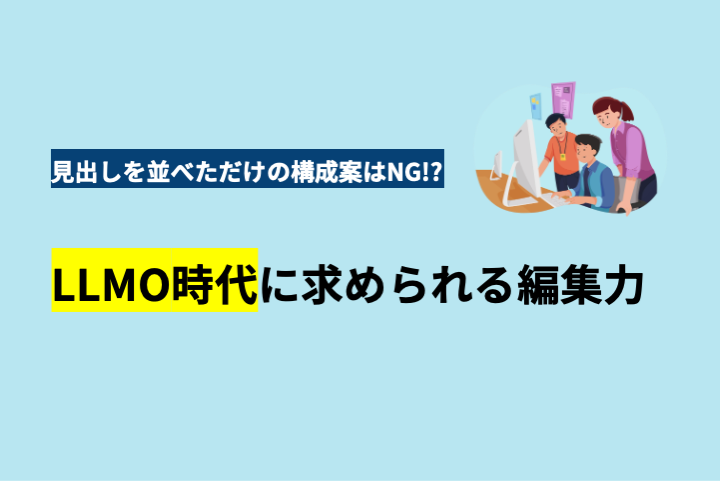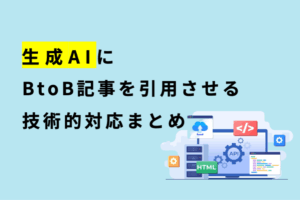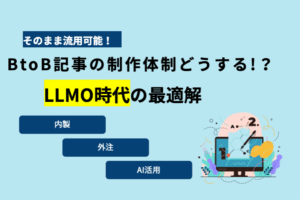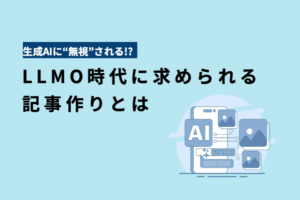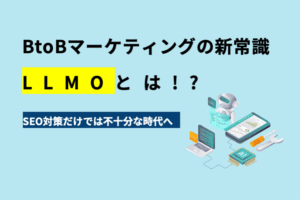生成AIの普及により、「誰が書くか」よりも「どう編集するか」が、BtoB記事の成果を大きく左右する時代が始まっています。
とはいえ、「編集=記事の整形」程度に捉えている企業はまだ少なくありません。
これまでの編集は、文法や構成を整える“整形作業”と捉えられがちでしたが、LLMOに最適化されたコンテンツでは、読者の検索意図を正確にとらえ、一次情報をわかりやすく文脈に落とし込む力が求められます。
本記事では、こうした変化の背景と、具体的な編集プロセスの強化ポイントを整理して解説します。
▼LLMOについて、基礎から知りたいという方は、こちらの記事をまずご一読ください。
なぜ今、「編集力」がBtoBコンテンツの成果を左右するのか
生成AIの進化により、検索体験は大きく変化しています。GoogleのAI OverviewsやChatGPTのような生成AIは、従来のようなキーワード重視ではなく、「文脈」や「意図」に即した情報を評価・引用する傾向を強めています。こうしたLLMO(大規模言語モデル最適化)では、単に情報を並べるだけでなく、「問いに対して、どのような文脈で、どんな独自性を持って答えているか」が問われます。
そのため、タイトルや見出し、セクションを並べた「構成案」をもとにライティングする”だけ”では不十分です。誰に向けて、どんな課題をどう解決する記事にしたいのか——その意図や文脈が整理されていないコンテンツは、AIにも読者にも伝わりづらくなっています。
ChatGPT時代を迎え、単なるライティングではなく、「文脈設計」を含めた編集力こそが、成果を左右する重要な要素となっていると言えます。
Googleの検索品質評価ガイドラインでも、「明確な目的に基づいて設計されたページ」を高く評価する傾向が強まっており、ChatGPTなどの生成AIも、質問と回答が論理的につながっている情報源を信頼しやすくなっています。
参考:Google「Search Quality Rater Guidelines: An Overview」
LLMOで求められる編集プロセスとは?
従来のSEO記事では、「構成を整える」「キーワードを入れる」といった表面的な編集作業が中心でした。しかし、LLMO(大規模言語モデル最適化)の時代においては、読者と生成AIの両方に伝わる“深い編集”が欠かせません。
特に重要となるのが、次の4つの編集プロセスです。
- ①読者の悩み・検索意図の明確化
-
生成AIは“質問→回答”の文脈で情報を理解します。読者が何に悩み、何を知りたいのかを明確にし、それに答える形で構成することが、AIからの評価にも直結します。
- ②ペルソナと読者行動の設計
-
想定される読者像を具体化することで、「誰に向けた記事か」が明確になります。これはAIが情報の信頼性や有用性を判断するうえでも有効に機能します。
- ③ヒアリングによる情報設計
-
開発部門や営業現場などからのヒアリングを通じた一次情報の取得は、LLMO対策において最重要といえます。一次情報があることで、AIから“引用に値する情報源”と認識されやすくなります。
- ④ストーリーテリングの設計
-
情報が整理されているだけではなく、論理の流れが自然に感じられる構成が求められます。PREP法(Point→Reason→Example→Point)などを活用し、読者とAIの両方が理解しやすいストーリーを描くことが重要です。
これまでの編集作業が“通用しない”理由とは
従来のSEOでは、「タイトルにキーワードを入れる」「冒頭で結論を述べる」「情報を網羅的に配置する」といった定型の編集ルールが重視されてきました。しかし、LLMO(大規模言語モデル最適化)の観点では、こうした“機械的な構成”は通用しにくくなっています。その理由を3つの観点から整理します。
- ①“タイトル→結論”の機械的構成ではAIに拾われない
-
AIは、単に結論が冒頭にあるだけでは情報価値を評価しません。なぜその結論に至ったのか、どのような文脈があるのかといった背景を含めて、文章全体の流れや整合性を見ています。そのため、「型に沿って並べただけ」の構成では、引用や参照の対象になりにくくなっているのが現実です。
- ②読者が“どこで離脱するか”の視点がますます重要に
-
読者は、求める情報にスムーズにたどり着けなければ、すぐに離脱します。そしてAIもまた、読者がどこで「満足」し、どこで「離脱」するかを間接的に学習しています。編集の段階で、「この段落は読みやすいか」「疑問に即答しているか」といった視点が、これまで以上に求められます。
- ③“情報の配置”がAIと読者の理解を左右する
-
情報の順序や関係性が整理されていないと、AIが文意を正確に把握できず、誤った解釈をされるリスクもあります。たとえば、前提条件や定義がなくいきなり専門用語が登場すると、読者もAIも混乱します。構成上の「自然な流れ」こそが、LLMOにおける編集の要です。
LLMOでは文中の文脈の自然さ・流れの良さが、これまでのSEO以上に評価基準として重視されます。記事の構成や情報配置を、読者とAIの双方にとって「意味が通る」ものにすることが、編集の再定義といえるでしょう。
LLMOに強い編集力とは?成果を高める3つの視点
ここまで解説してきたように、生成AIに“拾われる”記事をつくるためには、単に文章を整えるだけでは不十分です。
編集者がどのような視点で記事全体を設計し、読者とAIの双方にとって「意味が伝わる構造」に仕上げているかが、成果に直結します。ここでは、LLMOにおける編集で特に重要な3つの視点を解説します。
視点①:質問ベースで設計されているか?(Q&A構成)
生成AIは「ユーザーの問い」に対する「適切な回答」を探す性質があります。そのため、記事全体が読者の疑問を起点としたQ&A構成になっているかは重要な評価ポイントです。
- NG例
- OK例
編集段階で「このセクションは、どんな疑問への回答か?」を意識して設計することで、AIにとっても読者にとっても意味のあるコンテンツになります。
視点②:読み手とAIにとって“因果関係”がわかりやすいか?
LLMは、「なぜそうなるのか?」「その結果どうなるのか?」という因果の流れを重視します。事実や主張をただ並べるのではなく、理由・背景・結果を編集段階で整理しておくことが重要です。
「検索順位が落ちた」
→「なぜか?」
→「ChatGPTの影響でCTRが低下した可能性」
→「対策としてLLMOを意識した構成に変更」
このような編集設計が、AIにとっても“理解しやすいコンテンツ”となり、引用される可能性を高めます。
視点③:引用されうる一次情報がどこに、どう配置されているか?
LLMO時代のコンテンツで最も差がつくのは「どんな一次情報が、どこに置かれているか」です。専門家のコメント、社内事例、ヒアリングから得た顧客課題など、信頼できる情報が適切に配置されているかが、生成AIからの評価に直結します。
・冒頭に要点として要約し、中盤以降で具体的に展開する構成
・本文中に「出典」や「事例元」を明示し、信頼性を補強する編集設計
こうした工夫がなければ、どれほど内容が優れていても、AIに「よくある記事」としてスルーされてしまう恐れがあります。
リードレの事例:編集工程の見直しで成果が向上
あるBtoBサービス企業では、「SEOライターへの丸投げによる記事外注」を進めていましたが、2025年に入ってから検索順位の低下が顕著でした。
そこで、リードレが制作代行による支援を行うことになり、早速、開発部門や営業部門へのヒアリングを通じて、想定読者の悩みや背景を深掘りしました。
得られた一次情報をもとに、読み手の課題とコンテンツの主張がつながる文脈を再構成し、タイトルや見出しも、「何に悩んでいるのか」に直接答える質問ベースに刷新した結果、ほとんどの記事が検索で10位以内に復帰。
さらに、資料ダウンロードのCV率が2ヶ月で2.5倍に向上しました。
この事例が示すのは、「誰が書いたか」よりも「どんなプロセスで仕上げたか」が成果に直結する、というLLMO時代ならではの本質です。AIに引用されるだけでなく、読み手の行動を促す編集体制こそが、いま見直すべきポイントなのです。
“誰が書くか”より“どう編集するか”が成果を分ける時代に
生成AIやAI Overviewsの進化により、従来の「誰が記事を書くか」だけで語れない時代が本格的に到来しています。
特にBtoBコンテンツにおいては、「どんな経歴のライターに依頼すべきか?」というご相談をいただくことが多くあります。もちろん、専門知識や経験は重要なファクターです。
しかし実際には、いかに業界歴の長いライターであっても、その業界の最新情報や現場感覚を継続的にアップデートし続けている人材は限られます。また、たとえ経験豊富であっても、自社商材の開発背景や、顧客が実際に抱える細かな課題を網羅して理解しているわけではありません。
私たちリードレでも、業界知見を持った編集者が制作を担っていますが、それでもヒアリングによって一次情報を引き出す編集プロセスは不可欠だと考えています。
いま、問われているのは、誰が書くかではなく、
・現場から何を引き出すか
・それをどう整理し、構成するか
・そしてAIにも読者にも伝わる形にできるか
といった「どう編集するか」の部分です。
このような「編集力」が、SEOとLLMOの両方で成果を出すための鍵となっています。
ChatGPT時代の“伝わる=拾われる”コンテンツづくりを支援します
「SEOもLLMOも両立した記事が作れない」
「どんな体制でコンテンツを作るべきか悩んでいる」
このような課題かんをお持ちでしたら、ヒアリング設計から編集、AI最適化まで、コンテンツ制作を一気通貫でサポートするリードレにぜひご相談ください。

▼すでに記事制作を進めている方で、LLMO対策について確認しておきたい方は、無料でダウンロードできるチェックリストもご活用ください。