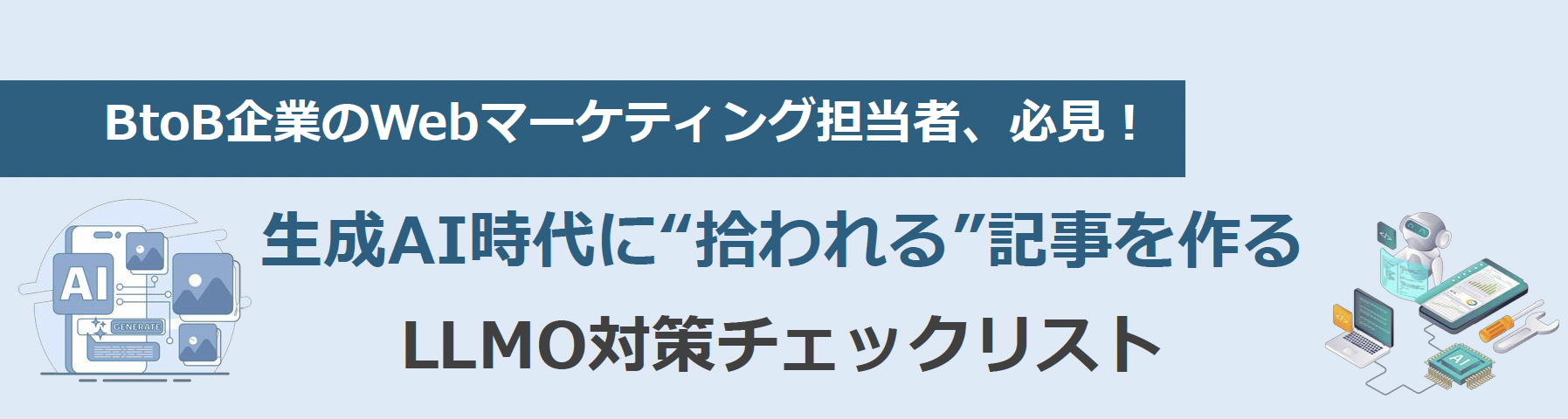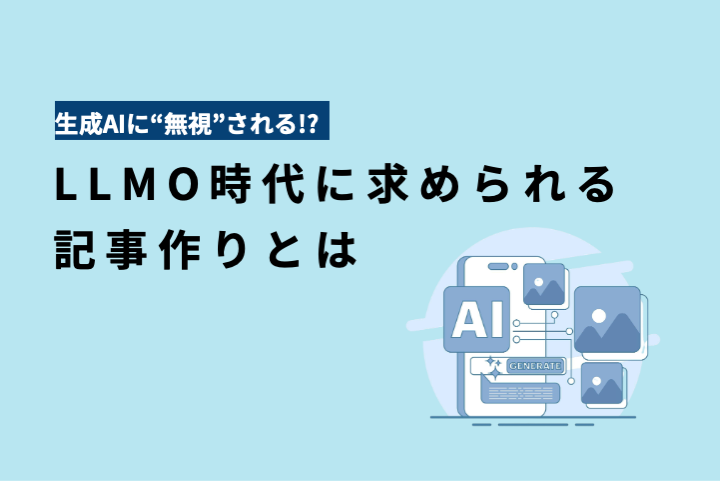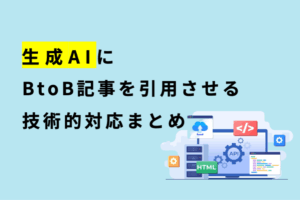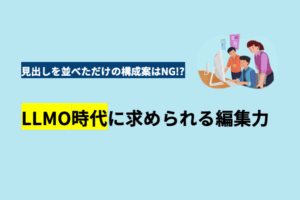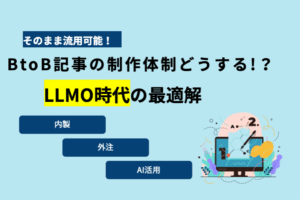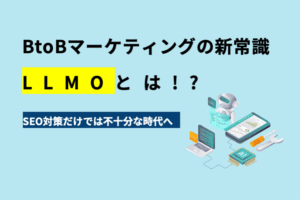「以前はSEOで上位を取れていたのに、最近なぜか記事が読まれなくなってきた」
そんな変化を感じていませんか?
この背景には、検索エンジンを通じた情報収集から、ChatGPTなど生成AIによる“質問ベースの検索”へのシフトがあります。これに伴い、従来のSEO対策では通用しなくなってきたのが現実です。
本記事では、「キーワードを詰め込んだだけの量産記事」がなぜAIに無視されるのか、そしてLLMO(ローカル・ランゲージ・モデル最適化)の観点から見た“通用しない記事”の特徴を、具体例を交えて解説します。
自社メディアを見直すきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。
また、LLMOの概要を知りたいという方は、まずこちらの記事をご一読ください。
従来のSEOで「評価されていた」記事の特徴とは?
生成AIが普及する以前、SEO対策において重要とされていたのは、「検索エンジンに最適化された構造」と「キーワードの使い方」でした。ここでは、かつて検索上位を獲得しやすかったSEO記事の典型的な特徴を紹介します。
キーワードを過剰に挿入したタイトル・見出し
Googleがコンテンツの意味を「語彙単位」で評価していた頃は、特定の検索キーワードをタイトル・見出し・本文に繰り返し入れることで、検索順位を押し上げることが可能でした。
たとえば、「BtoB マーケティング メリットとは?成功事例とBtoBマーケティング戦略も解説」といったタイトルは、キーワードを二重に入れたことで不自然さが目立ちます。
これは、Googleが検索品質評価の精度を上げる前、いわゆる「キーワード出現率」に一定の評価基準があった時代の名残です。
2022年以降のGoogleのアルゴリズム(Helpful Content Updateなど)では、「検索意図を満たす有益な情報が提供されているか」が重視されるようになり、キーワード過多な記事はむしろ評価を下げられる傾向にあります。
出典:Google検索セントラルブログ「2022 年 8 月の Google の有用なコンテンツの更新についてクリエイターが知っておくべきこと」
網羅性を重視した「まとめ記事」構成
「◯◯とは?」「◯◯のメリット・デメリット」「導入事例」「選び方」など、とにかく幅広い情報を詰め込んだ“まとめ記事”も、かつてはSEO評価の対象でした。ユーザーの多様な検索意図をカバーできる点が評価されたからです。
しかし、ChatGPTなどの生成AIにおける回答最適化では、網羅性よりも“文脈的に焦点が合った情報”の方が参照されやすくなっています。つまり、「何でもかんでもまとめた記事」では、生成AIの回答材料として選ばれにくいということです。
被リンクや文字数の多さ
外部サイトからの被リンク(Backlink)や、3,000文字を越えるの長文コンテンツも、「権威性」や「コンテンツの厚み」を測る指標として、かつては重要視されていました。
もちろん今でも被リンクの重要性はゼロではありませんが、Googleは質の低い大量コンテンツやスパム的リンク手法を明確に排除し始めています。
「検索ランキングを操作することを主な目的として、サイトへのリンクやサイトからのリンクを作成する行為」
リンクスパムの例:過剰な相互リンク(「リンクする代わりにリンクしてもらう」)や、相互リンクのみを目的としてパートナー ページを作成する
出典:Google 検索セントラル「Google のスパム対策システムに関するドキュメント」
そのため、形式的な「構造の最適化」や「数値的なボリューム」だけで評価される時代は終わりつつあるといえます。
こうした背景から、SEOにおいて“通用していた”戦術が、LLMO(ローカル・ランゲージ・モデル最適化)の時代にはむしろ「通用しない施策」へと変わりつつあるのです。
LLMO時代に“通用しない”記事の5つの特徴
従来のSEOで通用していた手法が、LLMO(ローカル・ランゲージ・モデル最適化)の時代にはかえってマイナスに作用することがあります。ここでは、生成AIに評価・引用されにくい「5つの典型的なNGパターン」を紹介します。
- ①キーワードの羅列だけで構成された文章
-
AIは自然な文脈で意味を理解するため、単語の集合は評価されにくい
- ②明確な主張や一次情報がない
-
オリジナリティや信頼性がなく、AIに引用されにくくなる
- ③読者の疑問に答えていない
-
LLMは「質問→回答」形式で情報を探すため、FAQ構成でない記事はスルーされやすい
- ④結論が曖昧/構成がわかりにくい
-
文脈が希薄だとAIが文意を正しく汲み取りづらい
- ⑤表面的なまとめ・自社の視点がない
-
「他サイトと差別化できない記事」として埋もれるリスクがある
実例で検証|“通用しない記事”と“AIに拾われる記事”の違い
「記事を書いているのに、なぜかAIに引用されない」と感じている場合、その原因は“記事の中身”にあるかもしれません。
ここでは、生成AI(LLM)に拾われにくいNG記事と、拾われやすいOK記事の具体例を比較しながら、どこに違いがあるのかを検証していきます。
BtoBマーケティングとは?
BtoBマーケティングとは、企業間取引におけるマーケティング活動を指します。代表的な施策には、展示会出展やDM、Web広告、SEOなどが含まれます。本記事では、BtoBマーケティングの主な施策や活用ツールをご紹介します。
このような記事は一見まとまっているように見えますが、情報が汎用的すぎるため、生成AIにとっては既に「学習済み」であり、あえて引用する価値がないと判断されやすいのです。
AI活用で“成果が出ない”BtoBマーケ施策、現場の本音とは?
近年、BtoBマーケティングにおいてもAIツールの導入が進んでいます。その一方、リード獲得や受注に繋がらないという声をいただく機会がすすなくありません。とくに、リードレが支援しているクライアントの現場からは「AIで制作したコンテンツは他社と似通い、差別化が難しい」という課題が挙がっています。
これは、コンテンツ制作体制が「費用対制作量」ばかりに目を向けられており、質を高めるための工夫や独自視点が不足していることに主な原因があると考えられます。
生成AIは、学習済みの一般情報を繰り返し引用するよりも、「その企業で実際に起きた出来事」や「社名・商品名が明記されたエピソード」など、具体的かつ信頼性の高い情報を優先する傾向があります。
これは、AIが回答の根拠として固有名詞(例:企業名・製品名)と実体験(例:導入経緯・現場課題)を組み合わせた情報を「出典価値のあるコンテンツ」として判断しやすいためです。
また、こうした構成はFAQ型であり、「◯◯に課題を感じているが、なぜうまくいかないのか?」といった質問ベースの検索にもマッチしやすい点も評価されます。
| 比較軸 | NG記事の特徴 | OK記事の特徴 |
|---|---|---|
| 情報の独自性 | 汎用的な定義や網羅情報 | 実体験・現場の課題感を含む |
| 引用の必要性 | LLMが既に学習済み | 新たな視点・価値がある |
| 質問対応力 | 読者の疑問に答えていない | 疑問→課題→原因の文脈がある |
| E-E-A-T評価 | 低評価対象(独自性欠如) | 経験・専門性・信頼性を反映 |
LLMOに強い記事を生み出すための社内連携と制作体制
LLMO時代において、“AIに拾われる”強いコンテンツをつくるためには、ライターやマーケティング担当者だけで完結する制作体制では不十分です。記事の信頼性・独自性を支える一次情報は、たいてい現場にあるためです。
マーケティング担当者だけでは「情報の深さ」に限界がある
多くのBtoB企業では、オウンドメディアやホワイトペーパー制作をマーケティング部門が主導しています。しかし、開発や営業、カスタマーサクセスなど、顧客と日々向き合っている現場の部門にこそ、一次情報の“宝庫”があります。
・「なぜこのサービスを開発したのか」という背景
・「導入前後で顧客にどんな変化が起きたのか」というリアルな事例
・「失注理由にどう向き合っているか」という営業の知見 など
こうした情報は、外部のライターがオンライン上の調査だけで書けるものではなく、現場からのヒアリングを通じて初めて引き出せる要素です。
質の高い記事には「インタビュー」が必須
効果的な記事制作には、以下のようなインタビュー・ヒアリングのプロセスが欠かせません。
マーケティング担当者が担当
外部のディレクターやライターが担当
社内外のライターが担当
このようなプロセスを経ることで、コンテンツに現場の視点・リアルな課題感・説得力のある因果関係が加わり、AIにも“意味ある情報源”として認識されやすくなります。
「情報提供の文化」を社内に根づかせる
LLMOに強いコンテンツを継続的に生み出すためには、コンテンツ制作にあたり「現場を巻き込む文化」を定着させることも重要です。
・社内で「オウンドメディア=発信の場」としての共通認識を持つ
・インタビュー協力を評価・感謝する仕組みを整える
・成果(例:AIに引用された/リードにつながった)を共有する
こうした工夫により、マーケティング部門が孤立せず、全社的にマーケティング部門を支える体制が築かれていきます。
これからのBtoBマーケティングに不可欠な「コンテンツの質」とは?
ここまでの解説をまとめると、今後は以下のような視点を持った記事制作が求められます。
・読者の疑問に答える「質問起点」の構成
・主張や一次情報に裏打ちされたオリジナリティ
・文脈と因果関係が明確な論理的な文章
・自社の知見や現場のリアルを反映した説得力ある内容
AI時代でも埋もれない記事を作るなら、実績豊富なリードレへ
リードレでは、BtoB企業のコンテンツ制作において、クライアントへのヒアリングを通じ、一次情報を言語化する制作代行を多数手がけてきました。
「社内にナレッジはあるけど、記事に落とし込めていない」
「AIに拾われる記事構成の考え方がわからない」
――そんなお悩みがある方は、無料で現状記事の分析も可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。

現状分析に役立つ、下記のチェックリストもぜひご活用ください。