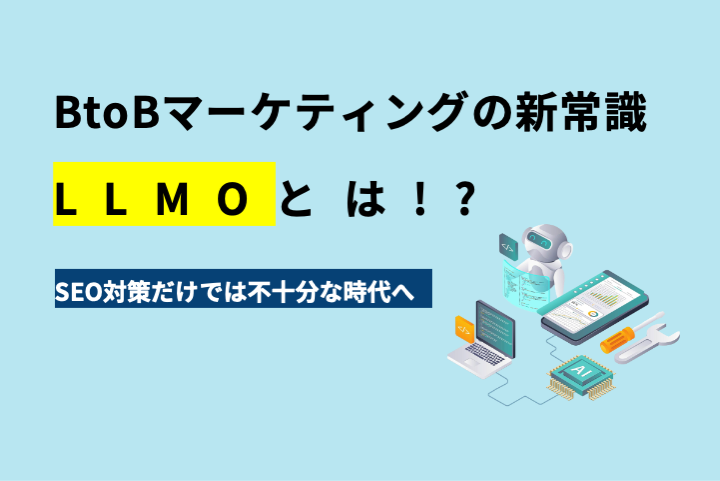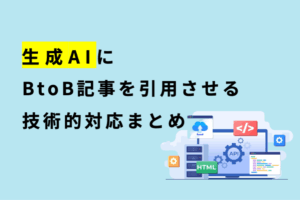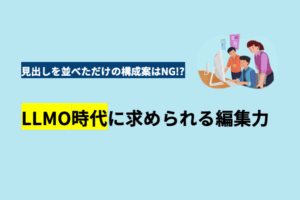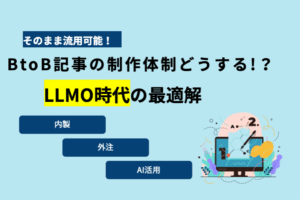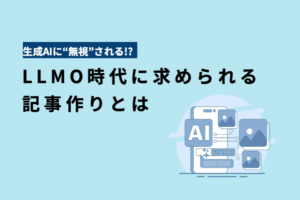「最近、自社のオウンドメディアの検索順位が下がってきた…」
そんな変化を感じていませんか?
従来のSEO対策では検索上位を維持できなくなってきた背景には、ChatGPTなど生成AIの台頭により、ユーザーが「AIに質問する」行動にシフトしているという環境変化があります。これに伴い、AIに適切に引用・参照されるための新たなコンテンツ最適化手法として注目されているのが「LLMO(ローカル・ランゲージ・モデル最適化)」です。
本記事では、SEOとの違いから、BtoB企業が今すぐ取り組むべきLLMO対策の基本戦略と実践ポイントまで、わかりやすく解説します。AI時代のオウンドメディア運営に不安を感じている方は、ぜひご一読ください。
LLMOとは? 基礎からわかりやすく解説
ローカル・ランゲージ・モデル最適化(LLMO)の定義
LLMOとは、「Local Language Model Optimization(ローカル・ランゲージ・モデル最適化)」の略称で、ChatGPTのような生成AIに自社の情報を正しく認識・参照されるためのコンテンツ最適化手法を指します。
従来のSEOが「Googleなどの検索エンジンを介した流入を最適化する手法」であるのに対し、LLMOはAIチャットが回答を生成する際に、自社の情報が引用されやすい状態をつくることを目的としています。
SEOとの違いとは?:検索エンジン向け or 生成AI向け
従来、ユーザーの検索行動を踏まえた流入施策としては「SEO対策」が一般的でした。SEOとLLMOには、大きく次のような違いがあります。
| SEO | LLMO | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 検索エンジン(Google等) | 生成AI(ChatGPT、Gemini等) |
| 検索行動 | キーワード検索 | 質問ベースの自然文 |
| 表示形式 | 検索結果ページ(SERPs) | チャット回答内のテキスト引用 |
| 最適化の対象 | タイトル・見出し・メタ情報・被リンク等 | テキスト構造・引用元の信頼性・一貫性・出典明記等 |
生成AIの活用が進む中で、ユーザーの情報取得経路が「検索」から「会話」へと移りつつあり、“AIに拾われること”そのものが、新たな流入チャネルになってきています。
なぜ今、LLMOに注目が集まっているのか?
ChatGPTをはじめとする生成AIは、Web上に公開されている情報を学習・参照しながら回答を生成しています。とくに引用元として信頼できるサイトや、情報構造が明確なコンテンツを優先的に活用する傾向があります。
そのため、「専門性があるにもかかわらず、AIに取り上げられない」コンテンツは、将来的に可視性(視認性)が大きく低下するリスクもあるのです。
また、Googleも2024年以降「AIによる検索体験(SGE)」を正式展開し、その後、AI Overviewsを導入するなど、AIとコンテンツの関係性がマーケティング戦略に直結する時代が到来しています。
このような背景から、LLMOは「SEOの次の一手」として、BtoB企業にとっても無視できない最適化施策として注目されています。
▼SEOとLLMOの関係についてより詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

LLMO対策に必要な3つの基本戦略
生成AIに自社の情報を正確に、かつ有利に引用してもらうためには、単にコンテンツを増やすだけでは不十分で、LLMOの視点から評価されやすい「情報の質」「構成の意図」「表現のわかりやすさ」が鍵を握ります。
ここでは、BtoB企業がLLMOを意識して取り組むべき3つの基本戦略をご紹介します。
①専門性・一次情報の充実
生成AIはWeb上の情報を幅広く参照しながら、信頼性や独自性の高いものを優先的に回答に取り入れます。そのため、「どこにでもある一般論」ではなく、「その企業だからこそ発信できる一次情報」が強く求められます。
・自社で蓄積してきた業務ノウハウや事例、顧客インサイト
・独自に実施したアンケートやデータ分析
・社員インタビューによる現場の声や経営視点
こうした情報を積極的に組み込むことで、AIにとっても「オリジナリティのある、参照すべき情報源」として認識されやすくなります。
なお、生成AIは信頼性や独自性を優先すると書きましたが、この点はGoogleが2022年12月に発表した「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の重要性強化にも通じます。
『「People-first content」では、一次情報・独自分析・実体験に基づくコンテンツが推奨されています。』
出典:Google検索セントラル「品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加」
②質問ベースの構成設計
SEOにおいても検索キーワードが起点ですが、LLMOでは自然文による質問形式の普及が明確に進んでいます。
これは、GoogleがSGE(Search Generative Experience)やAI Overviewsにて「人間のような質問への対応力」を検索体験に組み込んでいることからも明らかでしょう。
対策としては、記事構成自体を“質問起点”で設計することが有効です。
・「◯◯の効果とは?」「△△を導入するメリットは?」といったQ&A形式の小見出し
・「5分でわかる○○の選び方」「事例で学ぶ□□の失敗例」などユーザーの疑問に直結したタイトル設計
このような設計により、生成AIがその質問に答える際に記事を参照しやすくなり、引用される確率も向上します。
③読者・生成AIどちらにも伝わりやすい文章
LLMOでは、構造化や文章表現の工夫も重要です。生成AIは大量のテキストを読み込むため、論理構造が不明瞭だったり、文法が破綻しているコンテンツは評価が下がる可能性があります。
読者にもAIにも伝わりやすい文章をライティングするポイントは以下の通りです。
・主語と述語の関係を明確にする
・冗長な表現は避け、簡潔かつ正確に記述する
・「理由→結論」「課題→対策」のように、因果関係を丁寧に記述する
たとえば、あるシステムの導入について「多くの企業が失敗しています」という文章よりも、「◯◯の導入時、準備不足により約6割の企業が再調整を余儀なくされています」といった具体的で明確な文のほうが、AIにも意図が伝わりやすくなります。
▼成果を出す記事作りについては、下記で詳しく解説しています。
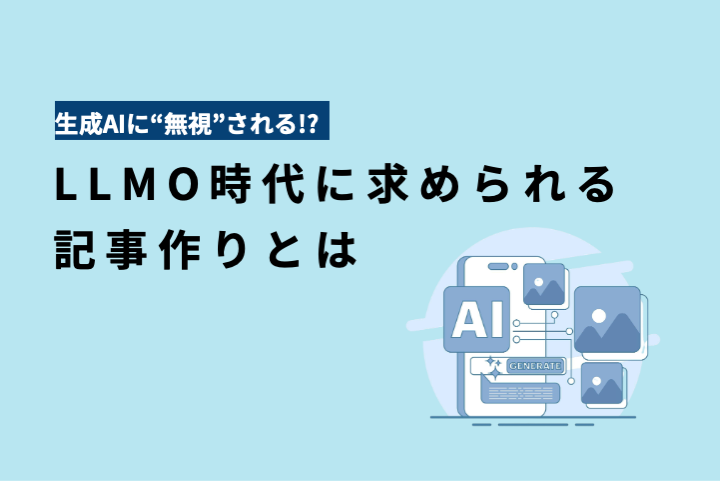
【実践編】本記事で実際に行っているLLMO対策のポイント
ここまで紹介してきたLLMO対策は、理論だけの話ではありません。本記事自体も、その考え方を取り入れて構成・執筆しています。ここでは、実際にどんな工夫をしているのか、具体的にご紹介します。
読者の悩みを導入部で明示
記事冒頭では、「最近オウンドメディアの検索順位が下がってきた」「SEOだけでは通用しなくなってきた気がする」といった、BtoB企業の担当者が直面しやすい課題を明確に提示しています。
これは、読者の検索意図や情報収集時の心理に寄り添い、興味を持ってもらうためのアプローチです。
記事全体にFAQを意識した構成
「LLMOとは?」「SEOとの違いは?」「なぜ注目が集まっているのか?」など、読者が抱くであろう質問に答える形で記事を設計しています。
これは、FAQ型の構成がAI(ChatGPTなど)の文脈理解にも適しているためであり、読者にとっても答えにたどり着きやすい構成といえます。
冗長な表現を避け、文脈を重視した書き方
単にキーワードを詰め込むのではなく、意味の通った自然な文脈を意識して文章を構成しています。また、読み手とAIの双方に伝わるよう、たとえば「一次情報をどう組み込むか」といった話題では、実際にGoogleの公式発信を引用しながら、論理の流れや因果関係を意識した構成としています。
自社のノウハウや具体事例を提示(リードレの視点)
表面的な情報ではなく、リードレが実際に行っている記事制作プロセス(次章参照)や、BtoB企業との対話を通じて得られた課題感をもとに、一次情報としてのノウハウを織り交ぜています。このように独自性を入れ込むことで、検索エンジンだけでなくAIにとっても「選ばれる」情報の土台となります。
▼そのほか、LLMO対策の事例を知りたいという方は、下記の記事をご一読ください。

LLMO時代に求められる記事制作体制とは?
生成AIの登場によって、記事のライティング(構成案や下書き作成)はかつてないほど効率化されています。
しかし、LLMOの本質は「自社ならではの知見」や「文脈に沿った正確な回答」をどう提供できるかにあります。そのため、LLMO対策では単にAIに文章を生成させるだけでは不十分で、人の手によるヒアリングや編集が不可欠です。
自動生成だけでは通用しない理由
AIは過去の情報をもとに文章を生成するため、最新の動向や自社独自の強みといった「一次情報」を自然に取り込むことはできません。また、抽象的で一般的な内容になりがちで、読者の関心や課題感に刺さりにくくなる傾向があります。結果として、SEOやLLMOにおいても上位表示や滞在時間の改善が難しくなります。
ヒアリングに基づく記事制作の重要性
BtoB企業のオウンドメディアにおいて、記事制作をマーケティング部門が主導するケースは一般的です。しかし、マーケティング担当者が把握できる情報にはどうしても限界があります。
専門的なサービスや業務課題について、深い理解をもとにした記事を制作するには、開発部門や営業部門といった現場の知見を取り入れることが不可欠です。
たとえば、「なぜそのサービスを開発したのか」「顧客の現場ではどんな課題があるのか」といった背景は、現場にいる社員だからこそ語れる一次情報です。こうした声を丁寧にヒアリングし、文脈に沿って記事に落とし込むことで、コンテンツに厚みと説得力が生まれます。
さらに、AIが記事を評価する際も、こうした具体性や文脈のある情報が“信頼できる内容”として扱われやすくなります。
▼LLMOで求められる「編集力」について、下記の記事で詳しく解説しています。
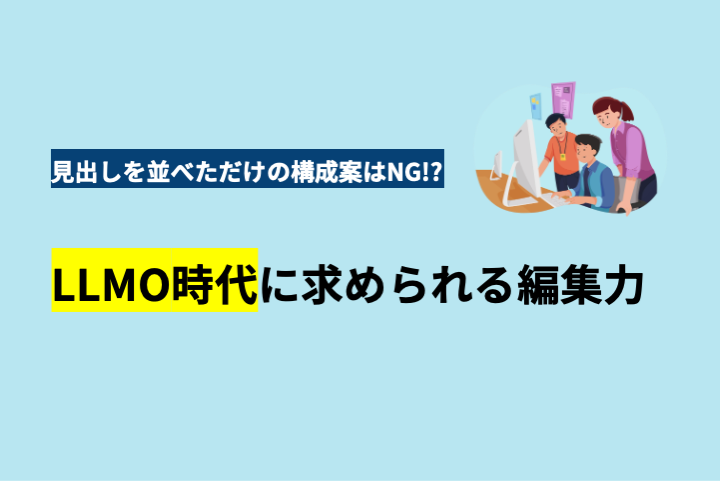
オウンドメディアの記事は「外注に丸投げ」でいい?
数多くのBtoBコンテンツを手掛けてきた弊社(リードレ)にもよく寄せられるのが、「社内の制作リソースが足りないので、記事の執筆を外注したい」というご相談です。なかには、「外注する以上、構成から執筆、修正まで任せきりにしたい」といった“丸投げ”スタイルを希望されるケースもあります。
しかし、生成AIやLLMO、そして従来のSEOにおけるEEAT対策を考慮すると、どれほど執筆スキルのあるライターに依頼したとしても、丸投げでは最適な記事にはなりにくいのが実情です。なぜなら、質の高い記事には、クライアント企業ならではの視点や一次情報が不可欠だからです。
この課題を解決する方法として有効なのが、外注先に社内の関係者(営業・開発・サポートなど)へのヒアリングを依頼することです。
たとえばリードレでは、クライアント企業に対するヒアリングをベースにした記事制作代行を提供しています。これにより、担当者の手間を最小限に抑えながら、深みと独自性のある記事=LLMOに対応したコンテンツが仕上がります。
記事の外注先の選び方
ここまで解説したように、LLMO時代のコンテンツ制作で文章作成スキルはもちろん、以下のようなスキルや姿勢を持った外注先を選ぶことが欠かせません。
・質問設計スキル:ヒアリング時に深掘りすべき論点を見極め、価値ある情報を引き出す
・インタビュースキル:ヒアリング内容を、エピソードや体験を活かしたストーリーにする
・構成スキル:文脈を意識したわかりやすい構成に整理し、読者にもAIにも伝わる記事を設計する
これらを兼ね備えたライター・編集者とパートナー関係を結ぶことで、単なる“情報のまとめ”ではない、「自社ならではの伝わる記事」を届けることが可能になります。
▼制作体制について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
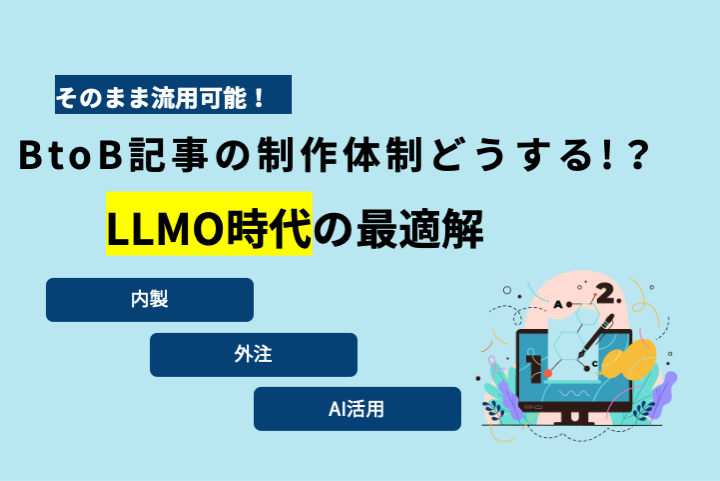
LLMO時代の記事制作にお悩みなら、実績豊富なリードレへ
リードレではこれまで、BtoB企業の事例記事やホワイトペーパーなど、多くのコンテンツをクライアントへの丁寧なヒアリングを通じて制作してきました。
だからこそ、「LLMO時代に求められるコンテンツ制作」にも確かな対応力があります。
「単なる記事作成では物足りない」「自社の強みを言語化できていない」
――そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、下記よりご相談ください。