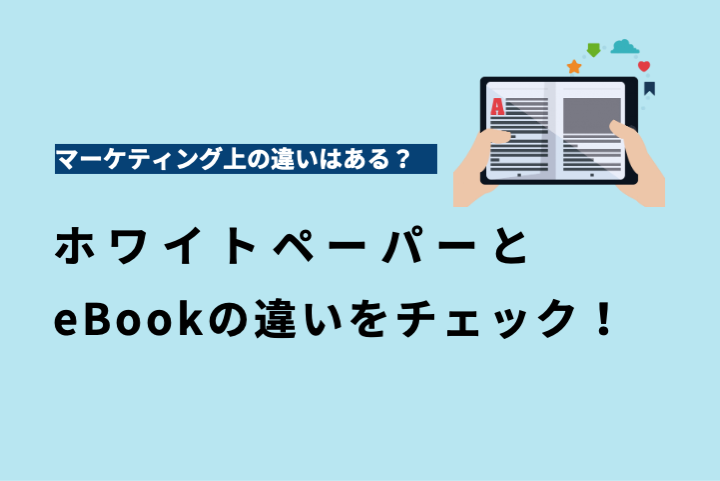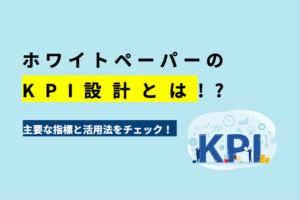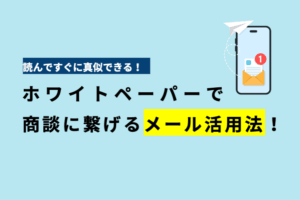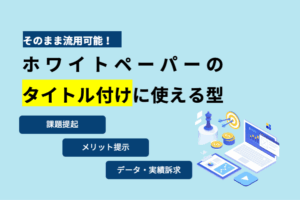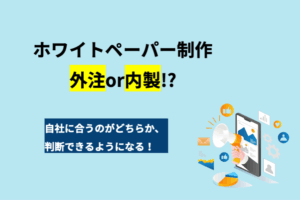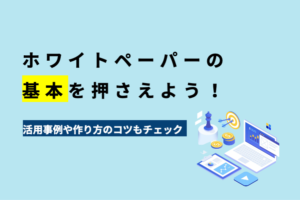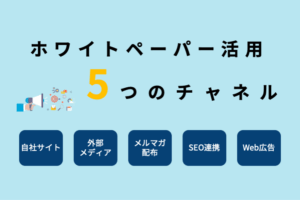「ホワイトペーパー」と「eBook」──どちらもBtoBマーケティングでよく見かける資料形式ですが、実際にはどう違うのでしょうか。
企業によっては使い分けているケースもある一方で、実務レベルでは「ほぼ同義」として扱われていることも少なくありません。
とくに日本国内においては、「eBook」という表現は一部の外資系企業やMAツール内での分類などに見られる程度であり、マーケティング資料の呼称としては「ホワイトペーパー」の方が圧倒的に主流です。
本記事では、両者の定義や背景について、詳しく整理していきます。
そもそも「eBook」とは何か?
「eBook(イーブック)」とは、本来「電子書籍」を意味する言葉で、Amazon Kindleなどに代表される一般消費者向けのデジタル書籍を指します。しかし、BtoBマーケティングの文脈では、少し異なる意味でこの用語が使われてきました。
海外マーケティングの文脈で使われ始めた「eBook」
マーケティング用語としての「eBook」は、米国を中心としたインバウンドマーケティングの中で生まれました
HubSpotをはじめとしたマーケティングオートメーション(MA)ベンダーが、リード獲得のためのコンテンツ資料を「eBook」と呼び、それが広く浸透した背景があります。
内容としては、業界トレンドやノウハウ、導入事例などをPDF形式でまとめた資料であり、日本でいう「ホワイトペーパー」と大きな違いはありません。
日本市場ではあまり定着しなかった「eBook」
一方、日本では「eBook=電子書籍」という認識が強く、BtoBマーケティング文脈で「eBook」という用語はあまり浸透しませんでした。特に、IT・SaaS企業など情報感度の高い企業を除けば、「eBook」という表現は馴染みが薄く、「ホワイトペーパー」という表現が一般的です。
そのため、Webサイトや資料請求フォーム、メール配信時などで「eBook」という表現を使用すると、かえって誤解や混乱を生む恐れがあり、現在では使われる機会も大きく減少しています。
マーケティング文脈での違いは“実質的にない”
ホワイトペーパーとeBookは、どちらもPDF形式で提供されるリード獲得用の資料として使われる点で、内容や形式、配布手法に本質的な違いはありません。多くのBtoB企業では、呼び方が異なるだけで、実際の役割や制作プロセスは共通しています。
たとえば、海外のMAツールやSaaS企業では、今でも「eBook」という表記が資料テンプレートやナーチャリング施策に残っていることがあります。HubSpotやMarketoなど、海外発のマーケティングツールでは、「eBook=ホワイトペーパー」として設計されているケースも一般的です。
一方で、国内でも一部のコラムでは、「ホワイトペーパー=専門性重視」「eBook=わかりやすさ・読みやすさ重視」としてトーンや構成の違いをもとに使い分ける考え方も紹介されています(参考:Marke Media Lab)。
ただし、こうした呼称の違いによって、資料の効果や信頼性が大きく左右されることは基本的にありません。実務において重要なのは、見込み客のニーズや検討フェーズに合った内容設計がなされているかどうかであり、名称にとらわれすぎる必要はありません。
「eBook」ではなく「ホワイトペーパー」を使うべき理由
マーケティング施策において、同じ意味を持つ「eBook」と「ホワイトペーパー」のどちらを使うか迷う場面があるかもしれません。しかし、日本国内のBtoB領域では「ホワイトペーパー」の表記を採用する方が合理的です。
まず、読者に意図が伝わりやすいという利点があります。「ホワイトペーパー」は、業界課題や解決策を論理的に解説する資料というイメージが定着しており、見込み客にも用途や中身が明確に伝わります。
さらに、BtoBマーケティングを担当する他部署や外部パートナーとの共通言語としても、「ホワイトペーパー」の方が圧倒的に通じやすいのが現状です。とくにMA(マーケティングオートメーション)やインサイドセールスとの連携時にも、「ホワイトペーパー」という呼称の方がスムーズに意思疎通できます。
加えて、SEO観点でも「ホワイトペーパー」の方が検索ボリューム・検索意図ともに明確です。「eBook」は電子書籍全般を指す一般的なキーワードであるため、BtoBマーケティング文脈では競合が分散しやすく、検索意図とのズレが生じがちです。
社内外での表記・用語統一のすすめ
マーケティング施策を展開する上で、表記や用語がバラバラな状態は、運用面でも成果分析面でも混乱を招きます。
たとえば、営業資料では「ホワイトペーパー」、ブログでは「eBook」、CTAボタンでは「資料」などと表現が混在していると、社内での管理が煩雑になるだけでなく、読み手にも意図が伝わりづらくなります。また、MAツールでのレポート分析やスコアリング設定時にも、呼称の違いが運用上のブレを生む原因になります。
そのため、ブログ・LP・CTAボタン・営業資料・テンプレート名に至るまで、「ホワイトペーパー」に統一して運用することが推奨されます。検索キーワードとしても、「ホワイトペーパー」はBtoBマーケティング領域で明確に定着している用語であり、集客・分析の観点からもメリットが大きいです。
呼称に一貫性を持たせることは、顧客体験の統一とチーム間の連携効率化、両面において重要な基盤となります。
ホワイトペーパー制作に迷ったら、まず「成功の型」を確認!
「ホワイトペーパーとeBook、どちらを使うべきか?」という悩みの多くは、実は呼び方ではなく“設計の質”にあります。伝わる構成・使いやすいフォーマット・成果につながるタイトル設計など、ダウンロードされるホワイトペーパーの条件を知ることが、マーケティングの第一歩です。
リードレでは、これからホワイトペーパー制作に取り組む方に向けて、最短で成果を出すための基本と実践ノウハウをまとめた無料のスタートアップガイドをご用意しています。
ホワイトペーパーについて、
「どんな構成がよいかわからない」
「社内リソースが足りない」
「業界に合った活用事例を知りたい」
といったお悩みがある方は、お気軽にリードレまでご相談ください。これまで500本以上のホワイトペーパーを制作してきた専門チームが、御社に最適な戦略設計を支援します。