「ホワイトペーパーを作りたいけれど、どんな内容にすれば読まれるのか分からない」
「1本作ったものの、その後の展開に悩んでいる」
——マーケティング担当者から、このような声を耳にします。
BtoBマーケティングにおけるホワイトペーパーは、見込み顧客との接点づくりから商談化までを担う重要なコンテンツです。しかし、ターゲットやフェーズに応じて適切な“型”を選ばなければ、せっかくの資料も成果につながりません。
この記事では、これまで500本以上のホワイトペーパーを手がけてきたリードレが、成果につながる5つの定番型を紹介します。それぞれの特徴や活用シーン、制作時のポイントを整理し、どの型をどのタイミングで活用すべきかが分かる内容です。
これからホワイトペーパーを初めて作る方はもちろん、既存のコンテンツを拡充・改善したい方にもおすすめのガイドです。
ホワイトペーパーを複数本制作するメリット
「ホワイトペーパーは、とりあえず1本あれば十分」
このように考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、マーケティングや営業活動の効果を最大化するためには、目的やターゲットに応じ、複数のホワイトペーパーを使い分けることが重要です。
メリット1:リード獲得フェーズに応じた資料が揃い、継続的な接点を確保できる
検討初期に効果的な課題提起型、比較検討中に響く選定ガイド型、導入直前の後押しとなる事例集型など、リードの検討フェーズに応じたホワイトペーパーを用意することで、接点の“使い捨て”を防ぎ、継続的に関係性を構築できます。
メリット2:類似テーマでも視点や切り口を変えて“刺さる”資料を増やせる
1つの商材でも、「導入の成果」「よくある失敗」「選定基準」など、切り口を変えることで複数のホワイトペーパーを制作できます。これにより、同じターゲットでも関心領域や検討フェーズに応じて使い分けができ、接触回数の増加やナーチャリング強化につながります。
メリット3:メールや営業トークと連動させやすくなる
用途に応じた資料が揃っていれば、メール配信や営業訪問などの接点で「相手の関心に合ったコンテンツをタイムリーに届ける」ことができます。資料の“ストック”が多いほど、接点設計の柔軟性も高まり、商談化までの導線がスムーズになります。
ホワイトペーパーの5つの型 活用フェーズと制作のポイント
ユーザーの情報収集段階から意思決定に至るまで、それぞれのフェーズや関心に応じてホワイトペーパーの設計を変えることで、リード獲得や商談化の確度を大きく高めることができます。
ここでは、ホワイトペーパーの代表的な5つの型について、それぞれの活用フェーズや制作時の注意点とあわせて解説します。
タイプ1:課題解決型
業界や職種でよく見られる課題を切り口に、自社ソリューションでの解決策を提示する形式です。
共感を生みやすく、認知初期の見込み顧客との接点づくりに効果的です。課題に対して「自分ごと」として反応してもらえるよう、具体的なユースケースや現場の声を盛り込むと反応が高まります。
制作ポイント:
よくある失敗として、抽象度の高い課題設定(例:「業務が非効率」など)にとどまるケースがあります。読者が自分の業務と結びつけやすくなるよう、「営業メールの返信率が低い」「採用母集団が集まらない」といった具体的な表現を用いると、資料への没入感が生まれます。
【作り方の例:自社商材が会計システムで、ターゲットが経理部門の場合】
・経理部門が抱えがちな課題にフォーカスする
・その際、課題は自社商材で解決できる/解決するためのサポートができるものを設定する
→課題例「法改正対応でやるべきことが多すぎる」
・法改正対応について、一般的な対策を提示する(複数提示すると尚良い)
→対策例:「クラウドサービスとして提供されている会計システムを使う」
・一般的な対策で生じうる、落とし穴を示す
→落とし穴の例「クラウドサービスは自社向けにカスタマイズできず、使いずらい」
・落とし穴を自社商材で解消できることを示し、その紹介をする
→「弊社の会計システムは、クラウドサービスで法改正対応でき、尚且つカスタマイズ可能」
タイプ2:選定ガイド型
製品・サービス選びの観点を提示し、自社商材を含む複数の選択肢を比較しながら紹介する形式です。
比較・検討段階にあるリードに最適で、営業資料の一部としても活用されやすいのが特長です。中立的かつ客観的に構成することで、読者の信頼を得やすくなります。
制作ポイント:
自社の製品だけを持ち上げすぎると、PR色が強くなって読者が離れてしまう恐れがあります。競合との違いを丁寧に比較し、「どういう課題にはA社が向いているか」「どんな業態には自社がマッチするか」といった視点で構成すると、読み手の意思決定を支援する有益な資料になります。
【作り方の例:自社商材がクラウド会計ソフトで、ターゲットが経理部門の場合】
・自社のクラウド会計ソフトの特長を整理する
→特長例「即日導入可能」「多様なプラグインに対応」「充実した問い合わせサポート」
・特長をふまえ、選定ポイントに落とし込む
→選定時のチェックポイント例:「導入までにかかる期間」「自社に合わせたカスタマイズ性」「アフターサポート」
・選定時のチェックポイントを先行して解説しつつ、自社商材がそれらを満足する商材であることを示す
→「弊社のクラウド会計ソフトは、これら全てを満たすツールです」
その3:導入事例集
自社商材の導入事例を記事としてまとめ、ホワイトペーパーにします。
導入事例は一般的に、「導入前の課題」「導入の経緯・決め手」「導入後の効果」の3つの要素で構成されます。こうした要素を読者に提供することで、自社商材導入のイメージが明確になるだけでなく、信頼性の向上にもつながります。
そのため、自社商材の導入検討を進めている顕在層に対して特に有効なホワイトペーパーと言えます。
【作り方】
・自社商材を導入している優良顧客にアプローチし、事例記事制作の許可を取る
・インタビュー取材を実施し、事例記事をライティングする
・同様に、複数の顧客にアプローチして事例記事を増やす
・まとまった数になったところで、それらを1つのホワイトペーパーとしてまとめる
新規の商材で既存顧客がいない場合や、商材の秘匿性が高く事例記事制作の許可が降りない場合などは、「ユースケース集」として、自社商材が解決できる課題と効果を具体的にイメージできる資料を作成するのがオススメです。
なお、事例記事は単体でもWebマーケティングを行う上で非常に効果的なコンテンツです。事例記事の作り方の詳細については、下記の記事もご一読ください。事例取材で使える「取材要綱テンプレート」もダウンロードいただけます。


その4:調査レポート型
自社商材に関係する業界や市場に関する調査を行ったうえで、それをホワイトペーパーとして公開する手法です。
最新の市場動向や業界の課題を客観的に分析したコンテンツは読者の興味・関心を惹きつけやすく、他のタイプのホワイトペーパーと比較してダウンロード数を増やしすいというメリットがあります。また、プレスリリースなどと併用することで、拡散性をより高めることも可能です。
ただし、調査に関する知見が自社にない場合、外部調査機関に依頼しなければならず、コストと時間がかかりやすい点に注意が必要です。
【作り方の例:自社商材が採用メディアで、ターゲットが求人企業の場合】
・採用に関するテーマのうち、求人企業の興味・関心を惹きつけやすいものをピックアップする
→テーマ例「Z世代の就活に関するアンケート調査 〇〇年版 」
・テーマをもとに質問を作成し、外部調査機関を通じてアンケートを実施する
・結果を資料としてまとめる
その5:セミナー資料/イベントレポート型
自社主催のセミナーや外部の展示会などで営業担当者や経営陣が登壇した場合には、その際に使用したセミナー資料を加工してホワイトペーパーとして公開するのが有効です。
特に外部の大規模な展示会やカンファレンスに関連するセミナー資料やイベントレポートであれば、多くのターゲットが関心を持つ可能性が高いので、Facebook広告やリスティング広告といったウェブ広告経由でのリード獲得のコンバージョンポイントとして効果的です。
また、参加者にも後からメールで送ることで、その後のコミュニケーションが取りやすくなるというメリットもあります。
【作成時の注意点】
「すでに投影資料としてまとまっているので、改めてホワイトペーパー化せずとも、そのまま使えばいいのではないか」といった質問いただくことがあります。
投影資料は、登壇者によるトークで内容が補完されていることが通常なので、そのままの状態で公開した場合、読者は文脈がわからなくなってしまいます。
そのため、登壇者のトークも踏まえ、読者に文脈がわかるよう改めて資料化する必要があります。
これからホワイトペーパーを制作するなら、制作実績豊富なリードレへの外注をご検討ください
リードレではこれまで、本記事で解説した5型を中心に、500本以上のホワイトペーパー制作を代行してきました。
すでにテーマが決まっている場合はもちろん、「どんなホワイトペーパーを作れば良いか分からない」「どれを優先すればいいの?」といったケースでも、企画出し・活用方法も含めてご支援させていただきます。
ホワイトペーパーについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。



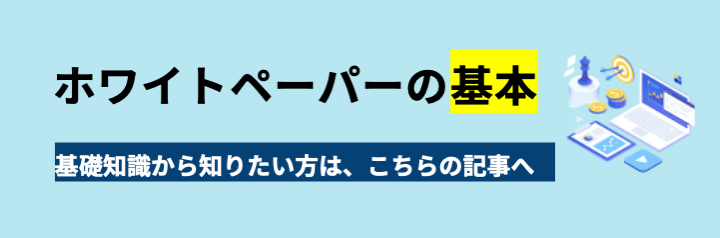


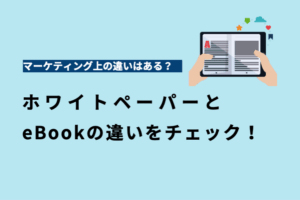
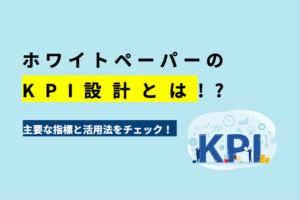
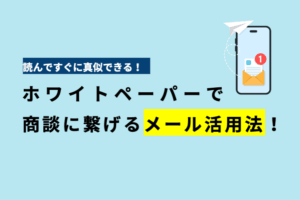
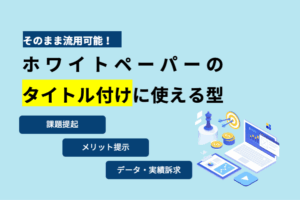
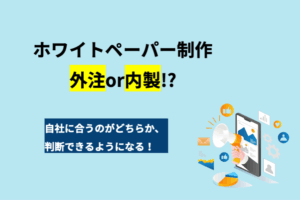
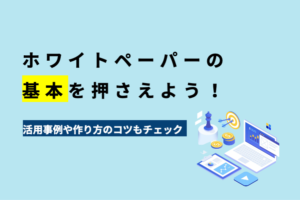
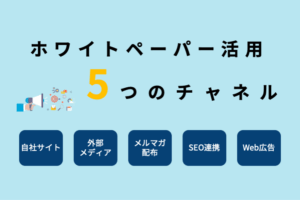
コメント