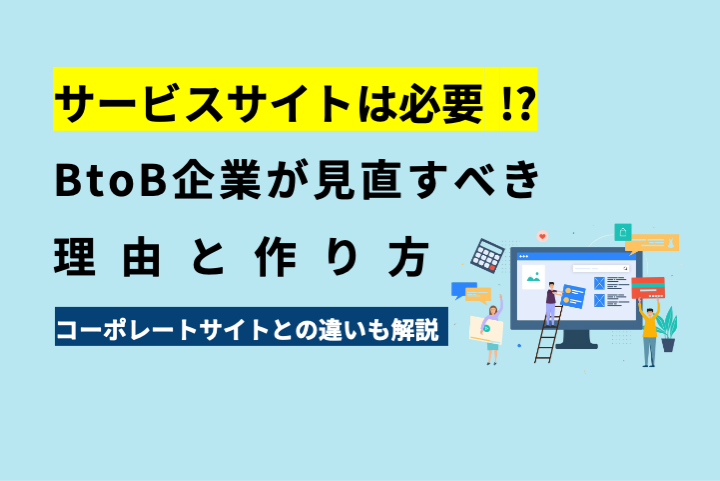「コーポレートサイトはあるけれど、なかなかWebからの問い合わせにつながらない」
そんな課題に直面した際、多くのBtoB企業が見直しているのが“サービスサイト”のあり方です。
すでにサービス単位でWeb発信を行っている企業も多い一方で、「自社のサービス紹介は、コーポレートサイトの一部にとどまっている」「どこまで作り込めば成果につながるのか分からない」といった声も少なくありません。
本記事では、BtoB企業が成果を出すためのサービスサイトの考え方、設計・制作のステップ、ありがちな失敗と成功パターンまでを体系的に解説します。
「サービスサイトはあるけれど手応えがない」「そもそもこれから作るべきか迷っている」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
サービスサイトとは? その定義と目的を再確認
サービスサイトとは、自社が提供する1つのサービスやソリューションに特化して設計されたWebサイトです。
会社情報や複数事業を包括的に掲載するコーポレートサイトとは異なり、特定のサービスについて深く・分かりやすく伝えることを目的としています。
BtoB領域では、購買までの検討期間が長く、複数の関与者が意思決定に関わることが一般的です。こうした背景から、サービスサイトには次のような役割が求められます。
- 見込み客の獲得(リード獲得)
-
SEOや広告、SNSなどからの流入を受け止め、ホワイトペーパーDLや問い合わせにつなげる導線設計
- サービス理解の促進
-
提供価値・機能・導入効果を具体的に伝えることで、意思決定者だけでなく現場担当者の納得感も醸成
- 課題意識の喚起とCTA誘導
-
顧客がまだ気づいていない潜在課題に共感を示しながら、次の行動(資料請求・相談予約など)を後押し
加えて、BtoBのサービスサイトでは「誰が書いた情報か」「どのような実績があるか」といった信頼性の担保や、検索意図に沿った文脈的な構成、検討フェーズごとのナーチャリング対応力も重要なポイントです。
コーポレートサイトとの違いと併用の考え方
「コーポレートサイトがあるから、あえてサービスサイトを作る必要はないのでは?」
このような声をいただく機会も少なくありません。しかし、両者の役割や設計思想には明確な違いがあります。
コーポレートサイトとサービスサイトの主な違い
| 比較項目 | コーポレートサイト | サービスサイト |
|---|---|---|
| 主な目的 | 企業情報の発信・信頼形成 | サービス単位でのリード獲得・ナーチャリング |
| 対象読者 | 社内外全てのステークホルダー (投資家、採用、メディアなど) | サービスに関心のある見込み客 (導入検討者・現場担当者など) |
| 情報の構成 | 会社紹介、ニュース、IR情報、事業紹介などを横断的に掲載 | 顧客の課題起点で構成。サービス理解→導入意欲→CTAまでの文脈を重視 |
| CTA設計 | お問い合わせ、採用エントリーなど汎用的 | ホワイトペーパーDL、資料請求、個別相談など明確な導線設計 |
コーポレートサイトは「会社全体の情報を網羅するハブ」、サービスサイトは「サービス単位で成果を生む専用チャネル」という位置づけです。
この違いを理解せずに、会社紹介ページの中でサービスの内容について簡単に触れているだけでは、検索流入も問い合わせも思うように増えません。
コーポレートサイトとサービスサイトはどう併用すべきか?
理想的な活用方法は、「コーポレートサイト → サービスサイト」へと自然に誘導するハブ&スポーク構造です。
たとえば、コーポレートサイトの「事業紹介」ページに、各サービスサイトへのリンクを配置することで、
・企業ブランディングはコーポレートサイトで
・実際のリード獲得や顧客教育はサービスサイトで
といったように、目的ごとに最適な情報設計を分担できます。
とくにBtoBにおいては、社内での情報共有や検討プロセスが複雑になりやすく、複数チャネルからの導線設計があることで検討の質とスピードが大きく向上します。
「サービスの魅力を十分に伝えきれていない」と感じている場合は、まずはコーポレートサイトとの役割分担を見直すことから始めてみましょう。
▼コーポレートサイトとの違いについて、より詳しく知りたい方は下記の記事もご一読ください。
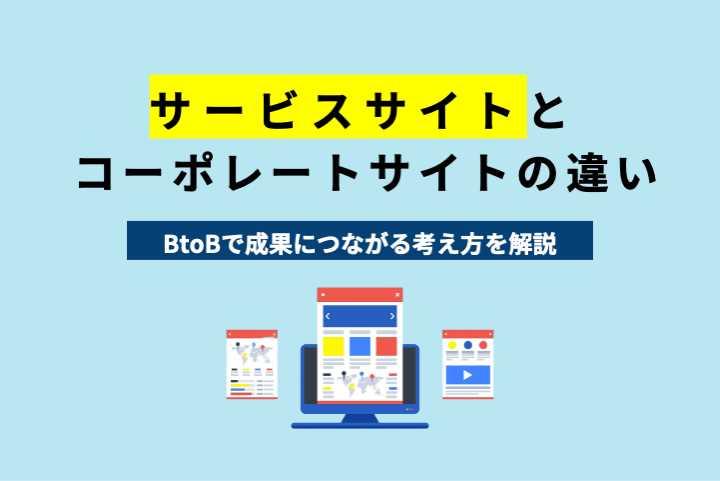
BtoBで成果を出すサービスサイトの構成設計
サービスサイトを作るうえで最も重要なのは、「何を伝えるか」ではなく「どう伝えるか」です。
BtoB領域では、単にサービスの機能や特徴を並べるだけでは見込み客に響きません。課題共感から解決へのストーリー設計と、適切なCTA(行動喚起)設計が成果を左右します。
ここでは、成果を出すためのサービスサイト構成の原則と、実践しやすいフレームをご紹介します。
構成設計の原則:課題解決起点で考える
BtoBのサービスサイトでは、「自社が何を提供できるか」ではなく、「顧客が何に困っているか」から出発することが重要です。
訪問者は、解決したい課題やニーズを持って検索や流入をしています。そのため、構成の起点はサービスの機能ではなく、見込み客の課題に置くべきです。
見込み客が「納得しやすい順番」で情報を設計する
サービスサイトでは、ただ機能や特徴を並べるだけでなく、「なぜそのサービスが必要なのか」を順序立てて伝える工夫が必要です。
たとえば次のような順番で構成すると、読み手の理解や納得感が高まります。
1 こんな課題を感じていませんか?(課題提起)
2 その原因は〇〇にあります(理由)
3 当社のサービスは、その課題をこうやって解決します(解決策の紹介)
4 実際に、このような成果が出ています(事例・データ)
このように「読み手が共感しやすく、納得しやすい順番」で情報を伝えることで、ただのサービスの特徴紹介ではなく、価値の伝わるページ構成になります。
見込み客の検討ステージに応じた情報の出し分けも重要
BtoBの見込み客は、いきなりサービスを導入するわけではなく、次のようなステップを踏んで意思決定をします。
・情報収集段階(まだ自社の課題と、その原因があいまい)
・比較・検討段階(自社の課題を解消するサービスを比較・検討している)
・導入前段階(サービスについて、詳細な条件などを確認している)
そのため、サイト内には次のようなコンテンツを用意し、各ステップで知りたい情報にすぐアクセスできるようにしておくことが大切です。
- 情報収集段階
-
サービスの目的や導入メリットを紹介したページ、課題を解説するコラムやホワイトペーパー
- 比較・検討段階
-
事例紹介、料金ページ、他社との違いを説明したページやホワイトペーパー
- 導入前段階
-
サービス資料や、導入フローがわかる資料、よくある質問に回答するページ(FAQ)
こうした工夫をすることで、「サイト内に何が書いてあるか分からない」「知りたい情報にたどり着けない」といった離脱を防ぐことができます。
CTAの種類と配置は“多層”に設計する
BtoBでは、訪問者が即座に問い合わせを行うケースは少なく、検討ステージに応じたCTAの配置が必要です。
・情報検討段階:ホワイトペーパーダウンロード
・比較・検討段階:導入事例ページやFAQページへの誘導
・導入前段階:無料相談や見積もり依頼
このように、1ページ内に複数のCTAを配置し、今すぐ客とその前段階の見込み客の両方に対応する設計が、成果につながるポイントです。
サービスサイトの基本フレーム(例)
「サービスサイトにどのような要素を入れたら良いのかわからない」という方は、まず下記のような構成で進めると良いでしょう。
○トップページ(課題提示+サービス概要++主要CTA)
┗導入事例
┗コラム
┗お役立ち資料
┗CTA
必要に応じて、サービス詳細やFAQのページを追加していくことをおすすめします。
参考として、リードレのサービスサイトもぜひご覧ください。
サービスサイト制作から公開、運用までのステップと注意点
サービスサイトは「作って終わり」ではなく、成果につなげるには戦略的な設計と継続的な運用が不可欠です。
ここでは、BtoB企業がサービスサイトを構築・改善していくための代表的なステップと、その際に押さえておきたい注意点を紹介します。
BtoBのサービスサイトでは、「問い合わせ」「資料請求」「顧客理解の促進」など、複数の目的を同時に果たす必要があります。そのため、まずは目的ごとの優先度を整理し、どのような導線やコンテンツでそれらを両立するかを設計することが重要です。
加えて、ターゲットとなるペルソナや検討フェーズを明確にし、それぞれに応じたKPI(例:DL数、CVR、回遊率など)を定めておくことで、サイト全体の構成や改善指標もブレにくくなります。
設計段階では、カスタマージャーニーをもとに必要なページ構成と情報の流れ(ワイヤーフレーム)を決定します。
BtoBのサービスサイトは、検索エンジンや広告、ホワイトペーパーなど複数の経路から流入があるため、「トップページから順に読む」という想定だけでは不十分です。
・どの経路から訪れても、次に進むべき動線が設計されているか?
・各ページで、どんな情報を届け、どんな行動を促すべきか?
・CTA(資料請求・相談予約など)をどのページに、どの位置で配置するか?
これらの点を意識しつつ、「訪問者の視点」で流入経路ごとに最適な体験を設計することが成果につながります。
実制作では、構成案に沿って文章・ビジュアル・UIを整えていく作業が中心になります。BtoBサービスの場合は以下の点を特に意識しましょう。
・専門用語をかみ砕いて説明できているか
・事例・データ・一次情報で信頼性を担保できているか
・モバイル/PC両対応でストレスなく閲覧できるか
とくに「誰がどんな立場で読むか」を意識し、読み手に届く言葉選びが成果につながります。
公開後は、アクセス解析ツールやヒートマップを使い、「読まれている箇所」「離脱が多いページ」「CTAのクリック率」などを確認します。
・CTAの文言を変えてCVRを改善
・読了率が低いページを構成ごとリライト
・新たな流入キーワードに合わせたコンテンツ設計
こうしたPDCAを継続できるかどうかで、サイトの寿命と成果が大きく変わります。
問い合わせや資料DLが発生した後、そのまま放置してしまっては、せっかくのリードも商談につながりません。特別なツールを使わなくても、既存のコンテンツを営業活動や社内共有に活用する方法は数多くあります。
・ダウンロードしてくれたユーザーに、手動でフォローメールを送る
・サービスサイト内の導入事例ページを、営業資料やメールに添付して再送
・よくある質問(FAQ)ページを、社内の営業・CS部門と共有し、トークの一貫性を保つ
「とりあえず作ったまま」にしないためにも、コンテンツを“使い倒す”意識が成果を分ける鍵です。
サービスサイトで成果が出る企業、出ない企業の違い
同じようにサービスサイトを制作しても、問い合わせや資料請求につながる企業と、成果が出ない企業があります。
その違いは、見た目やページ数の多さではなく、“伝え方”と“設計の深さ”にあります。
【よくある失敗例】
• 会社紹介に終始してしまい、「誰のどんな課題を解決できるのか」が伝わらない
• LPのように1ページで完結しており、顧客の検討ステップに対応できていない
• CTAが目立たず、行動喚起が弱い(例:「お問い合わせ」だけ)
【成功例】
• 「よくある課題→自社の解決策→事例」の流れで、自然に問い合わせまで誘導
• 導入事例・料金表・FAQ・比較コンテンツなどを揃え、複数のペルソナに対応
• 一次情報やリアルな声(導入前後の変化・担当者インタビュー)を掲載して信頼感を強化
リードレが支援した製造業の企業では、サービスサイトの設計を見直し、リニューアルを行なったことで、資料ダウンロード数が従来の約3倍に増加しました。
サービスサイトの制作会社はどう選ぶ?
最近では、ノーコードやローコードツールの普及により、専門知識がなくてもWebサイトを制作できる環境が整いつつあります。
ただし、BtoBのサービスサイトで成果を出すためには、戦略設計や構成・コンテンツ制作など複数の視点が必要となるため、自社だけで対応するのはハードルが高いという企業も少なくありません。
そのため、限られた期間で確実に成果につなげたい場合は、外部の制作パートナーに依頼する方が効率的です。とはいえ、制作会社の選び方を誤ると、期待した効果が得られず、時間もコストも無駄になるリスクがあります。
発注前に押さえておくべき3つのポイント
まずは、発注前に次の3点を整理しておきましょう。
1 サービスサイトで優先的に実現したい成果は何か?(問い合わせ獲得、資料請求、顧客理解の促進など)
2 どの成果を、どの指標で測るか?(例:資料DL数、CVR、滞在時間など)
3 誰に向けて、どのフェーズで届けるのか(例:ペルソナやターゲットなど)
これらを整理しておくことで、制作会社との打ち合わせでもブレのない要件定義が可能となり、成果につながる設計方針が見えやすくなります。
制作会社選びの5つの視点
制作会社を選ぶ際は、以下のような観点で比較すると失敗しにくくなります。
- BtoB実績
-
BtoBの分野での実績があるか
- コンテンツ力
-
構成やライティングまで一貫して対応できるか
- 運用支援
-
公開後の改善提案やレポーティングに対応しているか
- SEO知見
-
BtoB向けのSEO設計に対応できるか
- ヒアリング力
-
サービスの強みを引き出す力があるか、質問が的確か
リードレが提供する、成果につながるサービスサイト構築支援
株式会社リードレでは、これまでBtoB領域に特化したサービスサイトをはじめ、ホワイトペーパーや事例記事、コラムなど、Web経由の問い合わせにつながるコンテンツを数多く制作支援してきました。
サービスサイトに関連して、次のようなメニューを提供しています。
・サービスサイトの構成設計・ワイヤーフレーム作成
・ペルソナやカスタマージャーニーに基づくライティング
・サービスサイト構築・運用
・公開後の改善提案(ヒートマップ分析、コンテンツ制作支援)
「コーポレートサイトの運用だけで、Webからの問い合わせが増えない」
「Web経由の問い合わせ増にあたり、何から手をつけていいのかわからない」
このような課題を抱えている企業に向けて、現状に応じて最適な提案をさせていただきますので、ぜひ下記よりお気軽にご相談ください。