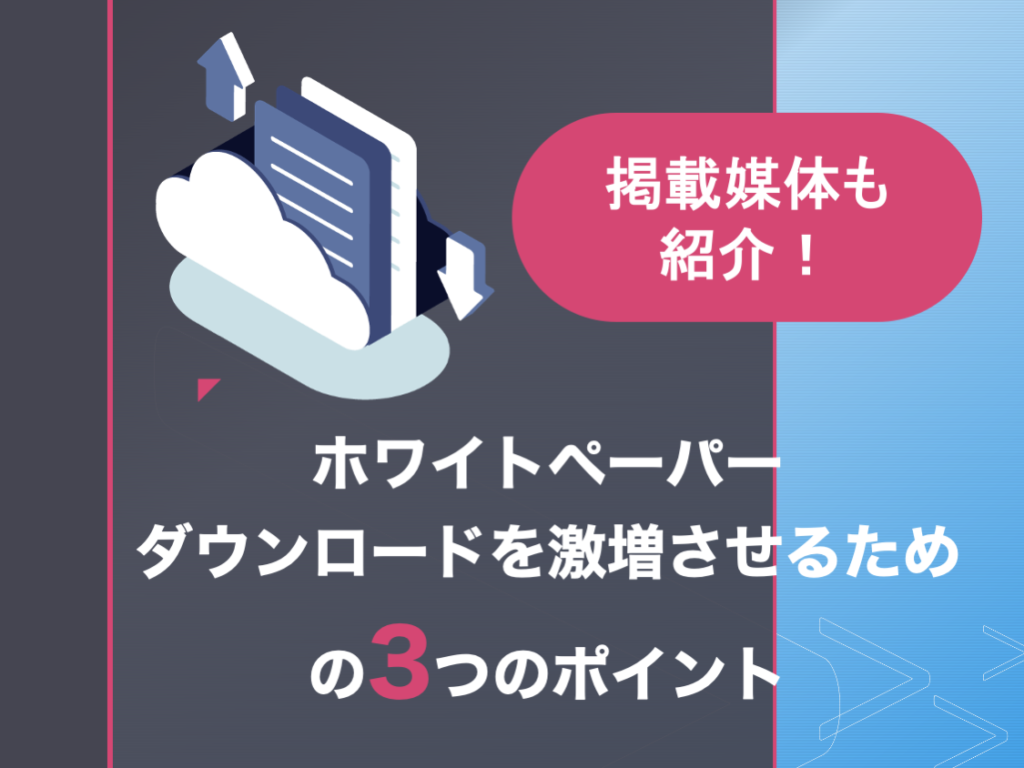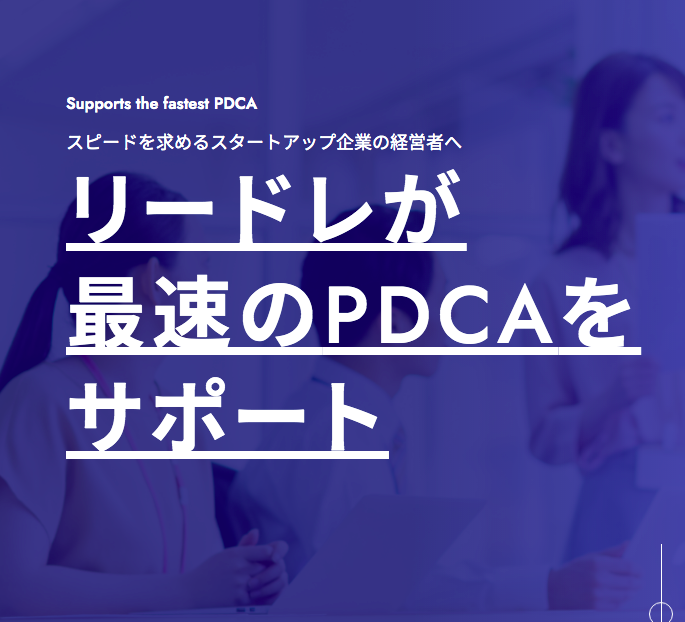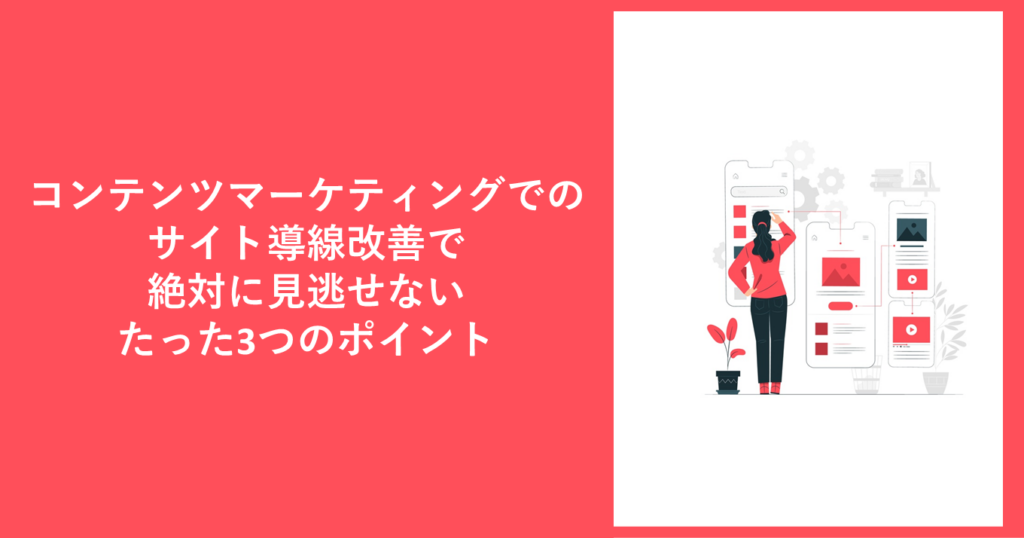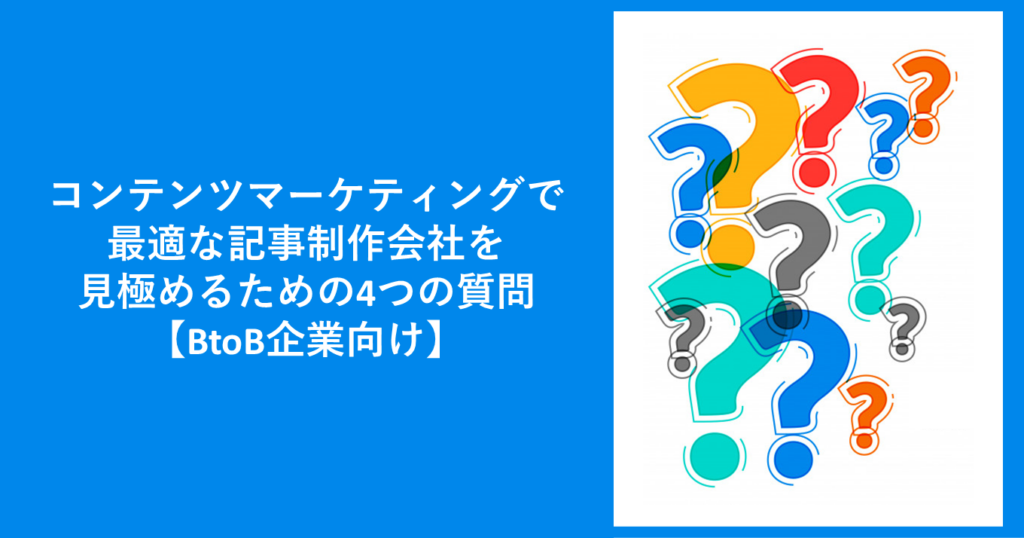ブログ
ホワイトペーパー
【人事リード獲得編】ホワイトペーパー制作のポイント
人材管理ツールや人材育成サービスなどを提供しているBtoB企業が、人事部門のリードを獲得するためのホワイトペーパーを制作する際に押さえるべきポイントを解説しています。 また、以下のホワイトペーパー構成案サンプルを無料でダウンロードいただけます。 ①人事採用部門に向けた福利厚生切り口のホワイトペーパー構成案 ②副業人材を集めようと思っている企業をターゲットにしたホワイトペーパー構成案 ③短期離職に課題がある企業の人事部向けのホワイトペーパー構成案 ④在宅勤務のトラブル事例とその解決策を示した人事向けホワイトペーパーの構成案 【このコラムで得られる人事ホワイトペーパー制作のポイント】 ・ターゲットが興味を持ちやすいトレンド・人事部門が抱えているよくある課題・リードを獲得するための導線設計の工夫・人事部門向けホワイトペーパーの構成のコツ/構成案サンプル 【人事部門のリード獲得を狙う代表的な商材】 ・人材管理ツール(例)スマートHR・タレントマネジメントツール(例)タレントパレット・勤怠管理ツール(例)ジョブカン・ダイレクトリクルーティングサービス(例)ビズリーチ・人材育成サービス(セミナー、研修など)(例)スカイディスク・福利厚生サービス(例)ベネフィットワン・健康管理サービス(例)おかん このような商材を提供しているBtoB企業が、人事部門のリードを獲得するためのホワイトペーパーを制作する際に押さえるべきポイントを次項から詳しく解説していきます。 人事部門のリードを獲得するためのホワイトペーパー制作3つのポイント 制作ポイント1:タイトルに人事に関するトレンドを盛り込む 誰もが納得するような素晴らしい内容のホワイトペーパーでも、対象となるターゲットは実際にダウンロードをするまで中身を見ることができません。そして、ターゲットはホワイトペーパーの設置されたランディングページや流入元のSEOコラムの内容をもとに、そのホワイトペーパーにダウンロードする価値があるかどうかを判断します。 そのため、ホワイトペーパーそのものだけでなく、ランディングページやSEOコラムの内容についても「ターゲットが求めている情報」とリンクさせることが重要です。 たとえば人事部門向けのホワイトペーパーの制作にあたっては、人事部門を取り巻く次のようなトレンドを盛り込んだタイトル・内容にすると、リード獲得につながりやすいです。 ・生産年齢人口の減少・タレントマネジメント・健康経営・副業解禁・フリーランサー・テレワーク/リモートワーク 制作ポイント2:タイトル・資料概要で人事に関する課題を喚起する より多くのターゲットにホワイトペーパーをダウンロードしてもらうためには、ターゲットの多くが抱えているよくある課題を喚起することが効果的。 次のような方法で課題を喚起して、ダウンロードを促しましょう。 「採用した人材が定着しない…とお悩みの人事担当者必見」といった形でタイトルに盛り込むランディングページや流入元のSEOコラムには、タイトルだけではなく、よくある課題とその解決策を解説している資料であることを示した資料概要も掲載する 人事部門向けのホワイトペーパーでは、たとえば次のような課題を喚起すると良いでしょう。 人事部門の管理職(部長/マネージャーなど)が抱える課題 採用目標を達成できそうにない…人材の流動性が高く、才能のある社員を見出すことができない…社員情報が散逸していて有効に活用できていない… 人事部門の現場担当者が抱える課題 募集をかけても人が集まらない…人材育成のため社外研修を積極的に行っているが、効果が今ひとつ…社員の時間外労働が減らない… ポイント3:商材紹介への“つなぎ”を考える ホワイトペーパーの資料構成は、いわゆる製品/サービス紹介資料や営業資料とは異なります。前提課題の確認やその解決策を一般論として語ったうえで、ごく限られたボリュームで自社商材を紹介するように構成していきます。 たとえば全12ページのホワイトペーパーであれば、自社商材の紹介には1〜2ページ程度だけを割くというのが一般的です。 そのため、前提課題や一般論としての解決策から自社商材の紹介へいかに違和感なくつなげられるかを考えることが重要です。具体的には、ホワイトペーパー制作にあたってはまず次のような大まかな流れを考えておくと違和感なく仕上げることができるでしょう。 【(例)人材採用代行サービスへの“つなぎ”】対象商材:人材採用代行サービスターゲット:人事部門の管理職(部長/マネージャーなど)前提課題:募集をかけても人が集まらない 1.一般的な解決策の提示: ・求人媒体やメディアへの出稿・採用エージェント会社の活用 2.一般的な解決策の問題点: ・求人媒体やメディアの数が多く、どれを選択すれば良いかわからない・複数の求人媒体やメディアを活用すると、費用対効果が合わない 3.商材紹介: ・○年に渡って蓄積された採用ノウハウを活かし、予算に応じて適切な求人媒体・メディアを選定。募集要項の書き方から面接前後の連絡まで、採用に関する業務を一貫してお任せいただけます。 以上3つのポイントを押さえて制作することで、人事部門のリード獲得につながるホワイトペーパーに仕上げることができるでしょう。 ホワイトペーパー制作はリード獲得できないと意味がない。 リードレでは、良質なホワイトペーパー=リード獲得ができるホワイトペーパーと定義しています。 大手媒体代理店時代、コンサルとして支援させていただいている述べ1500社以上の企業様のデータからリード獲得ができるホワイトペーパーを制作します。 まずは、こちらのページから気になる資料をダウンロードしてください。
2022-04-15